������ɴ̾��
�֤�ɴ̾��
����ɴ̾��
��������鸫���뻳
����ɴ��
����ɴ�㻳
��̸��λ�(ʬ���л�������)
���ܤλ���ɸ��1003��
����ɴ̾��(2019ǯ)
���ܤλ�1000
������դλ�350
����ɴ����
����̾����
��������̾��50
��̸��λ�50
������դλ�350(2010ǯ��
����λ��⤭100��
¿����¢����50
�⤤�Ƥߤ������ܤ�̾��
����365��
³��Ÿ˾�λ�ι
�����̾���٥���100
���������껳130
�������120
�ٻΤθ����뻳223
�������㻳30�����
����¿����¢����
50���ֲ����ܳ�̾��
�������������60
����¢
��û�(�֤�������) / ������/������/���/�ٻ�/���㻳/¢����/����/̯����
�ǽ���������ޥ쥳��YamaReco
�г�����۾���������������

��û��Ϻ�̸�����ԤȲ���Į�ˤޤ�������Ω���Ǥ���ɸ���1304���ǡ�������ɴ̾��������Ӳ֤�ɴ̾�������ꤵ��Ƥ��ޤ���
���ѷ��ΰҸ�����ѤƤ��ޤ�������¦�μ��̤��г���κη����ʤߡ�ǯ���ɤ����Ȥ˻��Ƥ��Ѳ����Ƥ��ޤ���
��̾�Ϥ����Ĥ�ܤ����Ǥ��ꡢ���ĤƤθƾΤϡ�̯�����ס�������֡ʤ������������ˡס�������ʤ����ߤĤ�ޡˡפʤɤ����ޤ���"��û�"��̾�ϡ�������º�ʤ�ޤȤ�����Τߤ��ȡˤˤ��ʤऽ���ǡ��ब�����κݤˡ�������ǰ�����λ��˹��ɤ���Ǽ����������������Ƥ��ޤ���
���Ť���γ�����

��û�������Ω���ϡ�����γ���л���ͳ�褷�ޤ������椫��ϡ����丶��Ū���ࡦ���Υɥ�Ȥβ��Ф�ȯ������Ƥ��ꡢ��2��5���3��ǯ���Τ�Τȿ�¬����Ƥ��ޤ���
����βл���ư�����ޤ�Ⱦ����˥��̤�ȯã�����䤬���г���ؤ��Ѥ��ޤ����г����Τ�ܤ������Υץ졼�Ȥϡ�Ĺ��ǯ������̾夷�������������������Φ�ץ졼�Ȥˤ֤Ĥ���ޤ��������Υץ졼�Ȥϳ��¤����߹���ǹԤ��ޤ����������Τΰ�����������Ʋ����夲���ޤ������������줿�ϼ��ϡ��ղ��Ρʤդ������ˡפȸƤФ졢���줬�����Ȳ����뤳�Ȥ�δ����³�������Ȥʤ�ޤ�����
��û�����¦���̤��г���Ǥ��������β�����¦�ϳ���л����ϴ䤬�Ѽ������п���ʤ�礯���礯����ˤǤ���
���ߤⷡ�郎³����۾�

��û�����¦����į���ȡ��Ͱ�Ū�˺��줿��ȩ���褯��Ω���ޤ����г���κη��ϡ���������˻Ϥޤ긽�ߤ�Ԥ��Ƥ��ޤ���
����ˤ���Ȥ��ޤˡ������ʥޥ��Ȥ�ȯ�˲���ʹ�����Ȥ�����ޤ������ˤ�����줿�г���ϡ���ľ�˷���줿�ȥ�ͥ������Ȥ��졢�ϲ��Υ٥�ȥ���٥��Dzù���ؤȱ��Ф�Ƥ��ޤ���

��û������г��Ͻ��٤��⤯�ɼ��Ȥ��졢�����Ȥμ�������Ѥ����ޤ���
��¤���줿�����Ȥϡ�����ޤǴ�����̺Ҥ������ԻԳ�ȯ�ˤ����Ѥ��졢�ӥ�俷��������®ƻϩ�η��ߤ��礤�˹����ޤ������ϸ��ˤϸ��Ѥ����ߡ��Ͼ컺�ȤȤ��ƷкѤ�٤��ޤ�����

���ĤƤλ�ĺ��ɸ��1336m�Ǥ�����1970ǯ��˺η���ˡ��ž�����ޤ�졢��ĺ���鳬�ʾ����ڤ������٥�����åȹ�ˡ�Ǥη��郎�Ϥޤ�ޤ���
���Τ������������������û����ֿ��ҡפϰ��ߤ���ޤ�����������ɸ���41m�㤤1295m�Ȥ��ƻ����������ߤ��졢�컳ĺ��1980ǯ�����ˤǼ����ޤ��������ߤ�ɸ���1304m�Ǥ�����2002ǯ��Ĵ���Ǻǹ�������9m�⤯�����줿����Ǥ���
������º��㫤뿮�Ĥλ�

��û��ϸŤ���ꡢ�������魯���Ȥ��ƿ����Ƥ��ޤ���
��ĺ�ˤϡ���û����ֿ��ҡפ��ú¤��Ƥ��ꡢ����Τ����ΰ����������º�Ǥ������Ҥ��̤����л�ƻ�ϡ�ɽ��ƻ�ס���ƻ�פʤɿ��Ĥˤ��ʤ�̾���դ��Ƥ��ޤ���

ɽ��ƻ��ϩ˵�ˤϡ������Сʤ��礦�ᤤ���ˡפ��֤���Ƥ��ޤ���
�����Ф����ҼԤΤ����ƻ����٤ǡ���Ǥ褯�������ޤ�����û��ϡְ��Ļ��פ�1���ܤȤ�����ĺ����û����ֿ��Ҥ�52���ܤ˿����Ƥ��ޤ���
�ե��ۤ����������Ϥ��˾����

��ĺ����û����ֿ��Ҥ���ˤϡ��ե��˰Ϥޤ줿�����Ÿ˾��ס�����Ÿ˾��פ�����ޤ����ǹ�������ξŸ˾��δ֤����֤��줿�֤��ݡ���Ǥ������ե��γ�¦�ˤ���Ƨ�����뤳�ȤϤǤ��ޤ���

���Ÿ˾�����¦�θ����餷��ͥ��Ƥ��ꡢξ���������ֻ����־뻳�����̥���ץ��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
�ޤ��㲼��˾��ΤϺη��������Գ����դ��ӻ�����μǺ������䤫�ʥ��ݥ���Ȥ�������ޤ���
�г����Ϥι⻳��ʪ����������

��û��̼��̤ϡ��г������ͭ�ο�ʪ��¿�����餷�Ƥ��ꡢ����û��г������ü쿢ʪ����פȤ��ƹ��ŷ����ǰʪ�˻��ꤵ��Ƥ��ޤ���
��û���ͭ��Ρ֥����֥��略����פ䡢�֥ߥ�ޥ��������ס֥֥����ޥ����פʤɤ��������������Ƥ��ޤ�����Ω���ػ߶��Τ����л��Ԥ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
���Ťʲ֡��ϡ����줾��γ��ִ��ˡ���û������ۡפ�Ÿ������ƴվޤǤ����礬����ޤ���
��ǥ륳����

4����49ʬ��6.6km
���Ļ���58ʬ�ˢ���ư���43ʬ�ˢ�����ι����82ʬ�ˢ���û���29ʬ�ˢ����饸���ܡ�77ʬ�ˢ����Ļ��

�ݥԥ�顼���л��롼�Ȥ�ɽ��ƻ�Ǥ��������ܤΰ��Ļ������ȯ���ޤ���Ļ���ξ�Ƥ˺¤������ϡ��ۡ������Ѥ�ϵ�Ǥ�������������¿��ϵ���Ĥ�����û��ˤ⺬�դ��Ƥ��뤳�Ȥ�ʬ����ޤ���
���Ļ���������־�Ϥ���ޤ������ؤ�Х����Υ��Ƥ��ޤ����������̵��ؤǸ��������ϡ�����Ŵƻ�ֲ����ءפ��饿�����������Ѥ��뤫����2�����⤯ɬ�פ�����ޤ���

���Ф餯�����褤�ι���ƻ��³���ޤ������������ܤ�����л�ƻ������ޤ���
���ϤϤޤä����˿��Ӥ���˰Ϥޤ�Ƥ��ޤ���

����ư��פϽ�Ȭ���ܤǡ��⤵5m�ۤɤ���ȿ�줬����ޤ���
�����ƤˤϿ夬���ä��ڥåȥܥȥ뤬���������¤�Ǥ��ޤ�������ϻ�ĺ�ȥ���ǻ��Ѥ��뤿��ο�ǡ��л��Ԥ�Ǥ�դDZ��Ӿ夲�˶��Ϥ��ޤ���
������㬤�������Ƥ��ꡢ���Ԥΰ����뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���

��Ȭ���ܤ������ܤδ֤ˤ�ƻ�Ŀ�㬤��ú¤��Ƥ��ꡢ��ˤϾ��֤���г��䤬����������Ƥ��ޤ��������ϻ�ĺ����û����ֿ��Ҥǡִ����СפȤ��Ƽ�����줿��Τǡ����ΤҤȤĤҤȤĤˤϴꤤ����������Ƥ��ޤ���

���������ܤ���ȡ�����ι���פǤ������ε��ڤ�Ω��ʿ��ʾ��ǡ��ٷƤ�Ŭ���Ƥ��ޤ���
����ι��������ƻ�ϡ��ڤκ����褯ĥ��Ф��Ƥ��ޤ����г���⤴���Ĥ��褦�ˤʤꡢ�Ĥޤ����ʤ��褦���դ��ޤ���

�������ܤλ�ĺ����ζ��ˤϡ������ȥ��줬���äƤ��ޤ���
���˿ʤ�ȸ������ܤ���û����ֿ��Ҥζ���Ǥ�����ư�줫����٤�����ϡ���̳�ꤽ�ФΥޥ�ۡ��뤫�����夷�ޤ���

��ĺ����������ظ����������ޤ���
�������Ȥΰ����Ǥ���֥��饸���ܡפޤǡ��ޤʲ��꤬³���ޤ���
���饸���ܤ�ƻ������ʬ����ޤ��������Ǻ���˲����а��Ļ������ޤ���

�⤦������ƻ�Ͼ��������Ф��֤�ƻ�Ǥ���
���֤�;͵������С�����������������ͳ��������礭�����뤳�Ȥ��ǽ�Ǥ���
����������ϡ��������뻳�η�����û���į��뤳�Ȥ��Ǥ��ޤ���
| ��� |
���Ļ�� ����28�� ��ΩƲ �������� ������ |
|---|
���ܾ���
| ɸ�� | 1304m |
|---|---|
| ��� | �̰�35��57ʬ05��, ���139��05ʬ52�� |
| ��ĺ | |
|---|---|
| �ȥ��� | ̵�����ߵ��������Բ� |
���β��� - [��ŵ��Wikipedia]
��û��ʤ֤������֤�������ˤϡ���̸���������������ԤȲ���Į�ζ����˰��֤��뻳������¿������Ω�����°���롣�������Ϥ���¦�ˤ��ꡢɸ���1,304��ȥ롣�������������ҤǤ���������Ҥο��������Ǥ��롣̵��ʸ���仺��������פϡ���û��ȶ����ؤ�꤬����Ȥ���Ƥ��롣
��̾�������֡�̯������������Ȥ⤤������ͭ��Υ����֥��略�����Ϥ����г����Ϥι⻳��ʪ��������������û��г������ü쿢ʪ����פȤ��ƹ�����ŷ����ǰʪ�ȤʤäƤ��롣
��û�����¦���̤��г�����Ǥ��ꡢ�г���κη�������˹Ԥ��Ƥ��롣�г���η��ˤ�껳�Ƥ��Ѳ������������컳ĺ�ϴ��˼����Ƥ��롣�ޤ�����ˤ��컳ĺ�ˤ��ä���ʸ���夫�����ޤǤˤ�������ˤΤ��ä����İ��ס���䷲����Ǥ��Ƥ��롣
�ն�λ�
���ξ��˴�Ϣ������
���ξ����̤��л��롼��
����¢ [������]
���Ѹ��̵���
�֡��Х����� �ż֡��Х��� ��������
���ѥ�٥����ϥ�٥�
��������롼��
-
��� ������ ����¢

 1��2��3��4��5��6��7��8��9��10��11��12���Կ�����Υ���������ͥ�줿����¢�ν����ʤ��顢����Գ��Ϥ��鸫����г���κη��ˤ���ˤޤ����Ѥ�����û��� �������ʤ��顢���̤�̤���˼�Ĥ����μ������Ĥ��졢����¢���㻳�ʤ����Ѳ����٤�����⤭��ڤ��ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ���
1��2��3��4��5��6��7��8��9��10��11��12���Կ�����Υ���������ͥ�줿����¢�ν����ʤ��顢����Գ��Ϥ��鸫����г���κη��ˤ���ˤޤ����Ѥ�����û��� �������ʤ��顢���̤�̤���˼�Ĥ����μ������Ĥ��졢����¢���㻳�ʤ����Ѳ����٤�����⤭��ڤ��ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ��� -
��� ������ ����



 1��2��3��4��5��6��7��8��9��10��11��12���������̾���������������ɤ���ä��Ф��Ƥ⤤�����ΰ�ġ�
1��2��3��4��5��6��7��8��9��10��11��12���������̾���������������ɤ���ä��Ф��Ƥ⤤�����ΰ�ġ�
����û��� �˴�Ϣ���뵭Ͽ�ʺǿ�10���
����¢
30 62
2026ǯ02��23�����������



 ��û��λ��Ե�Ͽ��
��û��λ��Ե�Ͽ��

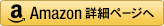












 Loading...
Loading...

