日本二百名山
新・花の百名山
山梨百名山
甲信越百名山
中央線から見える山
ヤマレコ30選
日本の山岳標高1003山
山梨県の山(分県登山ガイド)
甲州百山
日本の山1000
東京周辺の山350
日本百霊山
東京周辺の山350(2010年)
関東の山歩き100選
歩いてみたい日本の名山
山登り365日
名湯・秘湯の山旅
低山トラベル30座
展望の山旅
関東の名山ベスト100
関東日帰り山130
関東周辺週末160
関東周辺120
富士の見える山223
富士見ながら36山
富士山の見える山60選
2000メートル以上の642山
静かなる尾根歩き
山梨のハイクコース
日本2000m峰
奥秩父
最終更新:ヤマレコ/YamaReco
森・草原・岩場が揃った奥秩父の前衛

乾徳山は奥秩父山塊の南に聳えており、山梨県山梨市に属します。標高は2031mで、日本二百名山に数えられます。
日帰りで登れる山ながら、森林、草原、岩稜と変化に富んだ道で人気を博しています。特に多くの登山者を呼び込むのは奇岩登りです。岩場デビューや日本アルプスへ向けてのトレーニングにと選ばれています。
次々と現れる巨岩

魅力のひとつである岩塊は、山頂部に連なります。
「髪剃岩」や「カミナリ岩」など名のある岩もあり、所々に鎖や梯子が掛けられています。通過の際は三点支持を意識しながら慎重に登ります。

「鳳岩」は最後に立ちはだかる岩壁です。難易度が最も高く、ある程度の腕力も必要です。超えるのが厳しいと判断した場合は、巻き道から迂回できます。
富士山や南アルプスを望む

鳳岩を登り切った山頂は狭く、足元は不安定です。大岩が積み重なる中に、石造りの小さな祠が据えられています。

周囲に遮る物はなく、甲武信ヶ岳や金峰山、雲取山など秩父の山々を十分に見晴らします。
また富士山や南アルプスも望め、冬から春にかけての冠雪は風情を感じさせます。
初夏はツツジが美しい

乾徳山の麓から中腹は木立に覆われています。
初夏はトウゴクミツバツツジやレンゲツツジが花期を迎え、ぱっと鮮やかな色はハイカーの目を引きます。

「国師ヶ原」には、シラカバに囲まれ「乾徳山高原ヒュッテ」が建っています。バイオトイレが併設された避難小屋で、悪天時でも安全に休憩することができます。

森の中ではシカによく出会います。人慣れしているようで、距離が近くても物怖じする様子はありません。
牧場跡地の原っぱを行く

乾徳山高原ヒュッテの北方は、カヤの草原が広がります。開放感があり富士山や目指す山頂部がよく見えます。
かつては牛が放牧されており、牛乳も売られていたそうです。

中央に佇む「月見岩」は存在感があり、まるで道しるべのようです。
山号「乾徳山」の恵林寺

乾徳山は、夢窓疎石(むそうそせき:1275-1351年)が座禅修行を積んだ地と伝えられます。彼は七人もの天皇から国師号を賜った臨済宗の名僧です。また禅庭や枯山水の優れた庭園設計者でもありました。
山中には国師が座禅を組んだとされる「座禅岩」や、喉を潤したであろう「錦晶水」などがあります。

山麓には夢窓疎石が開いた恵林寺(えりんじ)があります。"乾徳山"の山名は、この寺の乾(いぬい、北西の方角)にあることが由来とされています。

恵林寺はのちに、武田信玄の菩提寺(※先祖代々の墓があり葬儀や法事を行う寺)に定められました。しかし天正10年(1582年)、敵をかくまったとして織田信長に焼き払われてしまいます。この時、百人余りの僧侶が焼死し、住職の快川紹喜(かいせんじょうき:1502-1582年)は「心頭滅却すれば火も自ら涼し」の辞世を遺しています。
恵林寺は織田信長が討たれた後、徳川家康により再建されました。
| 登山口 |
乾徳山登山口(オソバ沢ルート) 乾徳山登山口(道満尾根ルート) 大平牧場駐車場 |
|---|
基本情報
| 標高 | 2031m |
|---|---|
| 場所 | 北緯35度49分21秒, 東経138度42分53秒 |
| 山頂 |
|---|
山の解説 - [出典:Wikipedia]
乾徳山(けんとくさん)は、山梨県山梨市にある標高2,031mの山で、奥秩父の山域にある。日本二百名山のひとつ。山梨市北部の旧三富村域の中部からやや西方に位置する。南麓には笛吹川支流の徳和川が南東流し、徳和渓谷を形成しつつ笛吹川と合流する。西面には岩壁がそびえる岩山で、南アルプスや奥秩父の山々、富士山が遠望できる。東には南北に秩父往還が通じている。
江戸時代後期の『甲斐国志』に拠れば、鎌倉時代に臨済宗の僧・夢窓疎石が修行したとする伝承を持つ。夢窓は甲斐国においていくつかの寺院を創建しているが、乾徳山から南方の甲州市塩山小屋敷に所在する恵林寺は鎌倉末期の元徳2年(1330年)に夢窓の開いた寺院で、「乾徳山」が山号になっている。乾徳山には国師が座禅をしたといわれる座禅石や髪剃岩、天狗岩などの奇石があり、中腹には同じく国師との関わりを伝える銀晶水、錦晶水などの水飲場があり、山岳信仰にも関係していると考えられている。
付近の山
この場所に関連する本
この場所を通る登山ルート
おすすめルート
-
中級 日帰り 奥秩父


 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月適度な難易度の岩場で楽しめる乾徳山。 近年知名度が増してきた山頂への最短ルート、大平高原からのアプローチとなります。上部は鎖場が連続する険しい岩場が続き、北アルプスなどの岩稜歩きに向けたトレーニングにも最適な山です。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月適度な難易度の岩場で楽しめる乾徳山。 近年知名度が増してきた山頂への最短ルート、大平高原からのアプローチとなります。上部は鎖場が連続する険しい岩場が続き、北アルプスなどの岩稜歩きに向けたトレーニングにも最適な山です。


 乾徳山の山行記録へ
乾徳山の山行記録へ

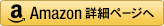















 Loading...
Loading...

