会津駒ヶ岳

- GPS
- 09:55
- 距離
- 9.6km
- 登り
- 1,206m
- 下り
- 1,192m
コースタイム
8:50駒ヶ岳登山口-9:45木の階段(取付)-14:30駒の小屋
(2日目)
7:30駒の小屋-8:22会津駒ヶ岳頂上-8:40駒の小屋-11:45駒ヶ岳登山口
| 天候 | 1日目曇り 2日目曇りのち晴れ |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2010年03月の天気図 |
| アクセス | |
| コース状況/ 危険箇所等 |
■道の状況(危険箇所など) ・アプローチ 国道352号は積雪もなく凍結している箇所もない。 ただし気温は0度程度になるので天候によっては凍結の危険あり。 スタッドレス・タイヤチェーン等装備は必須です(ノーマルだったので冷や冷やした) ・登山道 滝沢山口から登る道は斜度がきつく積雪も中途半端なため歩きにくい。 手前の谷筋にトレースがついており、そこから登るのが歩きやすくショートカットになる。 樹林を抜けた駒の小屋手前のポイントでは、天候次第で方角が分かりにくいので注意が必要。 ■登山ポストの有無 なし ■その他周辺情報 ・燧の湯: 午前9時から午後9時(11/16~4/28)、火曜日のみ正午から、12/30から1/3は午前6時から ・駒の湯: 午後1時から午後9時(12/30~1/3は午前6時から) ・アルザ尾瀬の郷: 正午から午後7時(土・日・祝日、12/24-1/7、3/20-4/5が営業日) 飲食店: そば処開山ほか(他のそば屋はシーズンによって営業していないことあり?) |
写真
感想
(1日目)
1泊2日で雪山初心者2名が登れる小屋泊まりの山ということで会津駒を選択。
埼玉から東北道で北上し、宇都宮あたりから下道で国道352号へ。
山以前にタイヤがノーマルなことを後悔しつつともかく桧枝岐村を目指して車を飛ばす。
桧枝岐の手前20kmほどのところで急に大粒の雨が降ってきたときには正直どうなることかと心配したが、朝方から降りが小ぶりになってきたので予定通り準備を進めた。
滝沢橋の駐車場は本当に1台停められる程度のスペースしかなくすでに取られていたため、100mほど下の滝沢グラウンド駐車場に車を止める。他の登山者は皆山スキーのようだった。
登山口からすでに雪が積もっているのですぐにスノーシューを装着しなだらかな林道を登っていくと、トレースは杉林の中に入り斜度がきつくなる。林道をトラバースしているかたちだろう。地図で木の階段の取付のところまでもトレースが付いているが、よりはっきりしたトレースは少し手前の大きなカーブのところを直登している。我々パーティは木の階段を上ってしまったが、この時期の積雪状態では、手前の直登が歩きやすい。
しばらくいくと手前の直登のトレースと合流する。そこから斜度が少し緩くなったが、雪の固まり具合が微妙で思ったほどは歩きやすくない。さらに2時間半ほど登ると斜面が緩やかになってきて樹林を抜ける。このあたりで山スキーの1パーティが雪洞をつくっていた。稜線に出ると風が強く景色も見えない。ホワイトアウトまではいかないものの木にくくられていて見つけやすかったマーカーもない状態に。降雪も本格的になってきてトレースもまったくない状態で一瞬方向を見失いそうになったが、駒の小屋に向かってポールが等間隔で立っていたのでそれを頼りに進むことができた。
駒の小屋の入口は完全に雪で埋もれていて、入口の引き戸も凍りついていて開けにくい状態だった。小屋の中に入ると外から粉雪が舞いこんでくる。ともかく無事に到着してほっとした。計画では初日に駒ヶ岳の頂上を踏む予定だったが、天候も悪く、視界も利かない状態なのでまだ14時過ぎだが荷を下ろすことにした。
もうそこからは、酒とつまみと焼き肉で早めの晩餐。
小屋の主人夫婦のほかに登山客が我々を入れて5人だったこともあり、気兼ねなく山談義に花を咲かせた。
9時ころには床についたが、大部屋に我々パーティ2人という何とも贅沢な状態。布団も毛布も暖かく。ほぼ目が覚めることなく6時ころまで爆睡してしまった。
(2日目)
天候は相変わらず。とはいえ、せっかくなので一応頂上を目指す。
すぐ間近にあるはずの頂上が見えない。トレースもない。
無雪期であれば往復30分程度の距離がやけに長く感じる。
正直引き返そうという考えもよぎったが、幸い頂上に向かって木が道しるべのように生えていたので、なんとかたどり着くことができた。
季節的には春山に向かっているとはいえ、東北の雪深い山で、かつ天候不順であれば一気に条件は厳しくなることを実感した。
ルートファインディングや読図の技術・経験を日ごろからトレーニングする必要性を痛感できたのは良い経験になった。
ともかく頂上を踏み、記念撮影もそこそこに、早速下山開始した。
小屋の主人には、小屋に戻らずに下山道に入るアドバイスをもらったが
正直ルートファインディングする自信がなかったので、いったん元来た道をたどって小屋に戻った。そこから昨日登った道を引き返す。
しばらく下ると、昨晩いっしょに小屋に止まっていた単独行のおじさんがつけたと思われるトレースがあった。そこから下はトレースがはっきりしていて、写真を撮りながらののんびり下山となった。
足が思いのほか披露していて、途中何度か転倒してしまったのは大きな反省。コースがコースであれば・・・
下山は夏コースタイムと同じ2時間ほどだった。
お勧めの燧の湯で温まり、そのあとそば処開山でそばを食して帰路についた。

 yu0329jts
yu0329jts
 dmarket
dmarket













 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手














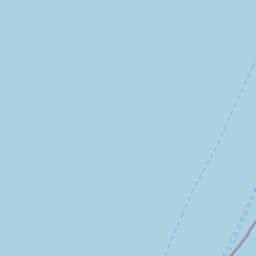











いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する