日本百名山
新・花の百名山
山梨百名山
日本百高山
信州百名山
一等三角点百名山
新日本百名山
甲信越百名山
中央線から見える山
ヤマレコ30選
日本の山岳標高1003山
山梨県の山(分県登山ガイド)
長野県の山(分県登山ガイド)
日本2500m峰
甲州百山
日本の山1000
東京周辺の山350
長野県の名峰百選
日本百霊峰
魅力別で選ぶ日本新百名山
日本名山図会
日本百霊山
ふるさと百名山
信州山カード
東京周辺の山350(2010年)
白籏史朗の百一名山
関東の山歩き100選
西丸震哉日本百山
歩いてみたい日本の名山
山登り365日
展望の山旅
関東の名山ベスト100
自然素晴しい50選
関東周辺週末160
関東周辺120
富士の見える山223
富士見ながら36山
2000メートル以上の642山
名景撮り方50名山
ほくとの山々
甲斐駒・北岳
甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ)
最終更新:ヤマレコ/YamaReco
威風堂々と立つ南アルプス北部の秀峰

甲斐駒ヶ岳は南アルプス北部に聳える山で、標高は2967mです。鋭く尖った山容で、花崗岩質の山肌は白っぽく、遠くからでもよく目立ちます。
隣に並ぶ仙丈ヶ岳はたおやかで女性的なため、これとよく比較され男らしい山とされています。「南アルプスの貴公子」と評されることもしばしばで、宇野浩二著の小説「山恋ひ」での表現を借り「山の団十郎」と比喩されることもあります。
日本百名山の一座ですが、選定者の深田久弥は、甲斐駒ヶ岳を最もピラミダルで最も綺麗な山として述べ、自身の中では十指に入るとして大変褒めそやしています。
駒ヶ岳の最高峰

山名に"駒ヶ岳"が付く山は国内にいくつもありますが、その中では一番の高さを誇ります。
"駒ヶ岳"である由来は諸説ありますが、いずれも、他の駒ヶ岳と同様に馬(※駒は馬を意味する)にちなむようです。その一つによると、白い神馬が住んでいたからとされており、別の言われでは、山梨県の巨摩(こま)地方が良馬の産地であったことに由来するそうです。

長野県の伊那地方では「白崩(しろくずれ)岳」「赤河原岳」の古名がありました。
この地で駒ヶ岳として定着したのは明治以降のようですが、「東駒」「東駒ヶ岳」の山名でも親しまれています。と言うのも木曽駒ヶ岳と区別するためで、伊那谷は2つの駒ヶ岳に挟まれた盆地です。甲斐駒ヶ岳は伊那谷の東に位置し、対する木曽駒ヶ岳は西側にあるため「西駒」「西駒ヶ岳」と呼ばれています。
登拝が盛んであった山

甲斐駒ヶ岳は山岳信仰の山で、開山は小尾権三郎(おびごんざぶろう、のちに弘幡(こうばん)行者:1796-1819年)により1816年に成されたと伝えられます。
その際の登路は横手駒ヶ岳神社から黒戸尾根を辿ったそうで、登山道沿いには信仰を伺わせる石仏や鉄剣などがあちこちに祀られています。特に九合目の烏帽子岩に突き立てられた2本の剣は、背後の絶景と相まって厳かな雰囲気を醸します。
かつては駒ヶ岳講の信者が大勢見受けられ、黒戸尾根には6軒もの山小屋があったそうです。
わらじが献じられる山頂

山頂は、大小様々な花崗岩が横たわる砂礫地です。山頂標識と石造りの祠があり、石碑がいくつも並んでいます。祠の格子戸に括られているのは、願いが込められ奉納されたわらじです。一段下がったところには駒ヶ岳神社本社が鎮座しています。

遮るものがない眺望で、仙丈ヶ岳や鋸岳、北岳など南アルプス北部の名峰はもちろん、連綿と続く南部の山々まで広く見渡せます。北アルプスや八ヶ岳、富士山も望めます。
北沢峠から目指す

7時間35分 8.9km
北沢峠(13分)→長衛小屋(38分)→仙水小屋(31分)→仙水峠(100分)→駒津峰(摩利支天ルート経由:83分)→甲斐駒ヶ岳(28分)→摩利支天(54分)→駒津峰(36分)→双児山(72分)→北沢峠
北沢峠は危険箇所が少なく、最も早く登頂できる登山口としてよく選ばれています。(登山口:北沢峠)
また、北沢峠からは仙丈ヶ岳に登ることもでき、こちらも最短時間で目指すことができます。そのため、仙丈ヶ岳の下山後に北沢峠に宿泊し、翌日は甲斐駒ヶ岳を目指す行程も支持を得ています。

北沢峠には「北沢峠こもれび山荘」と「南アルプス市長衛小屋」があります。

序盤は沢沿いに付けられた道を進みます。

「仙水小屋」を越えると、ごろごろとした岩場に変わります。傾斜もきつく、転ばないように十分注意します。

仙水峠を経て、森林限界を越えると駒津峰です。ここは展望の良いピークで、白く荒々しい山頂部や摩利支天、仙丈ヶ岳がよく見えます。

駒津峰から下った鞍部の巨岩は「六方石」と呼ばれています。

山頂へは「直登ルート」と「摩利支天ルート」に分かれます。
直登ルートは急坂の岩場です。両手両足を使った「三点支持」での登り方が求められるため、岩登りの経験が少ない場合は摩利支天ルートを選択した方が無難です。

摩利支天へは寄り道になりますが、短い時間で行き来することができます。いくつもの剣が刺さり、ところ狭しと石像が安置されています。

下りは双児山を経由します。ここで最後の見晴らしを満喫した後、樹林帯に入ります。
日本三大急登・黒戸尾根から行く

1日目:6時間59分 6.9km
尾白川渓谷駐車場(7分)→日向山登山口(162分)→笹ノ平分岐(130分)→刀利天狗(60分)→五合目(60分)→七丈小屋(35分)
2日目:8時間44分 9.9km
七丈小屋(69分)→八合目(100分)→甲斐駒ヶ岳(60分)→八合目(37分)→七丈小屋(36分)→五合目(50分)→刀根天狗(73分)→笹ノ平分岐(92分)→日向山登山口(7分)→尾白川渓谷駐車場

もうひとつ主な登路として「黒戸尾根」が挙げられます。(登山口:尾白川渓谷駐車場)
信仰の歴史を強く感じることができるほか、標高差2200mの長大な尾根で日本三大急登のひとつです。体力が求められますが、ステップアップを目指す登山者らに好まれています。

また岩場や鎖場が多く、岩登りの基本的な技術を習得してから臨む必要があります。

行程が長いため日帰りでの登山は厳しく、一般的には「七丈小屋」に宿泊します。
七丈小屋は黒戸尾根唯一の山小屋で、テント場も備えています。通年営業しており、積雪期や残雪期は熟達した登山者らで賑わっています。
| 登山口 |
北沢峠 尾白川渓谷駐車場 横手駒ヶ岳神社 |
|---|
基本情報
| 標高 | 2967m |
|---|---|
| 場所 | 北緯35度45分28秒, 東経138度14分11秒 |
| 山頂 | |
|---|---|
| 危険個所 | |
| 展望ポイント |
山の解説 - [出典:Wikipedia]
甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ)は、山梨県北杜市と長野県伊那市にまたがる標高の山。南アルプス国立公園内に位置する、南アルプス連峰(赤石山脈)の北の主峰である。峻険な山容をもち、半ば独立峰のような姿勢で屹立する日本アルプス屈指の名峰で、日本百名山、新日本百名山、新・花の百名山、山梨百名山、信州百名山、日本百景に選定されている。「駒ヶ岳」の名を冠する独立した山は全国に18山あるが、その中ではこの甲斐駒ヶ岳が最高峰であり、木曽駒ヶ岳がでこれに続く。ただし、富士山の火口を取り巻く火口縁(いわゆるお鉢めぐり)の南側には、駒ヶ岳もしくは浅間岳と呼ばれる小突起があり、その標高はである。
長野県側(特に甲斐駒ヶ岳と木曽駒ヶ岳に挟まれる伊那谷周辺)では、甲斐駒ヶ岳を東駒ヶ岳(ひがしこまがたけ)、木曽駒ヶ岳を西駒ヶ岳と呼ぶ。
南アルプスの山々は、高い標高と大きな山容を持ってはいるが、全般になだらかな稜線を連ねており、鋭角的な姿をした山は多くない。しかも、仙丈ヶ岳など南アルプスの他の多くの山は、前山に阻まれて人里からは間近に見えないことも多い。これに対して、甲斐駒ケ岳は、山梨県側の山麓から一気にほどの標高差をもって立ち上がっており、中央本線沿線からもその全貌が望まれる。また、「日本百名山」を記した深田久弥も甲斐駒ヶ岳の項の中で、「甲斐駒ケ岳は名峰である。もし日本の十名山を選べと言われたとしても、私はこの山を落とさないだろう」と述べており、その山容を絶賛している。
さらに、水成岩の山が多い南アルプスの中で、例外的に火成岩である花崗岩から成るため、山肌が夏でも白く望まれることも、駒ヶ岳の個性を際立たせている。このため、甲斐駒ヶ岳は古くから多くの人々に名山として称えられ、詩歌に歌われてきた。作家の宇野浩二はこの山を「山の団十郎」と評し、江戸時代の僧侶海量は、「甲峡に連綿として丘壑(きゅうがく)重なる 雲間に独り秀づ鉄驪(てつり)の峰」とその姿を漢詩に歌っている。
甲斐駒ヶ岳はまた、古くから信仰の対象ともなってきた。山梨県側の山麓の横手・竹宇両集落には駒ヶ岳神社が鎮座しており、そこから山頂にいたる黒戸尾根には現在も不動岩(威力不動尊を祀る)等の信仰にまつわる多くの石碑や石仏が残る。
付近の山
この場所に関連する本
この場所を通る登山ルート
おすすめルート
-
熟達 1泊2日 甲斐駒・北岳







 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月アンサウンドな岩場の処理と的確なルートファインディングを求められる南アルプス屈指の難路。どんなことにも対処できる、十分に経験を積んだ熟達者におすすめしたい岩稜ルートです。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月アンサウンドな岩場の処理と的確なルートファインディングを求められる南アルプス屈指の難路。どんなことにも対処できる、十分に経験を積んだ熟達者におすすめしたい岩稜ルートです。 -
☃ 雪山 1泊2日 甲斐駒・北岳


 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月長大な黒戸尾根をたどり山頂を目指します。 悪場の処理や長大な尾根に対応する体力など、冬山の総合力が問われるルートです。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月長大な黒戸尾根をたどり山頂を目指します。 悪場の処理や長大な尾根に対応する体力など、冬山の総合力が問われるルートです。



 甲斐駒ヶ岳の山行記録へ
甲斐駒ヶ岳の山行記録へ

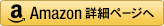











 Loading...
Loading...

