日本百名山
花の百名山
新・花の百名山
日本百高山
信州百名山
一等三角点百名山
富山の百山
新日本百名山
甲信越百名山
中央線から見える山
ヤマレコ30選
日本の山岳標高1003山
長野県の山(分県登山ガイド)
日本2500m峰
富山県の山(分県登山ガイド)
信州ふるさと120山
日本の山1000
長野県の名峰百選
魅力別で選ぶ日本新百名山
信州山歩き(中信・南信編)
温泉百名山
ふるさと百名山
信州山カード
特選日本名山50
山渓花の百名山地図帳
白籏史朗の百一名山
北陸新幹線百名山
西丸震哉日本百山
歩いてみたい日本の名山
山登り365日
名湯・秘湯の山旅
展望の山旅
自然素晴しい50選
関東周辺週末160
関東周辺120
富士の見える山223
日本いで湯百名山
2000メートル以上の642山
名景撮り方50名山
50歳爽快日本楽名山
越後百山
北陸の百山
白馬三山
白馬・鹿島槍・五竜
最終更新:ヤマレコ/YamaReco
大雪渓とお花畑が魅せる名峰

白馬岳は長野県と富山県の県境に位置する山です。後立山連峰の最高峰で標高は2932m、そして隣りに並ぶ杓子岳、白馬鑓ヶ岳を含む「白馬三山」の盟主です。
大雪渓と多彩な高山植物が特徴で、日本百名山および花の百名山に選定されています。
山体は南北に長く、典型的な非対称山稜です。東面は切れ落ちた急斜面で、西面はなだらかな勾配の地形です。
昔は山名が定かではなく、長野県では「西山」と呼ばれていました。富山県と新潟県では、山並みが馬の背に見えるとして「上駒ヶ岳」、または蓮の花に例えて「大蓮華岳」という古名がありました。

現在の「白馬岳(しろうまだけ)」の名は雪形にちなむとされます。春先に露出する馬形の山肌は「代掻き馬(しろかきうま)」と呼ばれ、この読みが転じたという説があります。
片や地元では”はくば”の読みが定着しています。白馬村(はくばむら)の村名をはじめ、宿泊施設やスキー場の名称等の多くは”はくば”と読みます。
役人が巡回していた奥山

山域は信濃(長野)、越中(富山)、越後(新潟)の三国にわたります。そのため、古くは国境警備や山林検分の登山が主で、庶民が立ち入ることはありませんでした。
北東にある小蓮華山では、この辺りでは珍しく信仰登山が行われていたようです。小蓮華山は大日岳の別称を持ち、山頂には鉄剣が祀られています。

登頂を目的とした最初の登山は、1883年(明治16年)です。以降は植物学者も入山するようになり、徐々に人々に開かれていきました。
1906年(明治39年)には松沢貞逸(まつざわていいつ:1889-1926年)が頂上直下に山小屋を開業しました。この小屋は、日本で最初の近代登山(※宗教目的ではなく山に登ることそのものを目的とした登山)のための宿泊施設で、現在の「白馬山荘」です。
松沢貞逸は日本最古の登山案内人組合を結成するなど、登山の大衆化やスキーの普及に尽力しました。長野県側の麓は、今やスキー場や自然園がいくつもある観光スポットです。白馬山荘の近くには彼のレリーフが設置されています。毎年5月に開催される「貞逸祭」は白馬連峰の山開きです。
勇ましい剱岳を望む

白馬岳山頂は日本の名だたる高峰が一望です。剱・立山連峰をはじめとする北アルプスの峰々や南アルプス、八ヶ岳の背後には富士山も見えます。
富山湾や能登半島も眺望できます。

山頂の方位盤は、新田次郎著「強力伝」のモデルとなった巨石です。強力伝は実話を元にした小説で、主人公が50貫(約187kg)もある花崗岩2つを、白馬岳山頂まで担ぎ上げる挑戦が描かれています。この物語は新田次郎のデビュー作で、直木賞を受賞しました。

ほど近い所に建つ「白馬山荘」は、日本最大級の収容人数を誇ります。併設するレストランでは生ビールやケーキを提供しており、山の上とは思えないほど優雅な時間を過ごせます。

白馬岳をやや南下すると「白馬岳頂上宿舎」があります。テント場を備えるほか、郵便局も開設されています。ここで投函された郵便物には白馬岳の図柄の風景印が押されます。
ダイナミックな雪渓歩きを楽しむ

1日目:6時間13分/6.2km
猿倉(88分)→白馬尻小屋(259分)→白馬岳頂上宿舎(26分)→白馬山荘
2日目:4時間35分/9.4km
白馬山荘(22分)→白馬岳(29分)→三国境(43分)→小蓮華岳(67分)→白馬大池(24分)→乗鞍岳(32分)→天狗原(58分)→)栂池自然園
東の長野県からのアクセスが主流で、とりわけ白馬大雪渓を通るルートが人気です。
白馬大雪渓は白馬岳から杓子岳にかけて、東の斜面に広がります。長さは2km、標高差は600mに及び、日本三大雪渓のひとつです。

猿倉から入り、白馬尻まで進めば白馬大雪渓の取り付きです。一面に展開する雪原と、雪渓を渡る涼しい風は、心に残る体験です。
通行には軽アイゼンが必要です。白馬駅の北アルプス総合案内所、猿倉荘、白馬山荘などでは軽アイゼンの販売、およびレンタルを行っています。
また落石に注意し、クレバスを避けて歩きます。雪上に赤い顔料で通行路が示されていれば、それに従います。この顔料はベンガラと言い、鉄酸化物から作られる赤い粉末です。

葱平(ねぶかっぴら)より上部はあちこちでお花畑が見らます。杓子岳の方を見遣れば天狗菱と呼ばれる岩峰が鋭く立ちます。

尾根に取り付き、白馬岳頂上宿舎まで至れば白馬連峰の主稜線です。白馬三山や剱・立山連峰、眼下には大雪渓が見渡せ、何とも開放的な気分です。

白馬大池は大きな火山堰止湖で、クロサンショウウオが生息します。畔に咲き乱れる花々と、きらめく湖面は神秘的な雰囲気です。
かつては雨乞の神がおわすとして崇められていましたが、足を踏み入れると飢饉になるとも信じられていました。

西の富山県からの登山口は欅平(けやきだいら)です。
林道をほどなく進むと祖母谷温泉(ばばだにおんせん)があり、ここから主稜線まで有人小屋はありません。コースタイムが長く健脚向けですが、ところどころに池塘が見られ、静かで味わいのある雰囲気です。振り返れば剱・立山連峰が眺められる点も魅力です。

後立山連峰の主稜線は人気の縦走路です。
白馬三山を踏破するルートのほか、白馬鑓ヶ岳より南下し、難所の不帰嶮(かえらずのけん)にチャレンジするルートなどがあります。
多様な花が咲き競う

白馬岳一帯は高山植物が豊富です。その種類は800種に及ぶとも言われ、国の特別天然記念物「白馬連山高山植物帯」の指定を受けます。
自然学者がよく訪れていたため、発見場所を指す「シロウマ」を冠する植物が数多くあります。
シロウマアサツキは、紅紫色の花がネギ坊主のように放射状に付きます。葱平に咲いており、葱平の地名の由来とされます。

また、ウルップソウやツクモグサが自生する数少ない地でもあります。
ハイマツ帯にはライチョウが生息しています。ひょっこりと現れては、見る人を癒します。
温泉巡りができる山

山域では温泉を楽しむことができ、これを目的とする登山者も少なくありません。
白馬鑓ヶ岳の中腹にある白馬鑓温泉は、大きな露天風呂が斜面から張り出ており、足湯もあります。標高2100mに位置し、御来光や星空を仰ぎながらの入湯は至極のひとときです。

北東にある蓮華温泉は、登山口のひとつです。効能の異なる4つの野天風呂を巡ることができます。
また、富山県の祖母谷温泉は河原に臨む立地です。せせらぎを耳にしながら心地良く入浴できます。
山行の締めくくりを温泉地にすれば、最後まで気分を高めて歩けそうです。
| 登山口 |
猿倉荘(猿倉登山口) 栂池パノラマウェイ 自然園駅 蓮華温泉 欅平駅 |
|---|
基本情報
| 標高 | 2932.24m |
|---|---|
| 場所 | 北緯36度45分30秒, 東経137度45分30秒 |
・後立山連峰の主峰、山頂直下の南には、日本最大規模の白馬山荘(収容1,200人)がある。高山植物が豊富で、本州でありながら八ヶ岳の硫黄岳と同様にウルップソウが見られる。澄んだ快晴時には、日本海や能登半島を見渡すことができる。日本最大の白馬大雪渓は、夏の遅くまで雪が残り、シーズン最盛期には、蟻の行列状態となる。
| 山頂 | |
|---|---|
| 危険個所 | ★平成25年ゴールデンウィーク中、遭難1件(雪崩・3名死亡)★平成24年度ゴールデンウィーク中、遭難2件(凍死傷・6名死亡、転倒・1名軽傷)ー長野県山岳遭難防止対策協会 提供ー |
山の解説 - [出典:Wikipedia]
白馬岳(しろうまだけ、はくばだけ)は、飛騨山脈(北アルプス)北部の後立山連峰にある標高2,932 mの山。長野県と富山県とにまたがり、中部山岳国立公園内にある。白馬岳は杓子岳、白馬鑓ヶ岳とともに白馬三山と呼ばれている。南に続く後立山連峰の山々とともに、南北に伸びる稜線の両側の傾斜が著しく異なる非対称山稜が発達している特徴的な山容を持つ。山頂を含む南北700 mの地帯は県境が設定されていない。山頂には一等三角点があり。
東側の谷筋には冬季の膨大な積雪と周囲の山塊からの雪崩が集積した日本最大の雪渓である白馬大雪渓がある。雪渓の上部は夏期には日本有数の高山植物の花畑が広がる。白馬大雪渓は日本三大雪渓のひとつとして有名。日本百名山、新日本百名山、花の百名山および新・花の百名山に選定されている。
鑓ヶ岳中腹の標高2,100 m地点には、日本有数の高所にある温泉である白馬鑓温泉があり、白馬大池の北麓には蓮華温泉がある。
雪渓、花畑、岩場、山の温泉と様々に楽しめる要素があり、交通の便も比較的良いことから、夏季にはたくさんの登山者が訪れて混雑する。夏期の登山者の大半は大雪渓を経由して登るため、夏休みの時期には大雪渓上は長蛇の列となることが多い。
なお、白馬岳山頂は日本郵便から交通困難地に指定されており、通年にわたり地外から当地宛の郵便物を送ることができない。
付近の山
この場所に関連する本
この場所を通る登山ルート
白馬・鹿島槍・五竜 [4日]
利用交通機関
車・バイク、 電車・バス、 タクシー
技術レベル体力レベル
槍・穂高・乗鞍 [7日]
利用交通機関
車・バイク、 電車・バス、 タクシー
技術レベル体力レベル
おすすめルート
-
中級 1泊2日 白馬・鹿島槍・五竜

 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月日本三大雪渓のひとつ「白馬大雪渓」をたどり、国内有数の高山植物帯と素晴らしい展望を楽しむ稜線闊歩。 技術的にも難しい箇所は少なく、北アルプスの縦走入門として人気の高いルートの一つです。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月日本三大雪渓のひとつ「白馬大雪渓」をたどり、国内有数の高山植物帯と素晴らしい展望を楽しむ稜線闊歩。 技術的にも難しい箇所は少なく、北アルプスの縦走入門として人気の高いルートの一つです。 -
☃ 雪山 1泊2日 白馬・鹿島槍・五竜


 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月積雪が安定する5月初旬から下旬にかけて、雪山初-中級者には最高のフィールドとなる白馬岳。 山頂近くに建つ白馬山荘に1泊して、翌日は旭岳に登り白馬大雪渓を下ります。 5月下旬に行われる開山祭(貞逸祭)に参加するのも楽しみのひとつかもしれません。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月積雪が安定する5月初旬から下旬にかけて、雪山初-中級者には最高のフィールドとなる白馬岳。 山頂近くに建つ白馬山荘に1泊して、翌日は旭岳に登り白馬大雪渓を下ります。 5月下旬に行われる開山祭(貞逸祭)に参加するのも楽しみのひとつかもしれません。 -
中級 2泊3日 白馬・鹿島槍・五竜




 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国内屈指の規模で高山植物が咲き乱れる白馬岳。 白馬大雪渓をたどり後立山の稜線散歩から秘湯「鑓温泉」へと変化に富んだルートです。1泊で済ませる方が多いですが、できれば2泊すると充実した山歩きを楽しむことができます。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月国内屈指の規模で高山植物が咲き乱れる白馬岳。 白馬大雪渓をたどり後立山の稜線散歩から秘湯「鑓温泉」へと変化に富んだルートです。1泊で済ませる方が多いですが、できれば2泊すると充実した山歩きを楽しむことができます。 -
中級 3泊4日 白馬・鹿島槍・五竜




 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月北アルプスの稜線から日本海を目指す長大な縦走コース。栂海新道は体力的にきついのですが、それだけに大きな達成感を得ることができるでしょう。できれば盛夏ではなく9月に入ってからのほうがおすすめです。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月北アルプスの稜線から日本海を目指す長大な縦走コース。栂海新道は体力的にきついのですが、それだけに大きな達成感を得ることができるでしょう。できれば盛夏ではなく9月に入ってからのほうがおすすめです。 -
上級 3泊4日 白馬・鹿島槍・五竜



 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月後立山連峰の核心部を北から南へと縦走。 高山植物を愛でながら、2つのキレット越えと素晴らしい展望を堪能する夏山の定番とも言えるルートです。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月後立山連峰の核心部を北から南へと縦走。 高山植物を愛でながら、2つのキレット越えと素晴らしい展望を堪能する夏山の定番とも言えるルートです。 -
☃ 雪山 1泊2日 白馬・鹿島槍・五竜



 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月日本を代表する古典的な積雪期バリエーションルート。 長大な雪稜と山頂へ詰め上がる見事な雪壁、そしてフィナーレの雪庇越えでクライマックスを迎える。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月日本を代表する古典的な積雪期バリエーションルート。 長大な雪稜と山頂へ詰め上がる見事な雪壁、そしてフィナーレの雪庇越えでクライマックスを迎える。



 白馬岳の山行記録へ
白馬岳の山行記録へ

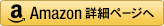














 Loading...
Loading...

