大嶽・大滝山ルート調査

- GPS
- --:--
- 距離
- 2.7km
- 登り
- 220m
- 下り
- 205m
コースタイム
| 過去天気図(気象庁) | 2015年11月の天気図 |
|---|---|
| アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
写真
感想
大嶽・大滝山調査
平郡島西地区の長深山調査(11月11日・12日)に続いて、東地区の大嶽・大滝山を調査する。
大嶽に登るルートは東側の羽仁地区からのルートが知られていたが,地理院地図には南側の市道の峠付近からの破線が示されており、それは大嶽や大滝山に登ると言うより、大滝山(287m)を起点とする主脈を辿り、深山・長深山の傍を通って西地区に至っている。その破線を辿って大嶽・大滝山から深山・長深山に至る縦走路を復活させたいと言う動機から、2年ほど前にこの南側からのルートを調べたことがある。その時は大嶽に辿り着くこともできずに終ってそのままになっていたが、その時の協力者である同島在住のMatukawa氏の手によって大嶽までのルートが明らかにされており、今回はそのルートを確認しながら大嶽に登り、その後大滝山から深山に向かう破線を辿ってみようと言う試みである。
そのMatukawa氏に地図を印刷してもらい、10時半に自宅を出発。羽仁地区(東)から西地区に至る市道の、五十谷を廻る道との合流点になる峠に車を置いて10:54唐歩き始める。
登山口の表示はないが、テープの目印があり、その目印を追いながらが蔓と邪魔な木や倒木を処理しながら登って行く。道はしっかりしてるが、登る人がいないので小さな灌木や蔓植物が繁茂しており、とりわけ蔓植物がまるで意思を持つかのように絡んで行く手を遮り、或は足を引っかけて進行を阻もうとする。それを全部切り払いながら登るので遅々として進まず、わずか140mの登りに1時間余りを費やす。
12時頃、深い林の中で熟したムベの実が落ちてるのを拾う。平郡島にはアケビと共にムベも多く,島ではこれをリンゴアケビと称しているが、それがどんな味のものかを語る人に会わず、アケビもそうであるが、島人にとってはあまり関心のある果実とは思えなかった。この時期には道に落ちているのものをよく見かけるが、食べられるほどに熟した実を手にすることがなく、食べたことはなかった。アケビに比べると種が大きく、種の周りのヌルヌルも豊富で食べて見てその甘さに驚く。種の多さに閉口するアケビに比べると味も食感も遥かに勝る上に食べやすく、認識を一変させられた。その辺りにも石垣を積んだ棚畑が見られ、かつてはここも耕作地だったことが窺えた。
勾配が緩くなって前方に木々の間にちらりと空が見えるようになり、12:27頃それまでまっすぐ尾根に沿って北北西方向に向かっていた目印が見当たらなくなり、そのまま直進すると、その一画だけが草地になった湿っぽい場所に出て、2年前にもその場所でウロウロして彷徨い始めたことを思い出し、目印のある所まで戻って入念に探すとそれまでの進行方向から右に向かって下がりながらトラバースしている目印を見つける(12:31)。それは主脈上に位置する大滝山と、それから東に外れている大嶽との鞍部に向かう下りで、前回は地図を持たずに歩いたために、この鞍部に向けて一旦下ると言う考えに至らなかったことが分かった。そこから先は倒木や蔓植物の処理に手間取り、30分かかって13:02にMatukawa氏によってつくられたバリケードに着く。それは羽仁地区から登って来た人が迷い込まないための通行止めの印で、そこを潜ると右手に誘導されて3分足らずで13:05に大嶽の大岩に着く。Matukawa氏に電話で報告し、みかんとスポーツ飲料で休憩。
13:29に大嶽をあとにして分岐点に戻り、そこから大滝山を目指して尾根と思われる方向に進む。先刻の草原を横切って薮の一画を切り払い、高みを目指して北西方向に進むとすぐに小高い丘のような場所に出る。
小高いと言ってもピークと言えるほど顕著でなく周りより幾分高いと言う程度。そこから石垣にそって歩いていると下がり気味となって船の音が大きくなってきたので引き返し、地図を開いて方位(太陽と時計)を確認して軌道修正し北西に向かう。
一帯は見通しの利かない樹林で、明瞭な尾根と言うほどの傾斜はなく、ただ前方に空が見えない方向に進むしかないと言うもので、帰りが不安なので、赤いテープが目立つよう白い肌の木を選んで目印をつけながら進む。薄暗い樹林の中では白い木自体が目印にもなった。
この尾根は沖浦と言う地区にあるみかん畑からよく見える尾根で、そこから見ると深山に向かってゆっくり高度を上げており、それは平郡航路のフェリーからもそのように見えるので、徐々に高度を上げて行くだろうと予想していたが、一向にその気配はなく登っているのか下っているのか分からないような単調さから、やがて明らかに下りに差しかかった地点で改めて地図を開くと、島を横断する破線が入った鞍部があり、そこに向かってのやや大きな下りに入ったものと判断し、時間を考えてそこまでとする。赤いテープを三重に巻き、更にテープの裏側に日付と名前を書いて貼りつけて置く。
そこから目印を頼りに引き返したが、それでもかなり右往左往して「そのおかげで行きでは見なかった標柱を見つける(14:28)。それが大滝山のピークを示すものかどうかは分からないが、そこから少し進んだ先で先刻の丘のような場所に着いた(14:34)のでその標柱が大滝山を示すものである可能性はある。その時は気づかなかったが、その丘にはレンガ造りの壁の跡のようなものがあった。
そこから難なく草原を横切って大嶽への分岐点に戻り(14:45)下山路に入ったが、実は登りの際にもう1ヶ所迷った所があった。それは分岐点から6~7分下った所で(14:52)、それまで高みを目指して直進する道が、そこで右折していたのに気づかず通過して目印を見失った場所で、そこに入念に目印(直進方向に✕印)を施して下る。15:16下山。
大嶽に南側から登るこのルートの再発掘はひとえにMatukawa氏の尽力によるもので、感謝にたえない。今後このルートが大嶽を縦走したり、深山~長深山へと続く縦走ルートの1つの起点なることを望むものである。
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 nobou
nobou







 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手























































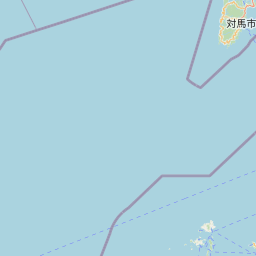









いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する