奥利根横断 ネコブ山~上銅倉沢~本谷山~十分沢~平ヶ岳~戸倉

 1192fujiwara
その他2人
1192fujiwara
その他2人 - GPS
- 56:58
- 距離
- 57.2km
- 登り
- 4,358m
- 下り
- 3,730m
コースタイム
- 山行
- 11:28
- 休憩
- 0:02
- 合計
- 11:30
- 山行
- 9:43
- 休憩
- 2:03
- 合計
- 11:46
| 天候 | 20日:晴れ 21日:曇りのち晴れ、夕方から風強い 22日:晴れ |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2025年03月の天気図 |
| アクセス |
写真
装備
| 備考 | メモ ・タンパク源は1日あたりベーコン50g ・行動食は輸入のクッキーとチョコレート菓子 ・コンソメスープは塩分も取れてよい。行動中にテルモスのお湯に混ぜて飲むも良し ・林道歩きが長い時はスマホに漫画を入れておくとよい ・共同装備は重量計算して平等に一人1.9kg。自分のザックは水なしで12kg |
|---|
感想
1/18に上銅倉沢まで偵察した奥利根横断。2回の延期を経て、ようやくチャンスが巡ってきた。
驚くべきことに、単独の横断者3人と遭遇した。全員微妙に違ったルート取りだったが、我々の視点から見ると行程の半分ほどが先行トレースを追うことになってしまい、嫌だった。。。とはいえ、無理にトレースを外して歩くほど原理主義的ではない。今年奥利根横断を狙っている人なら必然的にこの日になるだろうから、仕方ない。
そもそも、あまりトレースされていないとはいえ、記録を真似して手軽に冒険気分を味わおうとするのが浅はかな話。知恵を絞って、ユニークなラインを次は引こうと思った。まずは1回目の横断に成功したことを素直に喜び、2回目の布石としたい。やはり1回行ったことがあるのと無いのとではイメージの湧き方が違う。
21日
三国川ダムの駐車場に行くと、なんと既に2台の車が停まっており、出発済の模様。車をジロジロ観察すると、1台は中澤氏のものであると判明。いやー、先を越されてしまった。ネコブ往復とかだったらいいなあと思いながら出発。
ネコブ山まで(不本意ながらも)トレースを使い、楽に上銅倉沢のドロップポイントに到達。1週間ほど前のアイスバーンの上に2回降雪があり、その結合を気にしていたが、風の影響は小さく、結合は良かった。先行者2名はネコブ山山頂近くからドロップしたようだったが、我々は偵察時と同じように肩からエントリー。今回は視界が良いので1ピッチで1つ目の滝まで一気に滑り、あとはパーティーラン。気温が高く晴れているため、やや重めだったが、そこそこのパウダーを楽しめた。
もともとの予定ではネコブ山までのつもりだったが、ここまで来たら本谷山までなるべく進んでおくのが定石。暑さに喘ぎながらまたもやトレースを利用して登り返し、小穂口ノ頭手前で幕営していた先行者2人に挨拶し、自分たちは先へ進もうとしたのだが、アイゼンの調子が悪かったため、小穂口ノ頭でテントを張った。
22日
ほぼ日の出と同時に行動開始。テン場でうっかり例の2人に抜かされてしまったが、この際気にしない。本谷山では雪庇の位置がよく分からなかったので、山頂より少し北の斜度がゆるい場所でロープを出す。たまたまドンピシャで雪庇がなく、三浦氏の言う「ランペライン」らしき場所に出たが、どちらかというとバンドのようになっており、少し藪も出ていた。山頂すぐ南の雪庇が小さいことがここから見て取れたので、そちらへ移動。ピットを掘ると、表面30センチくらいのスラブが、結合はそこそこ良く、ほぼ大丈夫だと思うが、なんだか嫌な感じ。。。少し悩んだが、斜度の緩い十分沢を下降することに決めた。日帰り山行で同じコンディションだったら滑走していたような気もするが、なんとなく嫌な予感がしたのは、奥利根の迫力に圧倒されたのかもしれない。まあ、こんなもんでしょう。
少し尾根を滑り、十分沢にエントリー。安全な斜度なのでちょっとスピードを出してみる。最初の3ターンは良かった。4ターン目でなんだか雪質が怪しくなり足を取られたもののリカバリー。5ターン目で現れたモナカを処理できずゴロンと転倒。相変わらず懲りない。その後は緩い沢をだらだら降りる。
利根川本流に出る直前に一瞬いやらしいトラバースがあったが、その後は右岸を楽にトラバースして「ヒトマタギ」で横断。歩き尾根取り付きは細くて急なのでアイゼンで登る。踏み固められないザラメ雪になっており難儀した。途中のギャップは懸垂下降。そこ以外はスキーで快適に登高。
剱ガ倉山の雪庇がかなり大きく、どこから尾根に降りられるのか分からないのでロープを出そうかと思った、、、が、平ガ岳から滝が倉山に向かうワカントレースがあったので、簡単に突破できてしまった。この先の細尾根はワカントレースに助けられながらシートラーゲンで通過。途中からスキーを履いてダラダラ登り、平ガ岳へ。平ガ岳では気象計測用アンテナがソーラーパネルぎりぎりまで埋まっており驚いた。
今晩から風が強い予報なので、できれば樹林帯まで降りたかったが、時間も時間だし、平ガ岳の少し先で幕営。ここまで来れば勝利は貰ったも同然なので、ワインを空ける。2日目でここまで進むとは。
23日
景鶴山経由で下る選択肢も僅かに念頭にあったが、2日連続の高温により南面の雪質には期待できない。最短経路で鳩待峠から下山することにする。山ノ鼻では偶然おなじ会のパーティに遭遇。横断成功を祝ってもらった。鳩待峠からはスキーで一気に滑れると期待したのだが、思ったより早く除雪が始まっている。靴擦れに耐えながら鳩待入口バス停まで。ピッタリの時間でバスに乗れた。公共交通機関に乗ると一気に安心する。終わってみれば、長かったような短かったような山行だった。
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する













 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手























































































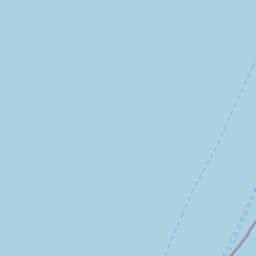



















チャンスをつかみました!
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する