大笠山へ びしょ濡れで晴れの山頂へ

- GPS
- 09:06
- 距離
- 12.3km
- 登り
- 1,601m
- 下り
- 1,598m
コースタイム
- 山行
- 7:40
- 休憩
- 1:24
- 合計
- 9:04
2:50 安曇野穂高発 安房トンネル経由 高山IC~五箇山IC
6:20 桂湖オートキャンプ場手前駐車場着
<復路>
15:50 駐車場発
16:20 五箇山 赤尾泊
| 天候 | 朝方の雨が上がり徐々に晴れる |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2019年09月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
| コース状況/ 危険箇所等 |
最初の梯子、鎖そしてしばらく両側が切れた登山道(笹などで見えないが切れ落ちている) 連続した急登 笹の濃いところがある(道は明瞭) |
| その他周辺情報 | 五箇山温泉 道の駅なども赤尾地区にある 合掌造りの集落 |
写真
感想
2019年(令和元年)9月19日(木)
大笠山へ びしょ濡れで晴れの山頂
本来は読売新道を計画していたが3日間の好天が見込めず、
北陸石川・富山県境の大笠山を目指した。
2日間は天気が良さそうなので大門山・医王山も考えた。
岐阜に入ると小雨が降り始める。
天気予報では晴れるとのことですぐにもやむだろうと思いきや、
登山口となる五箇山の桂湖でも天からの冷たい物を感じる。
出発をどうしようかためらっていると
すでに駐車場に止まっていた車から大笠へと向かった方がいた。
天気は良くなってくるのは確実だったので後を追うように出発した。
歩き始めると雨は上がり天気の心配はなくなった。
ただ登山口の草は濡れ雨上がりの登山道へと入り込んだ。
まず揺れる大畠谷の吊り橋を渡る。
大笠山というと垂直の梯子が連続する。
雨で濡れた滑る5つの鉄の梯子を慎重に登った。
それが終わると鎖が続き一気に高度を上げた。
一番怖いと思ったのはそれからだった。
登山道の両端が草、笹などで覆われているので気にしなければ良いのだが
細い登山道の両側はすっぱと切れ落ちている。
草などがないと恐怖で通れないのではないかと思うほどだ。
それからは急登の連続になる。
さらに笹が濡れ、その露をしっかりとパンツがすってしまう。
一気に濡れてしまったのでレインウエアに交換した。
急登にあえぎ、足が思うように進まない。
天気は好転し始めときどき薄日が差し、小鳥のさえずりも聞こえる。
しかし周りは雲に覆われ視界はなく黙々と歩くしかないのがきつかった。
前笈ヶ岳では二人の単独の方と一緒になり、
三百名山を目指していることが分かり話が弾んだ。
似たような考え行動をして山を楽しんでいることが分かる。
中間点辺りを過ぎてからも苦行は続く。
ほぼ下半身はずぶ濡れ状態でより足取りは重くスローペースになった。
ただ救われたのは旧避難小屋で休み、登り始めると
今まで覆うような笹が刈られ、登ることに集中できたことだ。
何よりも雲の上に出ると青空が広がり、
北アルプス、立山、剱岳の三角錐が雲に浮くように見えたことだ。
今日の天気は晴れの予報だったが正に晴れだした。
あと0.2km、そして奈良岳への分岐地点に着く。
近くには避難小屋も建ち、ほぼ平坦な道で山頂へと着くことができた。
山頂はもちろん太陽が照り日差しが強いくらいだった。
露でびしょ濡れのパンツをしっかり乾かすことができた。
周りに雲はかかるが笈ヶ岳その背後には白山も眺望できた。
猿ヶ馬場山のなだらかな山容、大門山のこんもりとその姿を確認することができた。
眼下には金沢市、小松市、福井市の街並みが広がっていた。
下山中には見られなかった周りの山並が見られ、
とくに笈ヶ岳の迫力ある山容がその姿を変えて迫ってきた。
苦しい登りのご褒美が晴れの天気だった。
ふるちゃん

 furuhiro
furuhiro







 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手







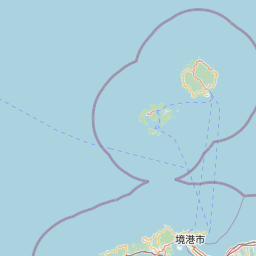













いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する