猫又谷から毛勝三山

- GPS
- 27:00
- 距離
- 7.3km
- 登り
- 1,696m
- 下り
- 278m
コースタイム
5/22 猫又山5:30-9:20蛇石
| 天候 | 5/21 晴れ 5/22 薄曇り |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2010年05月の天気図 |
| アクセス | |
| コース状況/ 危険箇所等 |
猫又谷の雪の状態はよく、小規模な雪崩や落石もありますがあまり問題はないと思います。あと2週間くらいこの状態なのではと思います。 縦走路はセッピ側に寄りすぎず、かつクレバス・シュルンドを早め早めに避けるルートファインドがポイント。雪面があまりに急すぎるので、ヤブを使わなければならないところが3ヶ所ほどあります。特に猫又~釜谷間がやや悪いです。全般に見た目ほど危なくないと思います。 |
写真
感想
前日夜車で出発し、どこか高速のSAで仮眠と思っていたが、魚津まで順調に来たのでその足で登山口まで入ってしまった。小田原からちょうど6時間。毛勝山に登るには毛勝谷からの方が有名だが、三山全部登るなら猫又谷からのほうが楽で安全だそうなので、今回はこちらからにした。車は残雪のため林道終点までは入れず、蛇石から数100m先の市道分岐の手前に置いた。標高は600mでここから猫又山の山頂までは1800m近くの標高差がある。テン泊装備では体力的にはかなりきついコースだ。
翌5/21、朝5時15分に出発。40分ほど林道を歩いてから林道から砂防ダムへ降りたが、これはちょっと失敗。その先川沿いはヤブが酷く、かなり時間がかかってしまった。行ける所まで林道を歩くのが正解で、最終砂防ダムの手前まで楽に入れる。
標高1080mの最終ダムから2180mの稜線まで全て雪渓の上を歩く。上部は40度くらいあるので、12本爪/ピッケル/ヘルメットの装備は Mustである。自分は念のため20m補助ロープも持った。雪渓下部は所々崩壊して激流が顔をのぞかせている。あまり川のほうに寄りすぎずに歩く。標高 1400mを越えるとだいたいどこでも好きなところを歩ける。デブリの跡を避けて、適当に歩きやすいところを歩く。
猫又谷は非常に大きいU字型の谷で、多分谷の広さでは白馬大雪渓などより上だ。山スキーヤーには極めて有名なコースなのだが、自分は最近まで知らなかった。谷は一直線に延びているので、スタート地点から稜線まで遮るものも無く広く見渡せるのは魅力である。谷が大きいので雪崩や落石もだいたい途中で止まる。今回も何回か落石があったが、歩いていたところはほぼ安全圏内だった。
上部手前まで斜度は緩いので何もなく順調に進んだ。1700mを越えると徐々に急になり苦しくなる。斜度も30度を常に越えているので滑ると危ない。キックステップを念入りに行う。2000mを越えるともう地獄である。体調もあまりよくない。さすがに前夜車中泊はきつかったと後悔し始める。ペースは死ぬほど遅くなってしまった。
それでもなんとか標高2180mの稜線に到着。いきなり東の展望が開けて剱岳がどど~んと現れた。これを見て度肝を抜かれ、しばらく動けなかった。なんてデカイ。こんなに近かったのか… ここでテントを張ってもいいかなと思ったが、もう少し頑張って登り、結局標高2320mの広広とした台地の端に幕営。登り始めてから6時間半もかかってしまった。お湯を沸かして食事大休憩。テレマーカーと単独登山者が一人ずつ横を通過していったので挨拶する。金曜日なのにさすがはこの時期人気の山。テレマークスキーほんとにかっこいい… 音がシャープやね。剱を横目に見ながら最高に気持ちいい滑りだろうな。
それにしても完全にばててしまい、体調も良くなく頭痛もする。これから毛勝までいくのをやめようかと思い始めるが、天気も良すぎるくらいなのでもったいない。3時半になったら引き返すと時間を決めて出発することに。この時点で1時。
幕営地から5分で猫又山(2373m)頂上。ここで初めて毛勝山とご対面。立派な山容だ。お隣の釜谷山も素晴らしい。しかし近くもなく、かといって遠くもなく微妙な距離だな…と思いながら釜谷山へ下ってゆく。ルートはほぼセッピを使えるが、釜谷山を越え、毛勝南峰の鞍部までは数箇所雪が切れており、ヤブを使わないとならない。ところどころ背丈以上のクレバスやシュルンドもあり注意を要する。何よりこの界隈のセッピは恐怖感をあおるのに十分な凄まじい外観をしている。最初これは行けないだろと自分も正直思ったが、意外と大丈夫なものである。
出発から1時間で釜谷山(2415m)。ここまで来て体調がずいぶん持ち直した。やはり空身で荷が軽いせいだろう。十分いける気がしてきた。毛勝南峰との鞍部に雪渓から水が滴っている場所があり、水筒を満タンにした。暑くて水の消費が激しい。毛勝南峰に取り付いてからは斜度も緩み、安全になる。南峰から北峰はすぐであっという間に毛勝山頂(2414m)に到達した。結局幕営地を出てからぴったり2時間だった。
山頂からは毛勝谷を見下ろせた。猫又谷よりは小さく、屈曲している谷だ。斜度も大きく雪崩と落石の危険もこちらのほうが高い。でも登る人は多いのか、トレースは綺麗に出来ていた。また、最近夏道ができたという北西尾根も見渡せたがこちらもまだまだ残雪が多い。登れるようになるのは6月中旬くらいからだろうか。
帰路も十分に注意を払い、猫又山まで戻った。特に釜谷山と猫又山の間は斜度が急でスリップ注意である。セッピに寄り過ぎなければ大事には至らないと思うが、クレバスには結構気を使う。テントには4時55分に到着。途中あきらめかけたこともあったが、終わってみればだいたい目論見どおりだった。
午後には雲に覆われていた剱岳は、夕方に完璧に晴れて夕焼けに染まった。なんと美しく厳しい姿だろう… そしてこんな雄大な山を見つづけていたら、きっといつか頭がパーになるだろうとも思った。
夜中、意外と冷え込んで寒くて何度か目が覚めた。暑いかと思ってシュラフを3シーズンにしたが、雪中キャンプはやはり冬用が正解。ここはちょっとミスった…
---
翌5/22。山は全て見えてご来光も拝めたが、天気は思ったよりも良くなく、上空にうす雲が広がっていた。まぁでもあとは下るだけだ。下り始めの 40度の急斜面、朝は雪が硬いのを警戒していたが、問題なくアイゼンが効く。下りはさすがに早く、1時間ちょっとで最終ダムまで到着。自分でもビックリ。この日は沢山のスキーヤーが登ってきた。この山、スキーも楽しそう。。。
毛勝三山、かなりの体力が必要ですが非常にいい山でこの時期は特にお勧め。特に猫又山から剱岳は一見の価値あり。最高の展望台!
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 triglav
triglav













 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手





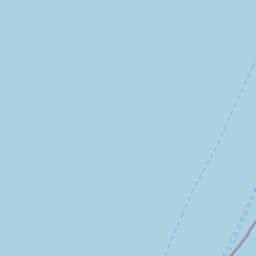

















triglavさん、junjapaです。
ご無沙汰です。連休はどう過ごしていますか。
わたしは、連休前半に毛勝山に行ってきました。この記録のようにテントをあげて縦走しようと思ったのですが、とてもとても(苦笑)。なんとか毛勝山だけゲットで精一杯でした。でも山自体も劔の展望台としても素晴らしいところですネ。
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する