記録ID: 4735044
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
八ヶ岳・蓼科
阿弥陀岳~赤岳周回 行者小屋ベース
2022年09月30日(金) ~
2022年10月01日(土)

体力度
4
1泊以上が適当
- GPS
- 11:38
- 距離
- 15.2km
- 登り
- 1,572m
- 下り
- 1,543m
コースタイム
1日目
- 山行
- 6:07
- 休憩
- 3:28
- 合計
- 9:35
距離 10.5km
登り 1,539m
下り 876m
16:41
| 天候 | 晴れ時々霧 |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2022年09月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
| コース状況/ 危険箇所等 |
とくに危険はありません 阿弥陀岳の登りはコースが何本も交差しているところがあり ルートをよく見極めて登らないと 不安定なガレになってしまいます 慎重に登る方が良いです |
写真
装備
| 個人装備 |
長袖シャツ
Tシャツ
ソフトシェル
タイツ
ズボン
靴下
グローブ
防寒着
雨具
着替え
靴
ザック
ザックカバー
昼ご飯
行動食
非常食
飲料
ガスカートリッジ
コンロ
コッヘル
ライター
地図(地形図)
ヘッドランプ
予備電池
GPS
筆記用具
ファーストエイドキット
常備薬
保険証
携帯
サングラス
タオル
ストック
ナイフ
カメラ
ポール
テント
テントマット
シェラフ
ヘルメット
携帯トイレ
|
|---|
感想
雪が来る前にどこかに出かけたくて 八ヶ岳のテント泊を計画しました 山行計画では 二日目は地蔵尾根を登り横岳から硫黄岳を縦走して 赤岳鉱泉に下山予定でしたが 標高2700m辺りからの目眩が出たため 2日目は下山をしました
この3年間コロナで山での宿泊を躊躇っていたため 標高に身体が順応できなかったのか それとも この3年間で血圧が上がり降圧剤を飲み始めたからか 今まで山で目眩や不調を感じたことはなかったので 原因は不明です
SKさんの「山はいつでもそこにある」の言葉を思い出し 安全第一に慎重を期することにしました それでも週2~3回 4~5kmのランニングを続けていたせいか 下山後の筋肉痛は全くありませんでした 少しずつ様子を見ながら 今後も山に登っていこうと思います
コメント
この記録に関連する登山ルート
無雪期ピークハント/縦走
八ヶ岳・蓼科 [2日]
美濃戸(南沢)~行者小屋~赤岳(文三郎尾根)~横岳~硫黄岳~赤岩の頭~行者小屋~阿弥陀岳(ピストン)
利用交通機関:
車・バイク
技術レベル
2/5
体力レベル
4/5









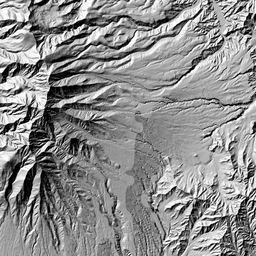

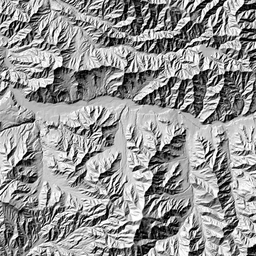


 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手

















































いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する