記録ID: 45785
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
剱・立山
剱岳
2009年09月06日(日) [日帰り]

- GPS
- 10:36
- 距離
- 14.2km
- 登り
- 2,335m
- 下り
- 2,335m
コースタイム
(早月尾根)
2:25馬場島-5:19早月小屋(休憩給水14分)-7:21剱岳山頂(休憩39分)
8:00下山開始-9:41早月小屋(休憩給水22分)-13:01馬場島
2:25馬場島-5:19早月小屋(休憩給水14分)-7:21剱岳山頂(休憩39分)
8:00下山開始-9:41早月小屋(休憩給水22分)-13:01馬場島
| 天候 | 晴れ |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2009年09月の天気図 |
| アクセス | |
| コース状況/ 危険箇所等 |
今回は北ア北部の剱岳と立山遠征。 初日は剱岳。 首都圏から登山口のある馬場島までは、距離的には安房トンネル経由の方が近いが、時間的には上信越道経由の方が圧倒的に有利で楽である。帰路に前者を使って非常に疲れた。 馬場島山荘前に無料駐車場があり、登山口までは歩いて5分程。 途中のキャンプ場には水場とトイレが有る。 早月尾根は途中水場が無いため、早月小屋での水購入(800円/2L)を計画した方が良いが、他の方の山行記録を見ると、水が売り切れの場合や、食事の準備中は売店での対応をしてもらえないこともあるらしい。 水を購入できない場合も考慮して、1.5Lを3つのビニール水筒に分けて、登山道の途中にデポしていったが、幸い小屋で調達できた。 当初は3時スタートの予定であったが、到着の車も多く、1時台になると準備、出発する人が増えてにぎやかになる。さすがにロングコースで日帰りを予定する人は皆さん早出である。 この日の日帰りは、おそらく10人程度だったと思う。 こちらも朝食(夜食?)を食べて2時過ぎに駐車場を出て、キャンプ場で出発準備をする。 幕営者を起こさない様に熊除けの鈴を手で押さえて登山口に向かった。 |
写真
早月尾根登山口(下山時撮影)。暗い中、この登山口でいきなり道迷いをした。
写真の左側のカラーコーン奥に踏み跡があり、進むと15m程で藪になる。
登山口の最初は暖斜面だろうと思ったのが間違いの原因。
もう一度戻って正面の木の奥の「壁」を照らすと、そこに登山道が。
そう、早月尾根を象徴する登山口からの急登であった。
写真の左側のカラーコーン奥に踏み跡があり、進むと15m程で藪になる。
登山口の最初は暖斜面だろうと思ったのが間違いの原因。
もう一度戻って正面の木の奥の「壁」を照らすと、そこに登山道が。
そう、早月尾根を象徴する登山口からの急登であった。
夜明けの早月小屋。
ここまでに3パーティー、15名程度をパスしてきた。丹沢の早朝登山並みに人が多い。
ヘッ電を5:00に消灯して、程なくして小屋が見えてきた。テントが10張以上。
小屋の前は出発準備の団体さんでごった返していた。
水2Lを購入して半分だけ給水し、残りは土間の片隅にデポさせてもらった。
購入したペットボトルはフタが開いていたので、リフィルだと思う。
それでもこのルートでの水提供は大変有り難い。
ここまでに3パーティー、15名程度をパスしてきた。丹沢の早朝登山並みに人が多い。
ヘッ電を5:00に消灯して、程なくして小屋が見えてきた。テントが10張以上。
小屋の前は出発準備の団体さんでごった返していた。
水2Lを購入して半分だけ給水し、残りは土間の片隅にデポさせてもらった。
購入したペットボトルはフタが開いていたので、リフィルだと思う。
それでもこのルートでの水提供は大変有り難い。
山頂手前で別山尾根からの登山道を合わせる。室堂が思ったより近い。
室堂からの高低差は僅かだが、前剱からは厳しそうである。
写真では判らないが、稜線上には多くの登山者が動いている。
やはり別山尾根がメインルートである。
室堂からの高低差は僅かだが、前剱からは厳しそうである。
写真では判らないが、稜線上には多くの登山者が動いている。
やはり別山尾根がメインルートである。
剱岳山頂。
なだらかで広い山頂部にはおそらく100人以上が休憩していた。
山中泊の方が集中する時間なのだろう。
山頂で休憩している間にも、20人単位の団体の到着と出発があった。
祠の前での記念撮影もままならない。
途中の小屋は「大盛況」だったことは想像に難くない。
なだらかで広い山頂部にはおそらく100人以上が休憩していた。
山中泊の方が集中する時間なのだろう。
山頂で休憩している間にも、20人単位の団体の到着と出発があった。
祠の前での記念撮影もままならない。
途中の小屋は「大盛況」だったことは想像に難くない。
山頂からの立山方向。文句なしの快晴である。
立山の向こうには、右から薬師岳、黒部五郎、笠ヶ岳と並ぶ。その左奥には乗鞍も見える。水晶、鷲羽と続き雄山に隠れる。
大汝山の向こうには、穂高、槍が逆光に浮かぶ。さらに大天井、常念と稜線が続く。
立山の向こうには、右から薬師岳、黒部五郎、笠ヶ岳と並ぶ。その左奥には乗鞍も見える。水晶、鷲羽と続き雄山に隠れる。
大汝山の向こうには、穂高、槍が逆光に浮かぶ。さらに大天井、常念と稜線が続く。
後立山方向のパノラマ。
左側の毛勝山から黒部渓谷を挟み、後立山の稜線が立ち上がり、旭岳とその奥の白馬岳が並ぶ。その右には鑓ヶ岳、不帰嶮、唐松岳、五竜岳と続く。さらに八峰キレットの右には双耳の鹿島槍が近い。
鹿島槍からここ剱岳を眺めていたのは昨年の夏休みであった。
http://www.yamareco.com/modules/yamareco/photodetail.php?did=30885&pid=95a50fbc6bf4f2722d44e9cc661553f0
左側の毛勝山から黒部渓谷を挟み、後立山の稜線が立ち上がり、旭岳とその奥の白馬岳が並ぶ。その右には鑓ヶ岳、不帰嶮、唐松岳、五竜岳と続く。さらに八峰キレットの右には双耳の鹿島槍が近い。
鹿島槍からここ剱岳を眺めていたのは昨年の夏休みであった。
http://www.yamareco.com/modules/yamareco/photodetail.php?did=30885&pid=95a50fbc6bf4f2722d44e9cc661553f0
試練と憧れ。
登山後に見るとちょっとだけ感慨深い。
(以下追記)
下山中ちょっと不思議なことがあった。
早月小屋を出発してしばらくしたころ、急降下の進行方向の木の上にチェックのネルシャツを着た若い方が登っており、下山する私のことを見ていた。
軽く会釈して、その木の下に行ったら挨拶をするつもりでいた。
しかし登山道はその木のある目算方向とは大きく逸れて下っていき、周りを見回したがそれらしき木は発見できなかった。
お昼前の出来事で、地元の方が木登りでもしているのかもと思ってあまり気にも留めなかったが、今考えると、木登りをするには場所的にも不自然で、良く解らない出来事であった。
登山後に見るとちょっとだけ感慨深い。
(以下追記)
下山中ちょっと不思議なことがあった。
早月小屋を出発してしばらくしたころ、急降下の進行方向の木の上にチェックのネルシャツを着た若い方が登っており、下山する私のことを見ていた。
軽く会釈して、その木の下に行ったら挨拶をするつもりでいた。
しかし登山道はその木のある目算方向とは大きく逸れて下っていき、周りを見回したがそれらしき木は発見できなかった。
お昼前の出来事で、地元の方が木登りでもしているのかもと思ってあまり気にも留めなかったが、今考えると、木登りをするには場所的にも不自然で、良く解らない出来事であった。
感想
高度感が苦手な私が今まで何となく恐れていた山。
しかし早月尾根は、上部に多少の鎖はあるものの、怖いところは全く無く、少々拍子抜けした。
それよりも、急斜面の木の根っ子の方が余程強敵で、登山時は問題ないが、下山時は相当苦労した。
下りは意識的にゆっくり歩いたが、それでも根っ子でスリップして転倒した。幸いザックがクッションになって尻餅程度で済んだが(でも結構強打!)、長時間の急斜面の下りは集中力の持続が難しい。
下りは多くの日帰り登山者に道を譲ることになった。
山小屋の方はとても気さくであった。
朝方に剱御前で転落事故があったらしい。
膝が悪い場合は、事故防止のため、とにかくゆっくり下れと言っていた。
言われたそばからスリップしているので世話はない。
ここ数日は安定した秋空が続き、一年の中で一番登山に良い季節だと思う。
しかし、午後からは雲が上がってきてしまうため、やはりまだ午前中の登山が吉の様である。
下山後は「つるぎふれあい館アルプスの湯」(600円)で入浴した。サウナ有り。
明日の立山に続く。
http://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-45789.html

 MATSU
MATSU













 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手
































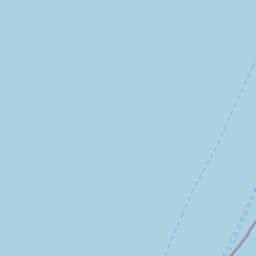



















天気も眺望も最高ですね!!
剱岳は、何時かは…と、思う憧れの山です。。
2年少々で登られるところが、すごいですね。
確かに車で行くと、登って下って、そして帰るまでの体力計算しないと。。
お疲れ様でした。
私の様な初心者が登れるのは天候の安定したこの時期だけだと思います。
何しろ「剱」ですから、私も登山前は少々不安でした。
しかし、山頂には団体さんも多く、困難な山を制覇したという実感はありませんでした。
実際、山頂で写真を撮ってもらったツアーのオジサンは、登山を今年から始めて、高尾山、富士山と登り、剱岳が3山目、と言っていました。
マイカー登山は気楽ですが、縦走ができないのと、当然行き帰りの運転をしなければいけないのが難点ですね。
から日帰りですか
大変だったんじゃないんですか?
一般的に室堂から登る人が多いですからね。
その途中のカニのタテバイとヨコバイが渋滞のもと。
ヨコバイは怖かったですが。
困難な山って感じではないですが、早月から日帰りで行ってるんですから立派な山行記録ですよね
コメント有り難うございます。
カニのヨコバイはやっぱり怖いですか。。
多少の高低差は気になりませんが、高度感はダメですね。
来年はクライミングに挑戦して、何とか高所恐怖症を克服したいと思っています。
去年自分も早月経由で行きましたが、なんと日帰りとは。
早月小屋の親父は、気さくな方でしたね。同感です。
あと、地元の自治体の観光用ポスターで、早月尾根からの剱岳の写真があるのですけれど、かなりお気に入りです。こっちからの剱岳の山容もいいですよね。
膝痛はだましだましです。
tenmouさんのアドバイスにもありました通り、膝の角度をX脚にしたり、色々と変化させて疲れを分散させています。
観光用のポスターは未確認ですが、私が好きな剱岳は、おそらく同じアングルの中山からの剱岳です。気が遠くなる程遠大な早月尾根の写真にそそられました。正に「試練と憧れ」だと思いました。
稚拙な日記をお読みいただきありがとうございます。
私も今年初めて悩まされまて、途中下山等してましたが、以前と変わらぬくらいまでに回復しております。
爆弾を抱えているのは変わりませんが。
早月からの写真は、これです。圧倒されました。
確か馬場荘で売っていたと記憶しておりますが、購入すべきでした。
http://www.town.kamiichi.toyama.jp/hp/kanko_turugi/turugi_top.htm
凄い迫力ですね。
容赦なく2,200mを一気に突き上げるルートの特徴と早月小屋から先の岩場の急登が良く判ります。
これを見て俄然ファイトが湧くか、尻込みするか...
尾根の角度から見て中山からではなく、馬場島の北側からの撮影だと思います。
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する