 旭登山口より出発。早朝より登山口には4台ほどの車両、うち2台は露を被り、前泊と思われる。
旭登山口より出発。早朝より登山口には4台ほどの車両、うち2台は露を被り、前泊と思われる。
 3
3
旭登山口より出発。早朝より登山口には4台ほどの車両、うち2台は露を被り、前泊と思われる。
 出発したつもりが、沢山のヒメシャラの落花に足が止まる。スタートできない・・。
出発したつもりが、沢山のヒメシャラの落花に足が止まる。スタートできない・・。
 8
8
出発したつもりが、沢山のヒメシャラの落花に足が止まる。スタートできない・・。
 またも、スタート直後に稜線からの朝日に足が止まる。
またも、スタート直後に稜線からの朝日に足が止まる。
「旭登山口での、朝日、。」
 11
11
またも、スタート直後に稜線からの朝日に足が止まる。
「旭登山口での、朝日、。」
 暫くは、森の中。初めて釈迦ヶ岳へ登ったとき、つたない情報で、「笹原を進む」と記憶していたが、笹原では無く森の中だったので不安を感じたことを思い出す。
暫くは、森の中。初めて釈迦ヶ岳へ登ったとき、つたない情報で、「笹原を進む」と記憶していたが、笹原では無く森の中だったので不安を感じたことを思い出す。
 5
5
暫くは、森の中。初めて釈迦ヶ岳へ登ったとき、つたない情報で、「笹原を進む」と記憶していたが、笹原では無く森の中だったので不安を感じたことを思い出す。
 赤い×は赤井谷への下り口。赤井谷は「ほんみち」(宗教法人)さんの所有地なので入る前に許可を得られたほうが良いみたいです。
赤い×は赤井谷への下り口。赤井谷は「ほんみち」(宗教法人)さんの所有地なので入る前に許可を得られたほうが良いみたいです。
歩いてみたいです・・、赤井谷。
 2
2
赤い×は赤井谷への下り口。赤井谷は「ほんみち」(宗教法人)さんの所有地なので入る前に許可を得られたほうが良いみたいです。
歩いてみたいです・・、赤井谷。
 ちょっと、フライングな紅葉?
ちょっと、フライングな紅葉?
「緑」盛りの中での赤は目立ちます。
 4
4
ちょっと、フライングな紅葉?
「緑」盛りの中での赤は目立ちます。
 気持ち良い道となります。標高1500mぐらいまでは草付の道です。
気持ち良い道となります。標高1500mぐらいまでは草付の道です。
朝露なのか、雨なのか?濡れてます。今更、ゲイターを使っても、役に立ちそうになく、諦めて歩きます。
 6
6
気持ち良い道となります。標高1500mぐらいまでは草付の道です。
朝露なのか、雨なのか?濡れてます。今更、ゲイターを使っても、役に立ちそうになく、諦めて歩きます。
 大峰の立ち枯れは良く見ますが、なぜか惹かれる存在感を感じます。
大峰の立ち枯れは良く見ますが、なぜか惹かれる存在感を感じます。
 4
4
大峰の立ち枯れは良く見ますが、なぜか惹かれる存在感を感じます。
 この辺りは、高い確率で雲海に出会えます。
この辺りは、高い確率で雲海に出会えます。
今日は、旭の谷から高野方面が雲に包まれています。
やや、左に島のように見える山のピークが、何気に・・。
 13
13
この辺りは、高い確率で雲海に出会えます。
今日は、旭の谷から高野方面が雲に包まれています。
やや、左に島のように見える山のピークが、何気に・・。
 赤井谷方向、向こうは、長く伸びる、南奥駈の稜線。
赤井谷方向、向こうは、長く伸びる、南奥駈の稜線。
 5
5
赤井谷方向、向こうは、長く伸びる、南奥駈の稜線。
 不動小屋谷出合。不動小屋谷ルートはあまり使われて無いようで踏み後も薄いようでした。
不動小屋谷出合。不動小屋谷ルートはあまり使われて無いようで踏み後も薄いようでした。
 1
1
不動小屋谷出合。不動小屋谷ルートはあまり使われて無いようで踏み後も薄いようでした。
 おっ、(ゲート?)試されてる?この間を、真っ直ぐに進みました。進めました。
おっ、(ゲート?)試されてる?この間を、真っ直ぐに進みました。進めました。
もし、体の何処かが触れたら、ダイエットをしろと言う意味なのでしょうか?
 7
7
おっ、(ゲート?)試されてる?この間を、真っ直ぐに進みました。進めました。
もし、体の何処かが触れたら、ダイエットをしろと言う意味なのでしょうか?
 これは・・、共生では無くて、寄生?ですか?
これは・・、共生では無くて、寄生?ですか?
朝日を浴びて健康そう。
木のほうは、迷惑してんのかなぁ。。。
 16
16
これは・・、共生では無くて、寄生?ですか?
朝日を浴びて健康そう。
木のほうは、迷惑してんのかなぁ。。。
 赤井谷の南方に(中央)台形の南奥駈道・笠捨山が見える。
赤井谷の南方に(中央)台形の南奥駈道・笠捨山が見える。
西行法師が、急登に疲れ、笠を捨てたと・・。
 2
2
赤井谷の南方に(中央)台形の南奥駈道・笠捨山が見える。
西行法師が、急登に疲れ、笠を捨てたと・・。
 バイケイソウはもうすぐ花期を終えます。
バイケイソウはもうすぐ花期を終えます。
春に芽吹き、一気に80cm程成長し、一斉に花を咲かせ、3ヶ月ほどで土に返る。実に、忙しい。
(個人的には、あまり、好きでない。)
 5
5
バイケイソウはもうすぐ花期を終えます。
春に芽吹き、一気に80cm程成長し、一斉に花を咲かせ、3ヶ月ほどで土に返る。実に、忙しい。
(個人的には、あまり、好きでない。)
 古田ノ森。ここは、いつも、通過です。
古田ノ森。ここは、いつも、通過です。
 2
2
古田ノ森。ここは、いつも、通過です。
 古田ノ森を少し過ぎると、少しの幅のカエデの森。気持ちよい林です。
古田ノ森を少し過ぎると、少しの幅のカエデの森。気持ちよい林です。
 6
6
古田ノ森を少し過ぎると、少しの幅のカエデの森。気持ちよい林です。
 正面に釈迦ヶ岳が現れる。
正面に釈迦ヶ岳が現れる。
穏やかなアップダウンが続きます。
 5
5
正面に釈迦ヶ岳が現れる。
穏やかなアップダウンが続きます。
 以前より「ほんみち」さんの境界杭が目立ちます。
以前より「ほんみち」さんの境界杭が目立ちます。
 2
2
以前より「ほんみち」さんの境界杭が目立ちます。
 千丈平です。カエデ・トウヒ・シラベ(シラビソ)の森で、穏やかな場所です。
千丈平です。カエデ・トウヒ・シラベ(シラビソ)の森で、穏やかな場所です。
 1
1
千丈平です。カエデ・トウヒ・シラベ(シラビソ)の森で、穏やかな場所です。
 千丈平、キャンプ適地。
千丈平、キャンプ適地。
この看板の間を進むと、深仙ノ宿へのトラバース道です。
 1
1
千丈平、キャンプ適地。
この看板の間を進むと、深仙ノ宿へのトラバース道です。
 先ほどの標示から100mほど進んだ右の「かくし水」です。しっかり出てます。
先ほどの標示から100mほど進んだ右の「かくし水」です。しっかり出てます。
(まれに、真夏の渇水期は、枯れることもあるらしい。)
 3
3
先ほどの標示から100mほど進んだ右の「かくし水」です。しっかり出てます。
(まれに、真夏の渇水期は、枯れることもあるらしい。)
 水場を過ぎると急登となります。
水場を過ぎると急登となります。
 2
2
水場を過ぎると急登となります。
 ここで、奥駈道に合流です。
ここで、奥駈道に合流です。
登山口に「大峯奥駈道」の表記がありますが、ここまではアクセス路で大峯奥駈道とはなりません。
 1
1
ここで、奥駈道に合流です。
登山口に「大峯奥駈道」の表記がありますが、ここまではアクセス路で大峯奥駈道とはなりません。
 奥駈道から200m登って山頂です。
奥駈道から200m登って山頂です。
ガスに包まれています。雨ではありません。
先ずは、手を合わせます。
 9
9
奥駈道から200m登って山頂です。
ガスに包まれています。雨ではありません。
先ずは、手を合わせます。
 台座の「ゾウだゾゥ~」、。
台座の「ゾウだゾゥ~」、。
想像動物なんだろうけど・・、爪の位置が???
確かに、アジアゾウは(前足)5つの爪を持つが・・。
 5
5
台座の「ゾウだゾゥ~」、。
想像動物なんだろうけど・・、爪の位置が???
確かに、アジアゾウは(前足)5つの爪を持つが・・。
 たっち。
たっち。
一等三角点・本点。
 9
9
たっち。
一等三角点・本点。
 奥駈道を北方へ。ヤセ尾根に、スチールの杭が打たれてる。実は、この杭を意識せず、上を歩けば歩きやすい。ただし、風があれば怖いかも?
奥駈道を北方へ。ヤセ尾根に、スチールの杭が打たれてる。実は、この杭を意識せず、上を歩けば歩きやすい。ただし、風があれば怖いかも?
この後、クサリも何箇所かあります。
 0
0
奥駈道を北方へ。ヤセ尾根に、スチールの杭が打たれてる。実は、この杭を意識せず、上を歩けば歩きやすい。ただし、風があれば怖いかも?
この後、クサリも何箇所かあります。
 進路、(右)孔雀岳、(左)仏生嶽。
進路、(右)孔雀岳、(左)仏生嶽。
 6
6
進路、(右)孔雀岳、(左)仏生嶽。
 先ずは、下って下って、1800mの釈迦山頂から1650m位まで、標高を落とします。(戻りは辛い、登りです。)
先ずは、下って下って、1800mの釈迦山頂から1650m位まで、標高を落とします。(戻りは辛い、登りです。)
大石を巻いた後は登りに転じます。
ここも、心地良い森です。
 2
2
先ずは、下って下って、1800mの釈迦山頂から1650m位まで、標高を落とします。(戻りは辛い、登りです。)
大石を巻いた後は登りに転じます。
ここも、心地良い森です。
 笹道が続きます。深いところは60cmほどで露に濡れてて・・、諦めが重要かと・・。
笹道が続きます。深いところは60cmほどで露に濡れてて・・、諦めが重要かと・・。
 3
3
笹道が続きます。深いところは60cmほどで露に濡れてて・・、諦めが重要かと・・。
 奇岩、たぶん「鳥の頭」に見られるのだろが・・。
奇岩、たぶん「鳥の頭」に見られるのだろが・・。
 11
11
奇岩、たぶん「鳥の頭」に見られるのだろが・・。
 掾の鼻(えんのはな)。
掾の鼻(えんのはな)。
蔵王権現が八経ヶ岳を向いています。
実に力強い。
 4
4
掾の鼻(えんのはな)。
蔵王権現が八経ヶ岳を向いています。
実に力強い。
 ここから、北方の谷の眺めは絶景とされている。
ここから、北方の谷の眺めは絶景とされている。
4名の前泊(楊子ノ宿)の方々とお会いした。
 4
4
ここから、北方の谷の眺めは絶景とされている。
4名の前泊(楊子ノ宿)の方々とお会いした。
 掾の鼻を過ぎると、やや穏やかな道となる。
掾の鼻を過ぎると、やや穏やかな道となる。
 1
1
掾の鼻を過ぎると、やや穏やかな道となる。
 孔雀手前で、1箇所だけ岩登りあり。
孔雀手前で、1箇所だけ岩登りあり。
ここは、ロープ無しで登れる。下りは、ローブは補助として。
 1
1
孔雀手前で、1箇所だけ岩登りあり。
ここは、ロープ無しで登れる。下りは、ローブは補助として。
 孔雀ノ覗着。
孔雀ノ覗着。
 1
1
孔雀ノ覗着。
 覗き込むと、十六羅漢と呼ばれる石柱群を眺める。
覗き込むと、十六羅漢と呼ばれる石柱群を眺める。
写真以上の険しさで、人を近づけない雰囲気を感じる。
 5
5
覗き込むと、十六羅漢と呼ばれる石柱群を眺める。
写真以上の険しさで、人を近づけない雰囲気を感じる。
 どうしたら良い?
どうしたら良い?
「仏生嶽」「仏生岳」「仏生ヶ岳」。。。
どれが正しいのか?
とりあえず、私は、「仏生嶽」で。
 2
2
どうしたら良い?
「仏生嶽」「仏生岳」「仏生ヶ岳」。。。
どれが正しいのか?
とりあえず、私は、「仏生嶽」で。
 孔雀-仏生は所々、石・苔の道が目立ちます。
孔雀-仏生は所々、石・苔の道が目立ちます。
 2
2
孔雀-仏生は所々、石・苔の道が目立ちます。
 孔雀岳直下の「鳥の水」です。
孔雀岳直下の「鳥の水」です。
細いですが、出てました。500mlで80秒ほど要しました。
 2
2
孔雀岳直下の「鳥の水」です。
細いですが、出てました。500mlで80秒ほど要しました。
 しっかり目立ちますが、渇水時期は止まりそうでした。
しっかり目立ちますが、渇水時期は止まりそうでした。
 2
2
しっかり目立ちますが、渇水時期は止まりそうでした。
 この石柱からが注意部分です。
この石柱からが注意部分です。
 2
2
この石柱からが注意部分です。
 穏やかな林を歩きますが、樹林の間を右左に・・、方向感覚が狂い、迷いやすい感じです。
穏やかな林を歩きますが、樹林の間を右左に・・、方向感覚が狂い、迷いやすい感じです。
この区間は、注意が必要です。
 3
3
穏やかな林を歩きますが、樹林の間を右左に・・、方向感覚が狂い、迷いやすい感じです。
この区間は、注意が必要です。
 またですが・・、立ち枯れ。
またですが・・、立ち枯れ。
酸性雨だけが原因では無いのでしょうが。
 9
9
またですが・・、立ち枯れ。
酸性雨だけが原因では無いのでしょうが。
 仏生嶽の巻き道です。ピークは過ぎてます。
仏生嶽の巻き道です。ピークは過ぎてます。
この上部辺りが、ダイヤモンド富士(富士山山頂からの日の出)が観測される最遠地点と思われます。
美しい、原生林ですね。
 4
4
仏生嶽の巻き道です。ピークは過ぎてます。
この上部辺りが、ダイヤモンド富士(富士山山頂からの日の出)が観測される最遠地点と思われます。
美しい、原生林ですね。
 楊子宿へは下りです。登山路が降雨時の水路かの区別がつきません。
楊子宿へは下りです。登山路が降雨時の水路かの区別がつきません。
 1
1
楊子宿へは下りです。登山路が降雨時の水路かの区別がつきません。
 楊子ノ宿非難小屋。
楊子ノ宿非難小屋。
見学は後で。
 1
1
楊子ノ宿非難小屋。
見学は後で。
 笹原の向こうに、P1693、本日の目的地。
笹原の向こうに、P1693、本日の目的地。
 2
2
笹原の向こうに、P1693、本日の目的地。
 楊子宿。新しい金剛杖が1本ありました。
楊子宿。新しい金剛杖が1本ありました。
靡(なびき)と呼ばれる行場です。
 1
1
楊子宿。新しい金剛杖が1本ありました。
靡(なびき)と呼ばれる行場です。
 石柱が・・、寝てます。
石柱が・・、寝てます。
P1693へ直登でなく巻き道の奥駈道を進みます。
 0
0
石柱が・・、寝てます。
P1693へ直登でなく巻き道の奥駈道を進みます。
 P1693への分岐です。
P1693への分岐です。
ここは、先日(7/12)八経から訪れました。
 0
0
P1693への分岐です。
ここは、先日(7/12)八経から訪れました。
 急登を登りP1693です。
急登を登りP1693です。
八経ヶ岳はガスの中です。
7/12、ここから七面山(東峰)を往復しました。
 0
0
急登を登りP1693です。
八経ヶ岳はガスの中です。
7/12、ここから七面山(東峰)を往復しました。
 楊子宿へ下ります。
楊子宿へ下ります。
こちらは、倒木も多く、登るのは辛そうです。あまり、(登りには)お勧めできないかな?
 1
1
楊子宿へ下ります。
こちらは、倒木も多く、登るのは辛そうです。あまり、(登りには)お勧めできないかな?
 楊子宿の笹原の景色です。
楊子宿の笹原の景色です。
 2
2
楊子宿の笹原の景色です。
 七面山の絶壁です。「険しい」の一言です!
七面山の絶壁です。「険しい」の一言です!
 15
15
七面山の絶壁です。「険しい」の一言です!
 楊子ノ宿非難小屋。小休憩。
楊子ノ宿非難小屋。小休憩。
 4
4
楊子ノ宿非難小屋。小休憩。
 新宮山彦ぐるーぷさんの案内。
新宮山彦ぐるーぷさんの案内。
ありがたいですね。
 1
1
新宮山彦ぐるーぷさんの案内。
ありがたいですね。
 仏生の登りですが、まだ今日は、強い疲れは表れていない。気温が高くないのもあるのかな?
仏生の登りですが、まだ今日は、強い疲れは表れていない。気温が高くないのもあるのかな?
原生林が気分良いのもあるだろう。
 0
0
仏生の登りですが、まだ今日は、強い疲れは表れていない。気温が高くないのもあるのかな?
原生林が気分良いのもあるだろう。
 木々のあいだから、釈迦ヶ岳を望む。まだ、遠いなぁと・・。
木々のあいだから、釈迦ヶ岳を望む。まだ、遠いなぁと・・。
 0
0
木々のあいだから、釈迦ヶ岳を望む。まだ、遠いなぁと・・。
 仏生嶽は奥駈道から外れています。折角なのでピークへ向かいます。
仏生嶽は奥駈道から外れています。折角なのでピークへ向かいます。
 0
0
仏生嶽は奥駈道から外れています。折角なのでピークへ向かいます。
 仏生嶽山頂。
仏生嶽山頂。
(一部の)日本仏教で、ここ仏生嶽がお釈迦様の生誕の地と考えられています。
では、釈迦ヶ岳は・・・。
 1
1
仏生嶽山頂。
(一部の)日本仏教で、ここ仏生嶽がお釈迦様の生誕の地と考えられています。
では、釈迦ヶ岳は・・・。
 三角点がありますので、たっちでし。
三角点がありますので、たっちでし。
 8
8
三角点がありますので、たっちでし。
 ショウキラン。
ショウキラン。
見つけたのは1株だけでした。
 13
13
ショウキラン。
見つけたのは1株だけでした。
 平地から、孔雀岳です。
平地から、孔雀岳です。
三角点はありません。
 1
1
平地から、孔雀岳です。
三角点はありません。
 そして、釈迦ヶ岳、少し近くなる。
そして、釈迦ヶ岳、少し近くなる。
 1
1
そして、釈迦ヶ岳、少し近くなる。
 キャンプ適地です。
キャンプ適地です。
日当たり良く、「鳥の水」から歩3~4分です。
水さえ確保できれば良い感じです。
 1
1
キャンプ適地です。
日当たり良く、「鳥の水」から歩3~4分です。
水さえ確保できれば良い感じです。
 孔雀岳への分岐、ここから7~8分で、山頂だったと思います。
孔雀岳への分岐、ここから7~8分で、山頂だったと思います。
 0
0
孔雀岳への分岐、ここから7~8分で、山頂だったと思います。
 美しい、苔と樹林の道を戻ると・・。
美しい、苔と樹林の道を戻ると・・。
 5
5
美しい、苔と樹林の道を戻ると・・。
 孔雀ノ覗。
孔雀ノ覗。
ここで、仏生の下ですれ違った女性の行者さんと再会し、少しお話しさせていただいた。
昨日は弥山(みせん)でお泊りで、夕立にあわれたと・・。「誰かが、聖宝理源大師像を触ったのだろう」と・・。
 6
6
孔雀ノ覗。
ここで、仏生の下ですれ違った女性の行者さんと再会し、少しお話しさせていただいた。
昨日は弥山(みせん)でお泊りで、夕立にあわれたと・・。「誰かが、聖宝理源大師像を触ったのだろう」と・・。
 もう一度、覗いとく。
もう一度、覗いとく。
高度感はあるが、恐怖はあまり感じない。って、どうせ遠目で眺めてただけですから。(ハイ、チキンですから。)
 3
3
もう一度、覗いとく。
高度感はあるが、恐怖はあまり感じない。って、どうせ遠目で眺めてただけですから。(ハイ、チキンですから。)
 先発した、女性行者さん。
先発した、女性行者さん。
後で、道を譲っていただいた。
 2
2
先発した、女性行者さん。
後で、道を譲っていただいた。
 シロヤシオ(ゴヨウツツジ)は葉の外がやや赤みのあるものも。(個体差あり。)
シロヤシオ(ゴヨウツツジ)は葉の外がやや赤みのあるものも。(個体差あり。)
 0
0
シロヤシオ(ゴヨウツツジ)は葉の外がやや赤みのあるものも。(個体差あり。)
 (たぶん?)「両部分け」と呼ばれる。キレット。
(たぶん?)「両部分け」と呼ばれる。キレット。
ただし、別の場所を「両部分け」と言われる方も多く、言葉は残ってても、場所の特定が曖昧な箇所が多い。
 3
3
(たぶん?)「両部分け」と呼ばれる。キレット。
ただし、別の場所を「両部分け」と言われる方も多く、言葉は残ってても、場所の特定が曖昧な箇所が多い。
 橡の鼻。
橡の鼻。
釈迦ヶ岳周辺の4体の仏像。釈迦・大日・千手・蔵王権現の中では、私としては、こちらの蔵王権現様が一番好きです。(個人的意見です。)
 5
5
橡の鼻。
釈迦ヶ岳周辺の4体の仏像。釈迦・大日・千手・蔵王権現の中では、私としては、こちらの蔵王権現様が一番好きです。(個人的意見です。)
 橡の鼻からの谷間。
橡の鼻からの谷間。
「お~」とか「わ~」とか「ヤッホー」とか、心の中で叫ぶ。
 8
8
橡の鼻からの谷間。
「お~」とか「わ~」とか「ヤッホー」とか、心の中で叫ぶ。
 橡の鼻からの釈迦ヶ岳。
橡の鼻からの釈迦ヶ岳。
 2
2
橡の鼻からの釈迦ヶ岳。
 ズームで山頂。
ズームで山頂。
お釈迦様の、斜め後姿が拝めます。
 1
1
ズームで山頂。
お釈迦様の、斜め後姿が拝めます。
 落ちると痛そうな所。
落ちると痛そうな所。
何処も、落ちれば痛いか?
 2
2
落ちると痛そうな所。
何処も、落ちれば痛いか?
 ここからの、0.6kmは厳しいです。
ここからの、0.6kmは厳しいです。
下って、登ってとなります。
 0
0
ここからの、0.6kmは厳しいです。
下って、登ってとなります。
 こちら、大峰の「モアイ」です。
こちら、大峰の「モアイ」です。
 6
6
こちら、大峰の「モアイ」です。
 「モアイ」と大岩と奥の釈迦ヶ岳です。
「モアイ」と大岩と奥の釈迦ヶ岳です。
モアイは、何を想い、何処を眺めているのでしょう、。
 1
1
「モアイ」と大岩と奥の釈迦ヶ岳です。
モアイは、何を想い、何処を眺めているのでしょう、。
 釈迦ヶ岳へは険しく急な登りが連続します。
釈迦ヶ岳へは険しく急な登りが連続します。
この辺りで、ホラの音色が聞こえてきた、あっ、あの女性行者さんが「橡の鼻」に着いたんだなぁと思う。
 3
3
釈迦ヶ岳へは険しく急な登りが連続します。
この辺りで、ホラの音色が聞こえてきた、あっ、あの女性行者さんが「橡の鼻」に着いたんだなぁと思う。
 朝は、ガスがあったのですが・・、ガスが飛んで、高度感を感じます。落ちると、かなり、痛そうな・・。
朝は、ガスがあったのですが・・、ガスが飛んで、高度感を感じます。落ちると、かなり、痛そうな・・。
 0
0
朝は、ガスがあったのですが・・、ガスが飛んで、高度感を感じます。落ちると、かなり、痛そうな・・。
 釈迦山頂脇。
釈迦山頂脇。
ベニドウダン(ツツジ)が残っています。
 3
3
釈迦山頂脇。
ベニドウダン(ツツジ)が残っています。
 お釈迦様に再び、手を合わす。
お釈迦様に再び、手を合わす。
そうそ、ここ釈迦ヶ岳は、実は・・、お釈迦様の亡くなった(入滅)の地と考えられています。(一部の日本仏教にて。)
実は、悲しい山頂なのですね。
 12
12
お釈迦様に再び、手を合わす。
そうそ、ここ釈迦ヶ岳は、実は・・、お釈迦様の亡くなった(入滅)の地と考えられています。(一部の日本仏教にて。)
実は、悲しい山頂なのですね。
 ぷしゅ~で休憩。
ぷしゅ~で休憩。
後から来られた、赤井谷を歩かれたという方としばしお話しを楽しみました。
 10
10
ぷしゅ~で休憩。
後から来られた、赤井谷を歩かれたという方としばしお話しを楽しみました。
 お釈迦様の足元のレンゲ(蓮花)の創りも素晴らしい。
お釈迦様の足元のレンゲ(蓮花)の創りも素晴らしい。
左の理源大師は笑ってる。(?)
 0
0
お釈迦様の足元のレンゲ(蓮花)の創りも素晴らしい。
左の理源大師は笑ってる。(?)
 帰りま~す。
帰りま~す。
ここが、私DCTのプロフ写真の場所です。
写真は、紅葉の夕景です。あの写真を撮った後で日没になり、半泣きで下山しました。
 11
11
帰りま~す。
ここが、私DCTのプロフ写真の場所です。
写真は、紅葉の夕景です。あの写真を撮った後で日没になり、半泣きで下山しました。
 立派な角の雄鹿です。あまり、警戒してない。
立派な角の雄鹿です。あまり、警戒してない。
夏毛の白いゴマが見えます。冬毛ではゴマ柄はありません。
 16
16
立派な角の雄鹿です。あまり、警戒してない。
夏毛の白いゴマが見えます。冬毛ではゴマ柄はありません。
 気持ち良く帰ります。
気持ち良く帰ります。
 4
4
気持ち良く帰ります。
 大日岳の白岩群を望む。
大日岳の白岩群を望む。
何だか?初夏の頃、ヤマレコ内で大日の岩登りレコが多いなぁと、感じましたね。
 4
4
大日岳の白岩群を望む。
何だか?初夏の頃、ヤマレコ内で大日の岩登りレコが多いなぁと、感じましたね。
 絵になる景色が多いです。
絵になる景色が多いです。
 8
8
絵になる景色が多いです。
 不動小屋谷出合。
不動小屋谷出合。
あと30分ちょっとで、登山口です。
 0
0
不動小屋谷出合。
あと30分ちょっとで、登山口です。
 あっ、おっっっ、ゴムのなる木。
あっ、おっっっ、ゴムのなる木。
けっこう、あちこちで、見ますなぁ。
 3
3
あっ、おっっっ、ゴムのなる木。
けっこう、あちこちで、見ますなぁ。
 ナナカマドの結実。これから実が大きくなって、真っ赤に色変わりします。
ナナカマドの結実。これから実が大きくなって、真っ赤に色変わりします。
たまに、街路樹に使われてます。
 1
1
ナナカマドの結実。これから実が大きくなって、真っ赤に色変わりします。
たまに、街路樹に使われてます。
 森を抜けて・・。
森を抜けて・・。
ですが、両側の熊笹(?)の葉がほとんどありません、鹿が全部食べつくしたのでしょう?鹿ってそんなに大食漢?それとも、凄い頭数がいるのでしょうか?
 0
0
森を抜けて・・。
ですが、両側の熊笹(?)の葉がほとんどありません、鹿が全部食べつくしたのでしょう?鹿ってそんなに大食漢?それとも、凄い頭数がいるのでしょうか?
 帰りました。うす曇で、気温は24℃まで下がってました。
帰りました。うす曇で、気温は24℃まで下がってました。
この後、帰路中、突然の雷雨で、五條・坂本の郵便局の軒下で40分の雨宿り。バイクの辛いところです。
 4
4
帰りました。うす曇で、気温は24℃まで下がってました。
この後、帰路中、突然の雷雨で、五條・坂本の郵便局の軒下で40分の雨宿り。バイクの辛いところです。
 五條まで戻り、7/12と同じ台湾料理(中華)店さんへ。
五條まで戻り、7/12と同じ台湾料理(中華)店さんへ。
ボリュームたっぷりで、ガッツリでした。980円。
 16
16
五條まで戻り、7/12と同じ台湾料理(中華)店さんへ。
ボリュームたっぷりで、ガッツリでした。980円。


 DCT
DCT







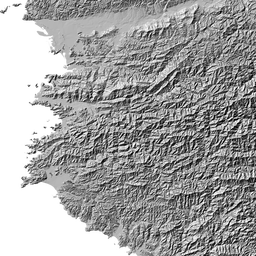
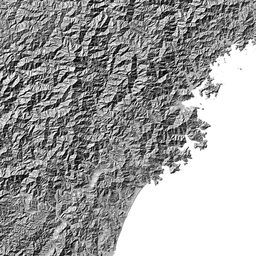
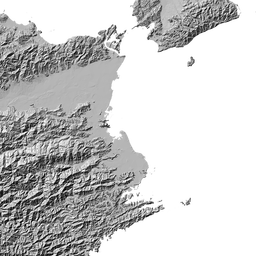
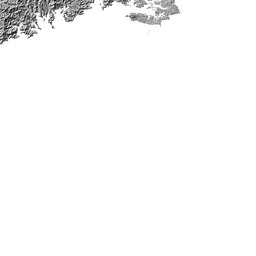
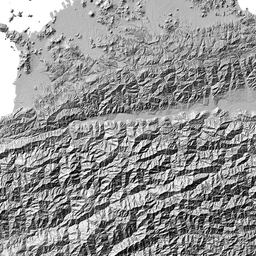

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手






























































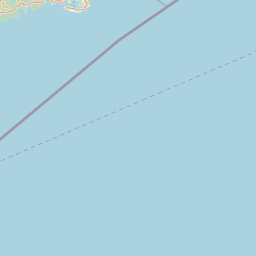

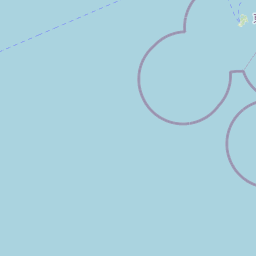

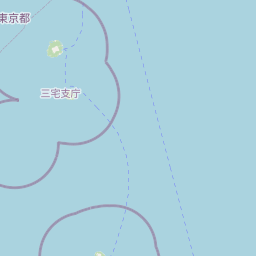














DCTさんは 大峰方面をよく歩かれていますね。
私も山での出会いを大切にしたいと思います。
旭登山口~楊枝の宿往復はアップダウンも多く大変だったと思います。
途中のモアイは気がつきませんでした。
たしかに そっくりですよね。
今度 歩くときは しっかり見ますね。
それとプロフィール写真 「八経ケ岳の夕景」 テント泊でないと撮れませんよね。
これからも安全で楽しい山歩きを続けて下さい。
karchiさん、こんにちは。
モアイは、モアイにしか見えないです。(私には。)
山の不思議は、見ず知らずの方との仲間意識です。町の交差点で信号待ちをしながら挨拶をすることはありませんが、山では自然と挨拶を交わします。短い挨拶にも、深い意味を感じます。
「こんにちは」=特に問題なし。
「こんにちは、頑張ってください」=この先、厳しい道あり。
「こんにちは、お気をつけて」=この先、危険箇所り。
などと、推測できます。たま~に、無言の方もおられますが・・。
プロフの写真は、数年前に、ここの千丈平と古田ノ森の間のこのレコの№89の場所での夕景でした。この写真を撮ったあと、「ストン!」と日が落ち、すぐ横を、数頭の鹿が疾走したり、聞いたことの無い動物の声を聞いたり・・、半泣きで下山した記憶があります。
先日の反対かわ釈迦岳方面から奥駈をつなげましたね。僕は近畿の1500mの山では仏生嶽とバリコヤの頭を登っていません。一度行ってみたいと思っています、 楊子ノ宿非難小屋に一泊も良いのではと思っています
カモシカさん、こんにちは。
楊子ノ宿での宿泊でのプランはお勧めです。(孔雀岳の鳥の水、小屋下の湧き水あり?)水の確保は重要ですが、小屋は行者環小屋のの半分ぐらいのサイズで、残念ながらトイレはありませんでした。しっかり、キレイに保たれていました。
笹原の丘ですが、「楊子ノ森」からの日没と日の出が楽しめればと思います。
バリゴヤは私も興味アリです。まだ、興味の段階ですが・・。かなりの体力勝負のお山の印象ですが、。
カモシカさんご夫婦も「富士山」挑戦、お疲れ様でした。頂上が間近に見えていても、勇気ある撤退、正しい判断だと思われます。山は逃げません、風雨で形状が変わっても、あるがままが自然の姿です。次回への期待を抱いて、またのチャレンジを期待します!!!
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する