記録ID: 522333
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
甲信越
紅葉の八海山(日本二百名山) [屏風道・新開道周回]
2014年10月02日(木) [日帰り]

- GPS
- 06:18
- 距離
- 9.6km
- 登り
- 1,447m
- 下り
- 1,444m
コースタイム
登山口7:10⇒5合目8:07⇒八海山避難小屋9:54
[標準CT 5:00(55%)]
避難小屋10:04⇒大日岳10:47⇒入道岳11:10
[標準CT 1:40(64%)]
入道岳11:27⇒新開道分岐11:53⇒稲荷社12:51⇒登山口13:21
[標準CT 4:30(42%)]
※本日のペース:標準ガイドタイムの42~64%程度です。
他の山よりゆったり目な標準CTだと思います。
[標準CT 5:00(55%)]
避難小屋10:04⇒大日岳10:47⇒入道岳11:10
[標準CT 1:40(64%)]
入道岳11:27⇒新開道分岐11:53⇒稲荷社12:51⇒登山口13:21
[標準CT 4:30(42%)]
※本日のペース:標準ガイドタイムの42~64%程度です。
他の山よりゆったり目な標準CTだと思います。
| 天候 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2014年10月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
自家用車
駐車スペースは20台弱の広さです。 トイレはありません。 |
| コース状況/ 危険箇所等 |
★登山道整備度:3~4(良5・4・3・2・1悪)階段や木道、鎖等の整備度 ★体力難易度 :3.5(難5・4・3・2・1易)歩行距離、累積標高差、急登等 ★技術難易度 :5(難5・4・3・2・1易)鎖場、ヘツリ等の頻度や時間等 ★登山道の眺望:3~4(良5・4・3・2・1悪) ★山頂の眺望 :4.5(良5・4・3・2・1悪) 【すれ違った登山者の数:3人】 次第に秋が深まり、秋晴れの日が多くなってきました。 このような登山日和に限って、仕事や子供の行事等で忙しく、なかなか山に行けない日々が続いています。 本日の天気予報は、イマイチでしたが、仕事が一段落したので、「今日しかない」と思い、越後三山の1つ、日本二百名山の「八海山」に行くことにしました。 山頂へのルートは、ロープウェイを使ったり、色々ありますが、八海山は、鎖場の連続で有名ですので、今日は、鎖場を思いっきり満喫しようと思い、屏風道(下山禁止)で登り、八海山らしい大日岳、最高標高点の入道岳に行き、下りは新開道で周回するルートの登山です。 今日は、時間に余裕があるので、珍しくCTは設定せず、ゆったりと秋の気配を楽しみながら登ることとしました。 南魚沼市街から、まずは八海山ロープウェイ乗り場方面を目指して車を走らせます。 広堀川を渡り、八海山神社前を通り過ぎたら、すぐ、日本大学セミナーハウス方向へ右折します。 更にセミナーハウス前の交差点を右折し、やや幅の狭い舗装された道を5分ほど山奥に進むと、屏風道と新開道の登山口駐車場があります。 駐車場は、20台弱ほど駐車できるスペースがあり、朝7時の時点で、既に先発車が2台ほど停まっていました。 天気予報は今一つでしたが、絶好の秋晴れの中、準備を整え、いざ、出発です。 【登山口⇒(屏風道)⇒八海山避難小屋】 登山口から約2分で、最初の渡渉地点があります。 今も使用しているか分かりませんが、ゴンドラに「渡渉する」と記載があるので、沢に降りて渡渉します。 流量は少なく、大きな石もあるので、普通に渡ることができました。 渡渉後、しばらく緩やかな勾配のスギ林の中をどんどん進みます。 流水のある2箇所目の渡渉箇所を渡り、沢の左岸側をしばらく登ると八海山の急峻で迫力の山肌が近くに迫り、4合目に到着。 4合目は、水場への分岐点になっていますが、水は十分あるので、そのまま進んでいくと、ついに最初の鎖場が登場し、ここから鎖場が連続します。 鎖場は、4合目過ぎから9合目付近まで、20~30箇所程度あったと思います。 鎖場の大半は、補助的なものが多く、上りだけなら特に危険性を感じるような箇所はありませんでした。 高所が苦手で無ければ、足場を確認しながらゆっくり登れば、支障ない感じです(個人的な感想ですが、二百名山の荒沢岳の鎖場より難易度は低いと思います)。 鎖場以外も急登が多いですが、ルートは明瞭で、迷うような箇所もなく、整備されていますので、破線ルートでなく、実線ルートのような印象でした。 4合目以降の急登は、やはり体力の消耗が激しく感じました。 鎖が無い急登は、両手を使いながら登る箇所も多く、いつもより前傾姿勢のため、普段の登山以上に足が疲れ、「休憩無しでは登れないな」と思いながら、要所で一呼吸おき、息を整え、山々の写真を撮影します。 途中、7合目の「のぞきの松」に銅像がありますが、眼光が鋭く、睨まれているような感じを受けましたが、登山の安全を祈願し、先を進みました。 8合目付近から、秋の気配が色濃く感じるようになり、絶壁に映える木々が良い色に色づき始め、青空とのコントラストが印象深かったです。 また、標高が上がるにつれ、八海山の山頂付近の独特の巨岩の連続が近くに見えるようになってきました。 避難小屋に近づくと、登山道の刈り払いも良くされて登り易くなり、登山口から3時間弱で避難小屋に到着です。 【避難小屋⇒大日岳⇒入道岳】 避難小屋前の休憩スペースで、お菓子休憩をとり、次は大日岳を目指して出発です。 山頂に続く稜線からは、越後三山の越後駒ヶ岳、中ノ岳も見えるようになり、更にテンションが上がります。 大日岳を含む山頂の稜線は、6~7つほどの巨岩が連なり、その岩を鎖や梯子で上り下りしながら進むコースと迂回ルートに分岐します。 天候が悪かったり、強風時は、迂回ルートを進むように記載された注意看板がありますが、天候も良いので、鎖場に向います。 地蔵岳、不動岳、五大岳、白川岳、摩利支岳、大日岳と巨岩には名前がついており、それぞれ山頂標柱があります。 落差10~20m程度の鎖場や岩場のトラバースでしたが、巨岩に生い茂るナナカマド等の低木の紅葉も最高でしたので、次から次に現れる巨岩の連続は、結構楽しく感じました。 とは言え、鎖場の下りもありますので、注意しながら慎重に進みましょう。 ちなみに、難易度は、屏風道の鎖場よりやや上かなっと感じました。 最後の巨岩をよじ登ると、ようやく大日岳に到着です。 大日岳といっても他の巨岩と大差のない感じでしたので、そのまま、最高標高点の入道岳を目指します。 大日岳の鎖場を降りると、迂回路と合流し、普通の登山道になりますので、稜線を進み、迂回路分岐点から約20分で、入道岳に到着。 山頂から正面に見える中ノ岳を見ながら、昼食を食べ、下山することにしました。 【入道岳⇒(新開道)⇒登山口】 入道岳から再び、大日岳のすぐ下にある迂回路分岐まで戻り、下山開始です。 迂回路といっても梯子が連続するルートを5分ほど進むと、新開道への分岐点があるので、見落とさないように注意しましょう。 新開道に入り、約20分間は、鎖場や岩場のトラバースが多くなります。 岩場のトラバースは、鎖が無い箇所もあるので、滑りやすい箇所は、注意しながら進みましょう。 岩場の急登を降りて山頂方面を振り返ると、大日岳等の山頂稜線の巨岩の頂きが良く見えるようになります。 ここからは、尾根に沿って、普通の登山道を下ります。 しばらくは礫質土の登山道になり、標高が低くなるとブナ林になり、登山道も粘質土に変わります。 どちらも若干滑りやすいので、慎重に進みます。 また、陽当たりの良い箇所は、笹等が生い茂り登山道を少し塞ぐような箇所もあり、私的な感想ですが、新開道より屏風道の方が整備されているような感じを受けました。 途中、左手の生い茂る山中で、「ガザガザ」と物音が。。 茂みの中で姿は確認できませんが、大型の獣と思われる動物が、遠くに離れていく物音を感じました。 「ん~、なんだろう??」、根拠はありませんが、以前カモシカに遭遇した時に感じた気配と似た感じがしたので、「熊ではない」と勝手に自分に言い聞かせ、その場は、やや早足で下山し、入道岳から約2時間で、無事、登山口に到着です。 本日の「八海山」、山頂付近は紅葉が見頃で、岩肌に映える鮮やかな葉の色調は、とても見応えがあり素晴らしく感じました。 累積標高は1400m弱でしたが、鎖場のアップダウンは、数値以上に体力を消耗し、久しぶりに手もかなり使いましたので、全身は程良い疲労感で、ビールが美味そうな感じです。 入道岳から良く見えた、八海山から中ノ岳縦走ルート、面白そうなルートに見えたので、来年は、越後三山の縦走でも計画してみようと思います。 |
写真
4合目を過ぎると鎖場が登場です。
避難小屋まで、恐らく20~30箇所の鎖場がありますが、思った以上に怖い箇所はありませんでした(高所が苦手な方は厳しいでしょうが)。
全体の9割は、補助的な鎖です。
滑り易い箇所は、足場を確認しながら慎重に登れば、特に支障ない感じです。
避難小屋まで、恐らく20~30箇所の鎖場がありますが、思った以上に怖い箇所はありませんでした(高所が苦手な方は厳しいでしょうが)。
全体の9割は、補助的な鎖です。
滑り易い箇所は、足場を確認しながら慎重に登れば、特に支障ない感じです。
撮影機器:

 Joker
Joker













 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手













































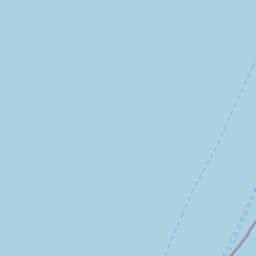












自分はJoker72さん程たくさん登れていませんが、行ったことのある山のタイムが割りに近いので、これから行きたいコースの目安にさせて頂いてます~
ありがとうございますm(__)m
コメント頂き、ありがとうございます。
単独や少人数の登山は、CTもほぼ一定かと思いますが、複数人の山行記録は、ゆっくり登ったりすることもあるので、CTにバラつきがありますので、ご了承くださいね。
当面は、新潟の地元の山ばかりですが、参考にして頂ければ嬉しいです
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する