トヨニ岳~ピリカヌプリ/野塚岳~オムシャヌプリ~十勝岳~楽古岳

- GPS
- 80:00
- 距離
- 40.4km
- 登り
- 3,745m
- 下り
- 3,861m
コースタイム
- 山行
- 4:15
- 休憩
- 0:00
- 合計
- 4:15
- 山行
- 9:15
- 休憩
- 2:05
- 合計
- 11:20
| 天候 | とにかく天候に恵まれました! これが全てでしょう。 4/29(水) 快晴 4/30(木) 快晴、午後から強風 5/1(金) 薄曇り、強風 5/2(土) 快晴 |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2015年04月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
| コース状況/ 危険箇所等 |
とにかく天気が良かったため、自分としては出来すぎの縦走でした。ここ最近の猛暑で稜線は融雪進んで藪がひどかった。行程は思ったよりはかどらなかったが、その分危険は少なかったのではないかと思う。 ・トンネル北の駐車場横の渡渉ポイントにはスノーブリッジあり。ただし今にも落ちそうだった。 ・トンネル北の駐車場からは尾根に取りつこうとしたが、完全に溶けており、すぐそばの沢を登った。雪崩が怖いのでいつ尾根に逃げようかと思いつつ、機会を逸して終始沢沿いで稜線まで出てしまった。トレースもずっと沢沿いについていた。 ・トヨニ岳南峰直下にある噂のナイフリッジは残雪なし。稜線上を行けた。全く問題なしだったが、帰りは強風で怖かった。 ・トヨニ北峰からピリカヌプリまでは難所なし。最終鞍部からピリカ山頂までは藪だが、探せば獣道があるのでそれほど苦はなく登れた。 ・駐車場への下降点から野塚岳西峰へは問題個所はないと思っていたが、シビアな岩峰を3つほど連続して通過する。ここは十分注意したい。2つは北面の残雪をトラバースできたが3つ目は厳しく稜線の藪をこいだ。風が強く滑落しないよう十分注意を払った。 ・野塚岳西峰~東峰の鞍部は南側が崖で危険と聞いていたが、全く問題なかった。 ・野塚岳東峰から南への下りは稜線は全く残雪がついておらず、かつ岩場がすごいのでいやらしく難しい箇所だ。基本的に雪のついた南東面を巻きながら下るが、斜度が尋常でないので滑落には十分注意のこと。 ・オムシャ前後は藪がひどい。特にオムシャ東峰は獣道もあまり見つけられず、ハイ松漕ぎになった。危険はあまりないが、出来高が上がらずやきもきした。 ・十勝岳の登りは部分的に雪が切れるが、短いところは巻かずに藪を突破した。また、山頂は残雪はほとんどないため藪漕ぎになるが、獣道がしっかりしていて思いのほかスムーズだった。 ・十勝から楽古は雪がよくついており、快適な区間だった。ただし楽古の肩の直下で距離は短いがハードな藪漕ぎになった。 ・楽古の山頂直下の雪渓は非常に急なので滑落要注意。落ちると止まらなさそう。 ・十勝岳西尾根は残雪量豊富で7割の区間は快適だが、最上部と最下部でハードな藪漕ぎを強いられた(上部はハイ松、下部はネマガリ)。全工程でここの藪が一番ひどかったが下りなのが幸いした。この時期は西尾根は登りではとても使えないだろう。 |
| その他周辺情報 | 忠類ナウマン温泉500円。レストラン有。 |
写真
感想
4/29(水) 快晴
野塚トンネル北~稜線~トヨニ岳南峰△
朝一の飛行機で帯広入りし、レンタカーで野塚トンネルについた。途中ガス缶や食料を買ったので遅くなり、出発したのは正午過ぎになってしまった。目の前の豊似川ポン三の沢支流は雪解けで濁流となっており渡渉は厳しい。一応スノーブリッジがかかっており、なんとか渡れたがあと1週間以内に落ちるであろう。さらに問題はその次で、1151ピークから派生する尾根にとりつこうとするものの、完全にヤブが露出しておりどう頑張っても無理である。トレースは雪で埋もれた横の沢の中に続いており、自分もそれに倣って登ってゆく。人が降りてきたので状況を聞いてみたが、しゃべることのできない方だった。身振り手振りで会話するが、何とかなるもので、トヨニ岳まで状況は比較的安全だとわかった。しかしすごい方がいるものだ。沢は標高780mあたりで二手に分かれるが、右を行く。右に入ってすぐのところで湧水があふれていたので水筒3.5Lを満タンにする。もちろんエキノコックスフリーだ。これは大事な飲み水になる。雪崩が怖いので尾根にとりつこうとタイミングをうかがっていたが、上から2人の女性が降りてきた。このまま沢伝いで上まで行けるという。風も弱く絶景とのこと。
確かに雪崩の危険もなく、いとも簡単に稜線に出てしまった。ここまで標高差500mで初日の重い荷物でもわずか1時間45分。日高の稜線に出るにはあまりにもお手軽なルートで、これだもこの時期皆こぞって登るわけである。トヨニ岳の南面が大迫力で切れ落ちており、思わず歓声を上げた。トヨニ岳南峰へはさらに400m標高を上げる必要がある。稜線は急峻なので雪がかなり解けており、ヤブ漕ぎもあった。南峰手前には日高側・十勝側両方が切れ落ちている難所があるが、ここは雪が全くついていないため稜線上を行けて安全だった。息も絶え絶えで南峰に到着。思ったより時間がかかり16時を過ぎた。事前調査通り南峰を超えてすぐのところに幕営適地があった。おまけに幸運なことに前の人が作った大がかりな雪囲いもあったのでこれを利用されてもらう。おかげで設営時間を短縮できて助かった。
幕営地からは明日登るピリカヌプリが遠くに見えた。あまりに遠く、本当に明日あそこまで行けるのか不安になる。おまけにヤブがかなり出ており南稜が真っ黒く見える。ヤブ漕ぎで猛烈に時間がかかってしまうのではなきあろうか。色々不安は募るが、昨日は睡眠時間2時間半だったので、眠くてかなわない。この日はご飯を食べたらそのままバタンキューだった。
ーーー
4/30(木) 快晴
トヨニ岳南峰~北峰~ピリカヌプリ~トヨニ岳北峰~南峰~駐車場下降点~野塚岳西峰△
朝3時半、そろそろ起きようかと思っていたところ、突然鈴の音が聞こえた。明かりをつけてテントから顔を出してみると、男性が立っていた。「すみません、起こしてしまいましたか」「いえ、今起きようと思っていたので大丈夫です」Ei-taroさんという単独行の方だった。0時から登り始め、日帰りでピリカを往復するという。日帰りという発想はなかったのでびっくりである。
Ei-taroさんより1時間ほど遅れて出発する。4時半を過ぎるともう明るくヘッドライトはいらない。トヨニ北峰にはすぐに到着。両翼を広げたような颯爽とした三角形のピリカヌプリが素晴らしい。ここからは実に快適な雪面が続き、アップダウンも少なく快適である。それにしてもトヨニ岳の北面の雪のヒダはなんて綺麗なのか、、、芸術品のようである。
ピリカが近づくといったん1330m鞍部まで下降し、最後の急坂に差し掛かる。鞍部から山頂まで半分はヤブだが、獣道らしきものがあるので意外と楽だった。ただ、尋常でなく急なので要注意である。ピリカの山頂部はいつの間にか鋭角に尖り、孤高の山のごとく天を突きさしている。思ったより早く山頂にたどり着いた。北側の展望が一気に広がり、神威、ソエマツ、ペテガリ、1839などははっきりわかり、はるか遠くにカムエクと思われる三角形も識別できた。Ei-taroさんと写真を撮りあって登頂を喜び合った。Ei-taroさんは子供のころ様似に在住していたこともあるとのこと。私は静内在住経験があるので実は昔はご近所同士だったことも判明した。世の中狭い。今日は最高の登山日和だったとお互い喜び合った。
山頂をあとにしてしばらく行くと3人さんパーティと遭遇。彼らも日帰りだった。ピリカヌプリは今は日帰りが普通なのだろうか?みなさん凄すぎる。トヨニ岳まで戻り、昼飯のラーメンを食ってから片づけをして出発する。いつの間にか風が強くなり、南峰の下のナイフリッジは吹き飛ばされないよう注意深く進まねばならなかった。1251ピーク手前の鞍部ではあまりの強風に体が吹き飛ばされ、転がってしまった。幸い怪我はなかった。なんとかかんとか安全なところまでたどり着き、ほっと溜息をついた。
駐車場への下降点を過ぎるとまた新たな道である。できれば野塚岳までと先を急ぐが、西峰の手前に厄介な岩峰が3つ連続で続いた。2つは雪面のトラバースで通過できたが最後のひとつは稜線のヤブを漕いだ。この区間は簡単に歩けると予想していたが、思ったより大変だった。野塚岳西峰のピーク直下でちょうど16時。なだらかな斜面で、これ以上進むとよい幕営地はなさそうだ。ここにテントを張ることにした。風が強いのでかなり深い竪穴を掘り風よけにし、なんとか快適な寝場所が出来上がった。日高の稜線は風の影響が強いので、基本竪穴を掘らないと安全には寝られそうにない。テント設営に40分くらいもかかってしまうが致し方ないだろう。
この場所は地図で見ると野塚トンネルのちょうど真上だった。地面の下から車の音が聞こえないか耳を澄ませてみたが聞こえるはずもない(笑)。野塚岳の北は残雪が豊富だ。西峰東峰の鞍部から駐車場へ至る沢が見えたが、いい具合に雪がつながっており安全に降りられそうだ。帰りはここを下ることになるのか、それとも十勝岳からエスケープするのかまだわからないが、一応の可能性として頭にとどめておく。この夜は終始強風が吹き荒れ、テントのバタバタ音に時折起こされながら寝ることとなった。
ーーー
5/1(金) 薄曇り
野塚岳西峰~野塚岳東峰~オムシャヌプリ~十勝岳△
今日は晴れの予報だが実際は昼過ぎまで太陽が少し見えるくらいの薄曇りだった。風も非常に強く寒い。ブツブツ文句を言いながらテントをたたむが、昨日までがあまりにもいい天気過ぎたので感覚がマヒしている。今日も進むには全く問題ない天気なのに。
野塚岳西峰をヤブを漕ぎながら越え、鞍部へと下る。鞍部の北斜面はスキーにうってつけの真っ白な広い斜面だ。南側は大きくガレているが、危険ではなかった。本峰である野塚岳東峰に到着。道の無い山のはずだが山頂には看板がある。野塚トンネルから登る人があまりにも多いため、踏み跡ができて無雪期でも登れるようになってしまったそうだ。風が激烈に強いので休憩も早々にオムシャへと下ってゆく。遠くから見て南尾根には全く雪がついていないように見えたが、実際その通りでおまけに岩峰が林立するとても悪い尾根だ。しかし南東斜面には雪が割とついていて、おまけにトレースまであった。トンネル北からオムシャを往復する人は割と多いのだろうか? ありがたくこのトレースを利用させてもらうが、斜度がかなり急なので滑落しないように十分注意をした。鞍部まで下ると雪はなくなるがヤブは低く獣道もあったので快適に進むことができた。
オムシャヌプリは今回の縦走でヤブで一番苦労した区間だった。遠くから見ても残雪量が明らかに少なく、苦労することはあらかじめ覚悟していた。まずは本峰である西峰から攻めるが、頂上直下で残雪がなくなり、背の高いハイ松に阻まれる。ここは北東面を巻いて切り抜けたが、ダケカンバのヤブがひどく、ザックやらアイゼンやら何やらが引っかかりまくって気が狂いそうになった。オムシャ西峰・東峰の鞍部に着き一息。十勝岳の西尾根がここで正面に初めて拝めたが、予想に反して残雪量がとても多い。この時点で野塚岳まで戻らず西尾根を下ろうと決意。トンネル越えのヒッチハイクが必要になるが、帰りにまたこのヤブを漕ぐよりずっとマシだ。
東峰のヤブはさらにひどかった。ここは適当な逃げ道が全くなく、稜線上を行くしかなかった。出来高が上がらないストレスの中、黙々と進むしかない。北側を乗越して、ようやく南の十勝岳が見えてやれやれと思ったら、オムシャの南にある1341ピークも雪がついておらず、ヤブ漕ぎが続くこととなった。なんとか十勝岳との鞍部に降り立った時はヘロヘロになっていた。
十勝岳の登りは頂上直下までは順調に雪の上を歩けた。遠くから見て山頂部のハイ松のヤブが黒々としていたので果たして上まで行けるのか心配だった。実際ヤブに突入してみるとすぐに山頂からの薄い踏み跡にぶち当たった。下道があればこっちのものである。意外と時間がかからずに山頂まで到達できた。十勝岳はとても展望の良いピークだ。まずは楽古の大きな姿に目を奪われた。オムシャの双耳峰と野塚の双耳峰は形がとても良く似ている。遠くトヨニ岳とピリカヌプリも小さく見えた。あんなところから歩いてきたのだ。南西のほうを見ると、様似町のアポイのピークもずいぶん近くにあることがわかる。南日高からの展望はなかなかチャンスがないので、この展望に興奮しきりだった。
山頂から少し下った南側の雪庇上にテントを張った。テラス状になっており南に雄大な楽古が望める絶好のポイント。今日は時間があれば楽古を往復しようと思っていたが天気もいまいちだし予想外のヤブに疲れも溜まっていたので、まだ昼だが行動を打ち切ることにした。テントの中から、正面に大きく見える楽古が暮れてゆく様子を見るのは至福の時だった。夕方になると上空の薄い雲も取れて風も弱まり、快晴の空気の中太陽が沈んでいった。やがて広尾の街や十勝港の明かりもつき出した。南にやってきて太平洋が間近になった。明日の天気は確実に良いだろう。早起きして願わくば堅雪の上をルンルンで楽古まで往復してしまおう。
ところが、夜中の11時ころ、ぞっとするような出来事があった。テントにドンとショックがあって、そのあとカランカランと甲高い音が聞こえた。風でテントが揺れ、スコップが倒れたのだろうと思って初めは気にも留めなかったが、少し気になるのでテントから首を出して外を確認してみた。特に異常はなく、寝に戻ろうとしたところで3mくらい離れたところに月明かり下に丸いものがあるのが見えた。取りに行ってみるとなんと自分のヘルメット!! もともとヘルメットは50㎝以上は掘った竪穴の中に置いてあり、さらにテントのフライシートの中に入れておいた。風では絶対外に出るはずがない。いったい何が起こったのだろう? 怪奇現象に呆然とし、気になってそのあとしばらく寝付けなかった。
ーーー
5/2(土) 快晴
十勝岳~楽古岳~十勝岳~翠明橋公園(野塚トンネル南)[下山]
朝3時に起床。昨晩の出来事を思い返してみて、多分動物の仕業だろうと思い至った。北海道の山ではキツネが悪さをするケースがとても多い。靴をくわえて持って行かれたり、食べ物を荒らされたり。しかし動物とはいえ本当にキツネだったのだろうか? まさか熊じゃ… 考えても仕方ないが。
4:10分、テントの食料は厳重に封をして簡単に開けられないようにしたあと、気を取り直し出発した。今日はかなり冷え込んでアイゼンがよく効いて歩きやすい。おまけにここから楽古まではほとんど雪が繋がっているように見える。駆け降りるように最低鞍部へ下って行った。十勝と楽古の最低鞍部は標高約1070mで、今回の稜線歩きでは一番低い。さらに楽古岳は1472mなので400mも登らねばならない。朝の元気のあるうちとはいえ、辛い登りになった。途中の1281ピークを超えてもまだ小ピークが続く。なんとか頑張って肩の手前まで登ると今度は雪がなくなりヤブ漕ぎだ。ここは区間は短いがなかなかつらかった。肩まで登ると札楽古川からの夏道と合流する。もう頂上までわずかだが、最後の最後は急な雪面の登りになり緊張した。そしてようやく楽古の山頂に登りついた。この縦走の目的のピークすべてに無事登り終えたのである。思わず万歳をして喜んだ。
天気も展望もすべて最高である。昨晩泊まった十勝岳が良い形で目の前にある。オムシャ、野塚、トヨニ、ピリカと登ったピークもすべて見えている。南方面はわからないピークだらけだが、東に少しずれた大きな山はおそらく広尾岳だろう。楽古岳から広尾岳への縦走もこの時期は可能との記録をどこかで読んだ記憶がある。見ると雪はしっかり付いており、確かに可能そうに思えた。実は楽古岳は学生時代の1997年秋に浦河側から登っており、18年ぶりの再訪なのだが、前回はガスで何も展望がなかった。今回最高の形でリベンジを果たせたのである。そして楽古は母の故郷の山でもあり、私のルーツの半分なのだ。山頂には目新しい看板が立っていたが、昔の朽ち果てた看板(木でできたとてもユニークなもの)も置かれてあり、懐かしく眺めた。
帰りの十勝岳の登りはつらいものとなった。最低鞍部からはこれでもかという急坂が続き、雪も腐ってきたのでなかなか体が上がらない。往きよりも少し時間がかかってなんとか十勝岳に戻った。テントが動物に襲われていないかがとても心配だったが、これも大丈夫だった。重責を果たして爽快な気分で昼飯にした。ラーメンを作り、お茶をたっぷり入れ、残飯整理に徹した。
さて、下山は十勝岳西尾根である。本当は野塚まで戻る予定だったが、もはやあのヤブを再び戻る根気はない。しかし西尾根は事前調査では5月に使ったという記録はほとんどなかった。上部は残雪豊富だが、下部はおそらく相当ひどいヤブだろう。これは今回の縦走ではかなりの不確定なところであり、これは自分なりのチャレンジである。十勝岳山頂からはまずハイ松漕ぎから始まる。わずか15分だがこれもとてもハードだった。登りだったら敬遠したいところだ。しかし西尾根の残雪に降り立つとスキー場のような快適な広い斜面が続き、あれよあれよという間に標高が下がっていった。西尾根は実に7割くらいが快適な区間だった。支尾根なのにこの豊富な雪には全く驚きだった。しかしさすがに標高900mを切ると笹薮と残雪のミックスになり、徐々に面倒くさくなってきた。天馬街道も真下に見え、いよいよ下山だと気持ちははやるが、逆にヤブはどんどんひどくなる。稜線上にはかすかな踏み跡もあったが、ネマガリと格闘するうちそれも見失い、復帰するのも面倒なのでヤケクソで強引突破する。最後は背丈以上の笹の急斜面を足で歩いているのか滑って転んで落ちているのかわからなくなりながら下り、突然すとんと林道に降り立った。どうやら少し西にずれてしまったようだが、なんとか下山できてよかった。十勝岳西尾根はやはり4月上旬までしか使えないヤブ尾根ということなのだろう。登山ポストもあったのだが、これは冬に登る人のためのものなのだろうか?
何はともあれ無事に下山できてよかった。あとはトンネルの向こうまでヒッチハイクできるかどうかが最大の問題だ。天馬街道を渡って翠明橋公園に行くと、公園はまだ冬季閉鎖中だった。しかし路肩に1台の車が駐車していた。チラ見で帯広ナンバーと確認。これは脈ありとばかり乗っているご夫婦に声をかけてみると、快くOKしてくれた。なんとありがたい。帯広在住の方で浦河の優駿牧場に遊びに行った後、帰る途中とのことだった。翠明橋公園で湧水を汲もうとしたが、冬季閉鎖中のため入れず、仕方なく休憩していたところだったとのこと。ほんとにラッキーだった。
トンネル北の駐車場で下してもらい感謝に感謝、そのあと忠類のナウマン温泉で4日間の汗を流した。温泉の駐車場で高校時代の友人にばったり遭遇するといううれしいハプニングもあり、今回の日高縦走も大満足のうちに終わった。
<後日談>
縦走を終えて3日後の早朝、札幌の実家で尿管結石になり、激痛のあまり救急車で搬送されるというとんでもない出来事がありました。思い返すと連日カラカラに乾燥した空気の中、十分水分を取っていたつもりですが、実際は不足していたのかもしれません。登山中の水分補給は基本中の基本ですが、長い縦走中はおろそかになりがち。今後は十分注意しようと反省しています。それにしても山の中で発症していたらと思うとぞっとします。単独行のリスクも考えてゆかねばなりません。
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 triglav
triglav













 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手






































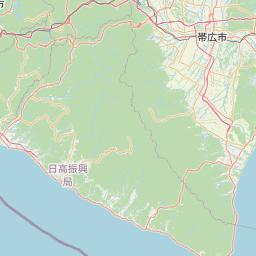
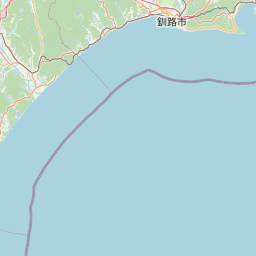

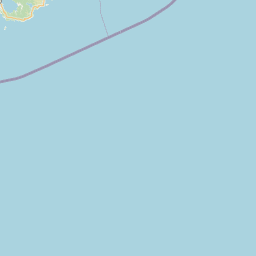



















junjapaです。またまた素晴らしい連休の山を過ごしましたね。日高はワタシの憧れの山です。でもちょっと怖いですね。痩せた尾根だとか、ヤブこぎだとか。尿管結石も3日後で良かったです。お大事に!
junjapaさま
無事に帰れてホッとしています。尿管結石は下山後で本当にラッキーでした。単独行のリスクを見直さねばなりませんね。詳細はまた飲み会でも。
激痛に救急車を呼んでしまったのですね
尿管結石と分かれば、救急病院では冷たくあしらわれます。
尿管結石で死ぬことは無いから、全然救急では無いのです(医師免許保持者)、タクシー代わり、歩いて行きなさい!
厳しい言葉の様ですが、水を飲みながら歩けば尿管結石は落下します
今年の厳冬期に、日帰りでトヨニ、野塚、オムシャ、十勝岳に。
この時期は、藪漕ぎが大変ですね。
テント泊は、日高山脈の自然に対して負荷が大きいですよ。
そこにテントを張っても良いとは誰も思っていません。
自分勝手なレコ、救急車並ですね。
自然冒涜、迷惑千万。Ei_taroさんの様に日帰りで行きなさい!!!
murakami2231さま
メッセージありがとうございます。
私は尿管結石は初めてでして、あまりの痛みに最初は原因が全く分かりませんでした。のたうち回っている状態で両親も深刻な状態かと思い、救急車を呼ぶことになりました。実際はこの程度で呼んではいけないとのこと、お恥ずかしい限りです。今投薬治療中ですが、治ったら生活面では十分注意したいと思います。
murakami2231さんは日高が大好きなのですね。私も日高の元で育ち、日高も大好きですので、今回の縦走が自然への冒涜といわれると悲しくなります。テント泊についてですが、残雪上での幕営は無雪期よりも自然への負荷は少ないのではないでしょうか。土や樹木にはほとんどダメージは与えませんし、雪は溶けてなくなります。これが日本アルプスのような一日に何百人と入山するような山なら別でしょうが、山の厳しさが防御になっている日高でインパクトがある自然破壊になっているとは正直あまり思えません。夏のカムエクとかは結構な人数が入るとは聞いていますが。
また、エキスパートの皆様のように日高を歩けるならともかく、今住んでいる内地から日高に行くにあたり、テントを持たず日帰り12時間以上をこなすというのは正直リスク面で不安があります。疲労や軽いアクシデントで宿泊せねばならないケースも想定できます。なので日帰りは選択肢としてまず思いつきませんでした。それが甘いと言われるとそれまでですけど…
私は今の入山人数を維持しつつ(つまり他の日本の山のように余計な手入れはせず厳しさは維持したまま)、色々な方にテント泊で長い縦走をして日高を楽しんでほしいと思っています。それが日高の貴重な自然を守ろうという動きにもつながっていくのではないかと個人的には思っています。
私の個人的な意見ですので、いろいろ間違っているかもしれません。ご指摘頂けるとありがたいです。
発想力、足元にも及びません☆
ピリカにて、大きな展望を共有でき嬉しい時間でした(^-^)
朝早い時間、テントに灯りも見えましたので、熊と紛らわしいよりはと、お声掛けさせて頂きました(^^
そしてまた凄まじい山行歴!
経験豊富な方とお喋りでき、一言ひとことに重みを感じました。
日高稜線での贅沢な時間、羨ましい限りです。
Ei-taroさま
ピリカヌプリではお話できて楽しかったです。次の日以降、誰にも会いませんでしたのでこちらもあのあとはとても心細かったです。Ei-taro さんも日帰りで1839や神威などいろいろ登られているとお聞きしました。日高に関しては私の先生ですね。ピリカ日帰りは本当に驚きました。
今回は贅沢にテントで楽しみましたが、南日高の様子もわかりましたので、機会を見つけて神威とかソエマツとか登ってない山にまた出かけたいです。ただ当面の夢はエサオマン~コイカクの夏の縦走です。いつか実現できるといいのですが。
murakami2231さんの意見は意見ですが、素人で尿管結石で痛ければ救急車を呼ぶのもやむを得ないと思いますよ。それと「タクシー代わり」とは、同列には論じられないでしょう。多少、指摘が極端に寄っていると感じます。
それと同様、山の登り方も千差万別、ゆっくり登る、走って登る、写真のために登る、慰霊のために登る、いろいろな楽しみ方があってこそが山登りだと思います。雪の上での幕営ではインパクトもないでしょうし、たとえインパクトがあっても些少でしょう。それを「日帰りで登れ」とはやはり極端な意見と理解します。日帰りで登ることでの「安全面の配慮」もどこかへ行ってしまっています。富士山などでも徹夜での日帰り登山は戒められています。
それにしてもmurakami2231さんは今日は名前が消えてゲストになっちゃってますね。どこかへ行ってしまったですね。
junjapaさま
ありがとうございます。同意していただける方がおられてありがたいです。山登りは色々な楽しみ方があってよいというのは激しく賛同です。
確かに極端なご指摘だったかもしれませんが、murakami2231さんも相当なエキスパートとお見受けしていたので、いろいろご意見を聞きたかったのが少し残念です。。
triglavさん初めまして。
縦走楽しかったでしょう~。そして遠くから来られてお疲れ様でした!
故郷で美味しいものイッパイ食べて帰れましたか~?
murakami2231さんのコメ
一瞬、私へのコメと間違ったのかな?って思いましたよ(笑
今までの子供とのレコを捨ててしまうほど
コメントに責任を感じてしまったのでしょうね...
まったくもー 帰って来て欲しいですね
syunpaさま
コメントありがとうございます。
とても楽しい縦走でした。内地からわざわざ行った甲斐がありました。
日高は大好きでいつも行く機会を狙っているのですが、なかなか遠くて。
また機会があればお邪魔したいと思います。
triglavさん、その時は
イッパーイお話ししながら日高の山を歩きましょう。
自然に抱かれながら そして守りながら
これからも楽しい山を歩いて下さいね!
私は初心にて再出発。 自然を思う風を感じて行きましょー
這松漕ぎにネマガリ竹。。。
想像しただけでも筋肉痛になりそうです(笑
過酷な行程でしたね。
しかし、苦労しても歩きたい、素晴らしい山ですね。
triglavさんの山は渋いです。
また、夢が増えました。
kiha58さん
いやいやkiha58さんも十分渋いですよ。残雪期の山に4泊も5泊もするなんて並大抵ではできないです。
私が南日高に入る前の週には帯広で30℃越えました。それを引きずっていてずっと暑かったです。とはいっても山の上は朝晩寒くて氷点下のことが多かったですが。
南日高はご覧のように5月はちょっと時期遅めです。登るのであれば4月中旬までがいいと思います。
天馬街道が出来たおかげで日高にあるまじきアプローチの短さです。いざとなればすぐに降りられるという心の安心も日高の他の山域では得られないものです。ここら辺の山は春の時期限定の楽しみです。
私も夏の日高をまた狙いたいのですが、今年は果たして行けるかな~
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する