 <谷村町駅>
<谷村町駅>
レトロ風駅舎の谷村町駅より行動開始。下りたのは自分ともう一人だけ。
 1
1
1/26 7:30
<谷村町駅>
レトロ風駅舎の谷村町駅より行動開始。下りたのは自分ともう一人だけ。
 駅から既に富士山がちらり。
駅から既に富士山がちらり。
 1
1
1/26 7:30
駅から既に富士山がちらり。
 都留アルプスの案内板。今回歩くのは一番左の古城山だけ。
都留アルプスの案内板。今回歩くのは一番左の古城山だけ。
 1
1
1/26 7:30
都留アルプスの案内板。今回歩くのは一番左の古城山だけ。
 <龍石寺>
<龍石寺>
ほぼ駅直結という風変わりな立地にあるお寺。都留市の役所も都留市駅ではなく谷村町駅が最寄り。
 1
1
1/26 7:31
<龍石寺>
ほぼ駅直結という風変わりな立地にあるお寺。都留市の役所も都留市駅ではなく谷村町駅が最寄り。
 境内には石仏・祠が整然と並ぶ。
境内には石仏・祠が整然と並ぶ。
 1
1
1/26 7:31
境内には石仏・祠が整然と並ぶ。
 都留アルプスには向かわず車道を歩いて西へ。
都留アルプスには向かわず車道を歩いて西へ。
 1
1
1/26 7:37
都留アルプスには向かわず車道を歩いて西へ。
 三ツ峠も良く見える。今日の山行が不安で何度あちらに予定変更しようと思った事か。
三ツ峠も良く見える。今日の山行が不安で何度あちらに予定変更しようと思った事か。
 1
1
1/26 7:44
三ツ峠も良く見える。今日の山行が不安で何度あちらに予定変更しようと思った事か。
 <田原神社>
<田原神社>
国道と桂川の交差する佐伯橋手前に鎮座する。こぢんまりとしているが起源は平安時代と古い。鬼瓦の桜の紋様や独特な書体の扁額が目を引く。富士に近いだけあってコノハナサクヤヒメや浅間大神を祀っているらしい。
 1
1
1/26 7:47
<田原神社>
国道と桂川の交差する佐伯橋手前に鎮座する。こぢんまりとしているが起源は平安時代と古い。鬼瓦の桜の紋様や独特な書体の扁額が目を引く。富士に近いだけあってコノハナサクヤヒメや浅間大神を祀っているらしい。
 神社裏手は芭蕉ゆかりの地で句碑も建つちょっとした公園になっていた。「勢いあり 氷消えては 瀧津魚」
神社裏手は芭蕉ゆかりの地で句碑も建つちょっとした公園になっていた。「勢いあり 氷消えては 瀧津魚」
 1
1
1/26 7:48
神社裏手は芭蕉ゆかりの地で句碑も建つちょっとした公園になっていた。「勢いあり 氷消えては 瀧津魚」
 <田原の滝>
<田原の滝>
佐伯橋手前で折れると突如響く水の音。流量もさることながら奥行きのある段瀑が現れる。
 1
1
1/26 7:49
<田原の滝>
佐伯橋手前で折れると突如響く水の音。流量もさることながら奥行きのある段瀑が現れる。
 周囲の木は水飛沫で霧氷に。
周囲の木は水飛沫で霧氷に。
 1
1
1/26 7:51
周囲の木は水飛沫で霧氷に。
 駐車場のある上流側まで寄ると轟音とともに引き込まれそうな迫力を感じることができる。脇の岩壁は柱状節理。何より住宅地の真裏にこんな光景が広がるというのが面白い。
駐車場のある上流側まで寄ると轟音とともに引き込まれそうな迫力を感じることができる。脇の岩壁は柱状節理。何より住宅地の真裏にこんな光景が広がるというのが面白い。
 1
1
1/26 7:52
駐車場のある上流側まで寄ると轟音とともに引き込まれそうな迫力を感じることができる。脇の岩壁は柱状節理。何より住宅地の真裏にこんな光景が広がるというのが面白い。
 佐伯橋よりもう一枚。
佐伯橋よりもう一枚。
 1
1
1/26 7:55
佐伯橋よりもう一枚。
 <十日市場駅>
<十日市場駅>
田原の滝のすぐ上流にある小ぢんまりとした駅。駅ホームから滝は見えるのかな。
 1
1
1/26 7:59
<十日市場駅>
田原の滝のすぐ上流にある小ぢんまりとした駅。駅ホームから滝は見えるのかな。
 駅のすぐ西側に色褪せた鳥居。奥には覆屋のような建物が見える。さすがに渡るわけにもいかないけど近くに有効な踏切なんてあるのだろうか。
駅のすぐ西側に色褪せた鳥居。奥には覆屋のような建物が見える。さすがに渡るわけにもいかないけど近くに有効な踏切なんてあるのだろうか。
 1
1
1/26 8:00
駅のすぐ西側に色褪せた鳥居。奥には覆屋のような建物が見える。さすがに渡るわけにもいかないけど近くに有効な踏切なんてあるのだろうか。
 線路沿いに西へ移動するとこれと思われるような簡易踏切があった。
線路沿いに西へ移動するとこれと思われるような簡易踏切があった。
 1
1
1/26 8:01
線路沿いに西へ移動するとこれと思われるような簡易踏切があった。
 線路は越えて桂川を見下ろす。
線路は越えて桂川を見下ろす。
 1
1
1/26 8:02
線路は越えて桂川を見下ろす。
 どうも先程見えた社殿に参拝するには線路脇を歩いて行かなければいけない様子。思案していたらほとんど無音で上り電車が通過していき肝を冷やした。何となく見咎められそうな気がして参拝はやめておいた。
どうも先程見えた社殿に参拝するには線路脇を歩いて行かなければいけない様子。思案していたらほとんど無音で上り電車が通過していき肝を冷やした。何となく見咎められそうな気がして参拝はやめておいた。
 1
1
1/26 8:02
どうも先程見えた社殿に参拝するには線路脇を歩いて行かなければいけない様子。思案していたらほとんど無音で上り電車が通過していき肝を冷やした。何となく見咎められそうな気がして参拝はやめておいた。
 気を取り直して国道へ合流し、北向かいの小丘に鎮座する小篠神社へ。
気を取り直して国道へ合流し、北向かいの小丘に鎮座する小篠神社へ。
 1
1
1/26 8:04
気を取り直して国道へ合流し、北向かいの小丘に鎮座する小篠神社へ。
 <小篠神社>
<小篠神社>
スサノオを祀る旧村社。都留市のマスコットキャラクターにもなったムササビが棲んでいたそう。屋根棟にある卍紋が珍しいというが、本殿側で左右に張り出した社殿の構造もそう多くはない。
 1
1
1/26 8:04
<小篠神社>
スサノオを祀る旧村社。都留市のマスコットキャラクターにもなったムササビが棲んでいたそう。屋根棟にある卍紋が珍しいというが、本殿側で左右に張り出した社殿の構造もそう多くはない。
 奥宮という位置付けだろうか、本殿のさらに先にも社殿が設けてあった。
奥宮という位置付けだろうか、本殿のさらに先にも社殿が設けてあった。
 1
1
1/26 8:05
奥宮という位置付けだろうか、本殿のさらに先にも社殿が設けてあった。
 もう一度富士急行線を跨いで山側へ。踏切名は「山梨踏切」。
もう一度富士急行線を跨いで山側へ。踏切名は「山梨踏切」。
 1
1
1/26 8:09
もう一度富士急行線を跨いで山側へ。踏切名は「山梨踏切」。
 北に開けて三ツ峠山がよく見える。
北に開けて三ツ峠山がよく見える。
 1
1
1/26 8:12
北に開けて三ツ峠山がよく見える。
 <蒼竜峡>
<蒼竜峡>
すぐ上流で桂川と鹿留川が合流することもあって流れが強く大きくうねっている。まさに蒼い竜のよう。
 1
1
1/26 8:13
<蒼竜峡>
すぐ上流で桂川と鹿留川が合流することもあって流れが強く大きくうねっている。まさに蒼い竜のよう。
 南に鉄塔の立つ小高い山を見上げる。あれが本日最初のピークである古城山。ただ、国道側からは直接取り付けないので大きく回り込んでアプローチする。
南に鉄塔の立つ小高い山を見上げる。あれが本日最初のピークである古城山。ただ、国道側からは直接取り付けないので大きく回り込んでアプローチする。
 1
1
1/26 8:14
南に鉄塔の立つ小高い山を見上げる。あれが本日最初のピークである古城山。ただ、国道側からは直接取り付けないので大きく回り込んでアプローチする。
 <早作の石仏群>
<早作の石仏群>
国道から直接南下してくる道と合わせまた左右に分かれる。交差点には榎を中心に多数の石仏が並べられている。
 1
1
1/26 8:15
<早作の石仏群>
国道から直接南下してくる道と合わせまた左右に分かれる。交差点には榎を中心に多数の石仏が並べられている。
 解説板によると御正体山上人堂の参詣路に並ぶ一番観音らしい。
解説板によると御正体山上人堂の参詣路に並ぶ一番観音らしい。
 1
1
1/26 8:16
解説板によると御正体山上人堂の参詣路に並ぶ一番観音らしい。
 <鍛冶屋坂水路>
<鍛冶屋坂水路>
桂川の水はこの辺りで取水されて谷村発電所へ流れていく。猿橋や駒橋あたりの水道橋と同じく年季が入っていて重厚感がある。
 1
1
1/26 8:17
<鍛冶屋坂水路>
桂川の水はこの辺りで取水されて谷村発電所へ流れていく。猿橋や駒橋あたりの水道橋と同じく年季が入っていて重厚感がある。
 <おなん淵の滝>
<おなん淵の滝>
本日2つめの滝見。鹿留川が柱状節理の岩を断ち割る様にして注ぐ。傍らに設置された解説板で淵の名前の由来となった伝説を読む事ができる。
 1
1
1/26 8:18
<おなん淵の滝>
本日2つめの滝見。鹿留川が柱状節理の岩を断ち割る様にして注ぐ。傍らに設置された解説板で淵の名前の由来となった伝説を読む事ができる。
 淵の対岸には祠に彫られているのは三体の地蔵だろうか。それとも三猿?
淵の対岸には祠に彫られているのは三体の地蔵だろうか。それとも三猿?
 1
1
1/26 8:18
淵の対岸には祠に彫られているのは三体の地蔵だろうか。それとも三猿?
 おなん淵の滝を上流側から。ごつごつとした特徴的な岩の様子が分かる。
おなん淵の滝を上流側から。ごつごつとした特徴的な岩の様子が分かる。
 1
1
1/26 8:19
おなん淵の滝を上流側から。ごつごつとした特徴的な岩の様子が分かる。
 <古城山清浄院跡(登山口)>
<古城山清浄院跡(登山口)>
水道橋の南でコの字に古渡の住宅地を折れていくと登山口に辿り着く。
 1
1
1/26 8:21
<古城山清浄院跡(登山口)>
水道橋の南でコの字に古渡の住宅地を折れていくと登山口に辿り着く。
 以前はこの平場にそれなりのお寺があったようだけど今は集められた石仏が整然と並び静かにその栄枯盛衰を伝えている。
以前はこの平場にそれなりのお寺があったようだけど今は集められた石仏が整然と並び静かにその栄枯盛衰を伝えている。
 1
1
1/26 8:21
以前はこの平場にそれなりのお寺があったようだけど今は集められた石仏が整然と並び静かにその栄枯盛衰を伝えている。
 谷村町から小一時間歩いてようやく身体も暖まってきたので上着や帽子を脱いで登り始める。参道は想像以上にきれいに整備されていて獣害防止のゲートまで設置されていた。
谷村町から小一時間歩いてようやく身体も暖まってきたので上着や帽子を脱いで登り始める。参道は想像以上にきれいに整備されていて獣害防止のゲートまで設置されていた。
 1
1
1/26 8:25
谷村町から小一時間歩いてようやく身体も暖まってきたので上着や帽子を脱いで登り始める。参道は想像以上にきれいに整備されていて獣害防止のゲートまで設置されていた。
 入山してすぐに郭や堀切と思しき地形が続き、アカマツの明るい林を登っていくとじきに住吉神社の境内に入る。
入山してすぐに郭や堀切と思しき地形が続き、アカマツの明るい林を登っていくとじきに住吉神社の境内に入る。
 1
1
1/26 8:26
入山してすぐに郭や堀切と思しき地形が続き、アカマツの明るい林を登っていくとじきに住吉神社の境内に入る。
 <住吉神社>
<住吉神社>
海のない山梨にどうして住吉神社と思ったが、麓からこの山を見上げると海を行く舟の形に似ている事から海上守護の神様が勧請されたという。
 1
1
1/26 8:26
<住吉神社>
海のない山梨にどうして住吉神社と思ったが、麓からこの山を見上げると海を行く舟の形に似ている事から海上守護の神様が勧請されたという。
 拝殿手前にある小さな祠には丸石道祖神。道中参拝してきた田原神社や小篠神社にも小さな丸石が祀られていた。
拝殿手前にある小さな祠には丸石道祖神。道中参拝してきた田原神社や小篠神社にも小さな丸石が祀られていた。
 1
1
1/26 8:27
拝殿手前にある小さな祠には丸石道祖神。道中参拝してきた田原神社や小篠神社にも小さな丸石が祀られていた。
 住𠮷神社本殿を覗く。朱塗りで凝った彫り、鬼の面と甲州街道沿いにしばしばみられる江戸後期の派手な構成。
住𠮷神社本殿を覗く。朱塗りで凝った彫り、鬼の面と甲州街道沿いにしばしばみられる江戸後期の派手な構成。
 1
1
1/26 8:27
住𠮷神社本殿を覗く。朱塗りで凝った彫り、鬼の面と甲州街道沿いにしばしばみられる江戸後期の派手な構成。
 <古城山山頂>
<古城山山頂>
住𠮷神社のある一帯が小山田氏が烽火台として使用した古渡城の主郭跡らしい。
 1
1
1/26 8:28
<古城山山頂>
住𠮷神社のある一帯が小山田氏が烽火台として使用した古渡城の主郭跡らしい。
 実際の最高点は社殿真裏の塚状に高くなった場所。
実際の最高点は社殿真裏の塚状に高くなった場所。
 1
1
1/26 8:28
実際の最高点は社殿真裏の塚状に高くなった場所。
 <東京電力山中線 21号鉄塔>
<東京電力山中線 21号鉄塔>
山頂のやや北に建つ。この先P697まではこの線の巡視路のお世話になる。
 1
1
1/26 8:28
<東京電力山中線 21号鉄塔>
山頂のやや北に建つ。この先P697まではこの線の巡視路のお世話になる。
 足元には都留アルプスの登山道表記。
足元には都留アルプスの登山道表記。
 1
1
1/26 8:28
足元には都留アルプスの登山道表記。
 東電のゴム製階段を辿って谷へと急下降。
東電のゴム製階段を辿って谷へと急下降。
 1
1
1/26 8:29
東電のゴム製階段を辿って谷へと急下降。
 下り立った先は刈り払われて気持ちの良い広場。ベンチまで設置されていた。
下り立った先は刈り払われて気持ちの良い広場。ベンチまで設置されていた。
 1
1
1/26 8:30
下り立った先は刈り払われて気持ちの良い広場。ベンチまで設置されていた。
 沢を越え対岸に取り付く。歩きやすいけど登り一辺倒で足にくる。
沢を越え対岸に取り付く。歩きやすいけど登り一辺倒で足にくる。
 1
1
1/26 8:36
沢を越え対岸に取り付く。歩きやすいけど登り一辺倒で足にくる。
 <東京電力山中線 20号鉄塔>
<東京電力山中線 20号鉄塔>
20号は木立に囲まれていて眺望に乏しい。
 1
1
1/26 8:37
<東京電力山中線 20号鉄塔>
20号は木立に囲まれていて眺望に乏しい。
 <697m点/東京電力山中線 19号鉄塔>
<697m点/東京電力山中線 19号鉄塔>
なおも続く階段道をあえぎながら歩いて行くと松の葉が敷き詰められた地道に変わり多少ましな登りになる。開けたと思い空を見上げると19号鉄塔が立っていた。
 1
1
1/26 8:42
<697m点/東京電力山中線 19号鉄塔>
なおも続く階段道をあえぎながら歩いて行くと松の葉が敷き詰められた地道に変わり多少ましな登りになる。開けたと思い空を見上げると19号鉄塔が立っていた。
 西に三ツ峠。
西に三ツ峠。
 1
1
1/26 8:43
西に三ツ峠。
 東側は今倉山?
東側は今倉山?
 1
1
1/26 8:43
東側は今倉山?
 697m点の先で都留アルプスとは道を分ける。
697m点の先で都留アルプスとは道を分ける。
 1
1
1/26 8:43
697m点の先で都留アルプスとは道を分ける。
 道標を見て南の尾崎山へ続く尾根へ。
道標を見て南の尾崎山へ続く尾根へ。
 1
1
1/26 8:43
道標を見て南の尾崎山へ続く尾根へ。
 踏み込むなり急に踏み跡が薄くなる。そして傾斜が一気について鉄砲登りとなる。
踏み込むなり急に踏み跡が薄くなる。そして傾斜が一気について鉄砲登りとなる。
 1
1
1/26 8:46
踏み込むなり急に踏み跡が薄くなる。そして傾斜が一気について鉄砲登りとなる。
 急登の途中、ちらちらと木立の向こうに富士山が見え隠れする。
急登の途中、ちらちらと木立の向こうに富士山が見え隠れする。
 1
1
1/26 8:52
急登の途中、ちらちらと木立の向こうに富士山が見え隠れする。
 標高850mを過ぎれば地形図上めちゃくちゃなな登りではないはずなのだけど、どうも足元がふわふわとしていて登り辛い。
標高850mを過ぎれば地形図上めちゃくちゃなな登りではないはずなのだけど、どうも足元がふわふわとしていて登り辛い。
 1
1
1/26 9:00
標高850mを過ぎれば地形図上めちゃくちゃなな登りではないはずなのだけど、どうも足元がふわふわとしていて登り辛い。
 <尾崎山山頂>
<尾崎山山頂>
まだ今日の山行の1/3も消化していないのに肩で息をつきながら尾崎山に登頂。尾崎山の標識は消えかかっている。また、アカマツ交じりの明るい山頂ながらあまり眺望は利かない。
 1
1
1/26 9:05
<尾崎山山頂>
まだ今日の山行の1/3も消化していないのに肩で息をつきながら尾崎山に登頂。尾崎山の標識は消えかかっている。また、アカマツ交じりの明るい山頂ながらあまり眺望は利かない。
 967.8m三等三角点「辺殿」
967.8m三等三角点「辺殿」
 1
1
1/26 9:05
967.8m三等三角点「辺殿」
 尾崎山まで登ってしまえば小野分岐まではごく緩やかな下りが続く。こちらの方が正規ルートの感があり歩きやすかった。
尾崎山まで登ってしまえば小野分岐まではごく緩やかな下りが続く。こちらの方が正規ルートの感があり歩きやすかった。
 1
1
1/26 9:08
尾崎山まで登ってしまえば小野分岐まではごく緩やかな下りが続く。こちらの方が正規ルートの感があり歩きやすかった。
 小野分岐手前のやや痩せたコル。分岐までは少しだけ登り返しがあった。
小野分岐手前のやや痩せたコル。分岐までは少しだけ登り返しがあった。
 1
1
1/26 9:16
小野分岐手前のやや痩せたコル。分岐までは少しだけ登り返しがあった。
 梢越しの都留市街と大菩薩へ連なる山稜。
梢越しの都留市街と大菩薩へ連なる山稜。
 1
1
1/26 9:16
梢越しの都留市街と大菩薩へ連なる山稜。
 振り向くと尾崎山越しの三ツ峠。
振り向くと尾崎山越しの三ツ峠。
 1
1
1/26 9:18
振り向くと尾崎山越しの三ツ峠。
 <分岐>
<分岐>
緩く登り上げた先で三叉路に入る。「文台山」の案内あり。
 1
1
1/26 9:18
<分岐>
緩く登り上げた先で三叉路に入る。「文台山」の案内あり。
 やっと富士山が開けて見えた。
やっと富士山が開けて見えた。
 1
1
1/26 9:19
やっと富士山が開けて見えた。
 ここからがバリエーション本番。グリップの効き辛い斜面を急下降。
ここからがバリエーション本番。グリップの効き辛い斜面を急下降。
 1
1
1/26 9:21
ここからがバリエーション本番。グリップの効き辛い斜面を急下降。
 安全地帯より振り返って。等高線はあまり信用しない方がいい。
安全地帯より振り返って。等高線はあまり信用しない方がいい。
 1
1
1/26 9:23
安全地帯より振り返って。等高線はあまり信用しない方がいい。
 続けて下ろうとすると一体どうやって登ってきたのか獣害防止のネットが張ってある。突然首の高さに張り綱が引かれているのでぎょっとした。
続けて下ろうとすると一体どうやって登ってきたのか獣害防止のネットが張ってある。突然首の高さに張り綱が引かれているのでぎょっとした。
 1
1
1/26 9:23
続けて下ろうとすると一体どうやって登ってきたのか獣害防止のネットが張ってある。突然首の高さに張り綱が引かれているのでぎょっとした。
 しばらくするとネットは東の谷へ逸れていく。掴まるものがなくなるので木の幹に飛び移る様にして滑り落ちていった。
しばらくするとネットは東の谷へ逸れていく。掴まるものがなくなるので木の幹に飛び移る様にして滑り落ちていった。
 1
1
1/26 9:26
しばらくするとネットは東の谷へ逸れていく。掴まるものがなくなるので木の幹に飛び移る様にして滑り落ちていった。
 次のP895の途中にある痩せ尾根は足早に通過。
次のP895の途中にある痩せ尾根は足早に通過。
 1
1
1/26 9:30
次のP895の途中にある痩せ尾根は足早に通過。
 895m点は特徴が薄く、かえって警戒しながら南へ下りた。
895m点は特徴が薄く、かえって警戒しながら南へ下りた。
 1
1
1/26 9:32
895m点は特徴が薄く、かえって警戒しながら南へ下りた。
 次の小コブからは北に笹尾根のあたりへ開けている。
次の小コブからは北に笹尾根のあたりへ開けている。
 1
1
1/26 9:34
次の小コブからは北に笹尾根のあたりへ開けている。
 鞍部から文台山への荒れた登り返し。この辺りは序の口。
鞍部から文台山への荒れた登り返し。この辺りは序の口。
 1
1
1/26 9:40
鞍部から文台山への荒れた登り返し。この辺りは序の口。
 標高950mを超えるとテープはあるものの踏み跡はほぼ消滅してルートファインディングが求められる。好みによるかもしれないが今回は正面の大岩を西にかわして次の岩場を直登した。
標高950mを超えるとテープはあるものの踏み跡はほぼ消滅してルートファインディングが求められる。好みによるかもしれないが今回は正面の大岩を西にかわして次の岩場を直登した。
 1
1
1/26 9:46
標高950mを超えるとテープはあるものの踏み跡はほぼ消滅してルートファインディングが求められる。好みによるかもしれないが今回は正面の大岩を西にかわして次の岩場を直登した。
 テープはあくまで目安程度。
テープはあくまで目安程度。
 1
1
1/26 9:49
テープはあくまで目安程度。
 岩場を這いあがる。足元はぐずぐずで木の根や崩れる岩も掴まざるを得なかった。見た目以上に危ない。
岩場を這いあがる。足元はぐずぐずで木の根や崩れる岩も掴まざるを得なかった。見た目以上に危ない。
 1
1
1/26 9:49
岩場を這いあがる。足元はぐずぐずで木の根や崩れる岩も掴まざるを得なかった。見た目以上に危ない。
 1000mを過ぎると尾根らしくなり多少は地に足が付いた感じになる。
1000mを過ぎると尾根らしくなり多少は地に足が付いた感じになる。
 1
1
1/26 9:53
1000mを過ぎると尾根らしくなり多少は地に足が付いた感じになる。
 振り向くと文台山の影が。ここを下りたいとは思わない。
振り向くと文台山の影が。ここを下りたいとは思わない。
 1
1
1/26 9:53
振り向くと文台山の影が。ここを下りたいとは思わない。
 急登はまだ200m近く続く。杓子山越しに南アルプスが見える。冬場でなければ心が折れそうな登りだった。
急登はまだ200m近く続く。杓子山越しに南アルプスが見える。冬場でなければ心が折れそうな登りだった。
 1
1
1/26 9:58
急登はまだ200m近く続く。杓子山越しに南アルプスが見える。冬場でなければ心が折れそうな登りだった。
 直下に出ても依然として不明瞭な山道。
直下に出ても依然として不明瞭な山道。
 1
1
1/26 10:04
直下に出ても依然として不明瞭な山道。
 <文台山山頂>
<文台山山頂>
緩く傾斜したピークが文台山の頂上。「登山道」の看板が白々しく見える道だった。
 1
1
1/26 10:06
<文台山山頂>
緩く傾斜したピークが文台山の頂上。「登山道」の看板が白々しく見える道だった。
 山頂標
山頂標
 1
1
1/26 10:06
山頂標
 有名なツルハシと三等三角点「宮沢」
有名なツルハシと三等三角点「宮沢」
 1
1
1/26 10:06
有名なツルハシと三等三角点「宮沢」
 南に見えるのが御正体山だろうか。
南に見えるのが御正体山だろうか。
 1
1
1/26 10:06
南に見えるのが御正体山だろうか。
 山頂南でがさがさいうので身構えていたら南斜面から猟犬が登ってきた。大野山あたりで2発ほど銃声を聞いたのはこれだったか。程なくして猟師も上がってきた。
山頂南でがさがさいうので身構えていたら南斜面から猟犬が登ってきた。大野山あたりで2発ほど銃声を聞いたのはこれだったか。程なくして猟師も上がってきた。
 1
1
1/26 10:06
山頂南でがさがさいうので身構えていたら南斜面から猟犬が登ってきた。大野山あたりで2発ほど銃声を聞いたのはこれだったか。程なくして猟師も上がってきた。
 居座っていたら猟犬が落ち着かないだろうから自分は東峰の方で休む事にする。地図上では大したことない双耳峰だけど短いながらしっかりとした登り返しが待っている。
居座っていたら猟犬が落ち着かないだろうから自分は東峰の方で休む事にする。地図上では大したことない双耳峰だけど短いながらしっかりとした登り返しが待っている。
 1
1
1/26 10:09
居座っていたら猟犬が落ち着かないだろうから自分は東峰の方で休む事にする。地図上では大したことない双耳峰だけど短いながらしっかりとした登り返しが待っている。
 <文台山東峰>
<文台山東峰>
西峰に比べれば手狭だけど休憩するには十分。お茶を飲みながら御正体山のシルエットを眺める。
 1
1
1/26 10:10
<文台山東峰>
西峰に比べれば手狭だけど休憩するには十分。お茶を飲みながら御正体山のシルエットを眺める。
 100mほど下に林道が見えた。あの辺りに下りるのだろう。
100mほど下に林道が見えた。あの辺りに下りるのだろう。
 1
1
1/26 10:11
100mほど下に林道が見えた。あの辺りに下りるのだろう。
 <分岐>
<分岐>
左右に切れ落ちた急斜面を慎重に下りていくと南尾根への分岐に出る。ハガケ山を案内する標識はないもののテープ類が賑やかなので気が付いた。
 1
1
1/26 10:18
<分岐>
左右に切れ落ちた急斜面を慎重に下りていくと南尾根への分岐に出る。ハガケ山を案内する標識はないもののテープ類が賑やかなので気が付いた。
 東へ伸びる尾根は細野からの正規登山道らしい。このプレートを背にして下りていく。
東へ伸びる尾根は細野からの正規登山道らしい。このプレートを背にして下りていく。
 1
1
1/26 10:18
東へ伸びる尾根は細野からの正規登山道らしい。このプレートを背にして下りていく。
 南の尾根は灌木がうるさいが足元は滑りやすいので掴まる場所に困らない。
南の尾根は灌木がうるさいが足元は滑りやすいので掴まる場所に困らない。
 1
1
1/26 10:19
南の尾根は灌木がうるさいが足元は滑りやすいので掴まる場所に困らない。
 尾根は林道の工事で破壊されているため地図通りには歩けない。テープにが擁壁を避けて下りられるルートを案内していた。
尾根は林道の工事で破壊されているため地図通りには歩けない。テープにが擁壁を避けて下りられるルートを案内していた。
 1
1
1/26 10:21
尾根は林道の工事で破壊されているため地図通りには歩けない。テープにが擁壁を避けて下りられるルートを案内していた。
 林道を東に進むと以前はロープが下がっていた斜面は立派な階段道に変わっていた。ご丁寧に道標まで設置してある。
林道を東に進むと以前はロープが下がっていた斜面は立派な階段道に変わっていた。ご丁寧に道標まで設置してある。
 1
1
1/26 10:22
林道を東に進むと以前はロープが下がっていた斜面は立派な階段道に変わっていた。ご丁寧に道標まで設置してある。
 しかしこの階段、一段がやたら高くてスタミナを奪われた。
しかしこの階段、一段がやたら高くてスタミナを奪われた。
 1
1
1/26 10:23
しかしこの階段、一段がやたら高くてスタミナを奪われた。
 登り切って擁壁側に移動すれば三ツ峠が大きい。
登り切って擁壁側に移動すれば三ツ峠が大きい。
 1
1
1/26 10:24
登り切って擁壁側に移動すれば三ツ峠が大きい。
 再び踏み跡の薄い尾根歩き。倒木をかわしながら冬枯れの眺めを楽しむ。この辺りまで来ると富士山は杓子山の陰だった。
再び踏み跡の薄い尾根歩き。倒木をかわしながら冬枯れの眺めを楽しむ。この辺りまで来ると富士山は杓子山の陰だった。
 1
1
1/26 10:29
再び踏み跡の薄い尾根歩き。倒木をかわしながら冬枯れの眺めを楽しむ。この辺りまで来ると富士山は杓子山の陰だった。
 林道以降しばらくは大きな登りもなく小コブを淡々と消化していく。相変わらず倒木が多いのと一部崩壊地はあるものの歩くのに支障はない。
林道以降しばらくは大きな登りもなく小コブを淡々と消化していく。相変わらず倒木が多いのと一部崩壊地はあるものの歩くのに支障はない。
 1
1
1/26 10:33
林道以降しばらくは大きな登りもなく小コブを淡々と消化していく。相変わらず倒木が多いのと一部崩壊地はあるものの歩くのに支障はない。
 明るいアカマツ林の1225m点。
明るいアカマツ林の1225m点。
 1
1
1/26 10:35
明るいアカマツ林の1225m点。
 次のピークには意味ありげな石柱。
次のピークには意味ありげな石柱。
 1
1
1/26 10:42
次のピークには意味ありげな石柱。
 鋭鋒のハガケ山を捉えた。
鋭鋒のハガケ山を捉えた。
 1
1
1/26 10:42
鋭鋒のハガケ山を捉えた。
 もう一つ先のピークで南に折れる。古いテープの道案内がありがたい。
もう一つ先のピークで南に折れる。古いテープの道案内がありがたい。
 1
1
1/26 10:45
もう一つ先のピークで南に折れる。古いテープの道案内がありがたい。
 ハゲケ山の鞍部に向けて下り始めるあたりから道が目立って荒れ始める。
ハゲケ山の鞍部に向けて下り始めるあたりから道が目立って荒れ始める。
 1
1
1/26 10:49
ハゲケ山の鞍部に向けて下り始めるあたりから道が目立って荒れ始める。
 倒木が終わると次は灌木がうるさくなる。
倒木が終わると次は灌木がうるさくなる。
 1
1
1/26 10:53
倒木が終わると次は灌木がうるさくなる。
 痩せた尾根から飛びつくようにして急登に移る。
痩せた尾根から飛びつくようにして急登に移る。
 1
1
1/26 10:54
痩せた尾根から飛びつくようにして急登に移る。
 ハガケ山の北面はほとんど崖のよう。
ハガケ山の北面はほとんど崖のよう。
 1
1
1/26 10:55
ハガケ山の北面はほとんど崖のよう。
 やや南寄りに灌木の間を縫うようにして登る。ザックが何度も引っ掛けられるし足元も固まっていなくて苦しい。
やや南寄りに灌木の間を縫うようにして登る。ザックが何度も引っ掛けられるし足元も固まっていなくて苦しい。
 1
1
1/26 10:57
やや南寄りに灌木の間を縫うようにして登る。ザックが何度も引っ掛けられるし足元も固まっていなくて苦しい。
 小さな岩場も。これは容易に越えられる。
小さな岩場も。これは容易に越えられる。
 1
1
1/26 10:58
小さな岩場も。これは容易に越えられる。
 岩場に立つと富士山が正面に。吉田口ルートの登山道もくっきりと見える。
岩場に立つと富士山が正面に。吉田口ルートの登山道もくっきりと見える。
 1
1
1/26 10:59
岩場に立つと富士山が正面に。吉田口ルートの登山道もくっきりと見える。
 急登が続くものの直下は安定していた。
急登が続くものの直下は安定していた。
 1
1
1/26 11:00
急登が続くものの直下は安定していた。
 <ハガケ山山頂>
<ハガケ山山頂>
狭く、数人が立てばいっぱいになりそうな頂上に到着。山頂標はなく、テープにマジックで書かれていた山名も消えてしまっていた。
 1
1
1/26 11:03
<ハガケ山山頂>
狭く、数人が立てばいっぱいになりそうな頂上に到着。山頂標はなく、テープにマジックで書かれていた山名も消えてしまっていた。
 どっしりとした御正体山を眺められるのも冬場だけ。
どっしりとした御正体山を眺められるのも冬場だけ。
 1
1
1/26 11:10
どっしりとした御正体山を眺められるのも冬場だけ。
 御正体山へ続く東尾根はいきなり落ちるような急下降。この辺りの等高線はあまり信用できない。
御正体山へ続く東尾根はいきなり落ちるような急下降。この辺りの等高線はあまり信用できない。
 1
1
1/26 11:10
御正体山へ続く東尾根はいきなり落ちるような急下降。この辺りの等高線はあまり信用できない。
 崩壊地に引きずり込まれないように進む。
崩壊地に引きずり込まれないように進む。
 1
1
1/26 11:12
崩壊地に引きずり込まれないように進む。
 ハガケ山東の小ピークより岩峰と呼ばれる核心部を見る。
ハガケ山東の小ピークより岩峰と呼ばれる核心部を見る。
 1
1
1/26 11:14
ハガケ山東の小ピークより岩峰と呼ばれる核心部を見る。
 ピークの先、1段目はとりあえず灌木の間に付けられた踏み跡を追っていけば何とか下りられるけど……
ピークの先、1段目はとりあえず灌木の間に付けられた踏み跡を追っていけば何とか下りられるけど……
 1
1
1/26 11:16
ピークの先、1段目はとりあえず灌木の間に付けられた踏み跡を追っていけば何とか下りられるけど……
 岩峰西側のコルに見える地図上の膨らみにはギャップが存在する。行き止まりのような地形から正直に東へ出ようとすると崖下りになり危ない。
岩峰西側のコルに見える地図上の膨らみにはギャップが存在する。行き止まりのような地形から正直に東へ出ようとすると崖下りになり危ない。
 1
1
1/26 11:18
岩峰西側のコルに見える地図上の膨らみにはギャップが存在する。行き止まりのような地形から正直に東へ出ようとすると崖下りになり危ない。
 南を観察するとテープが誘導している。
南を観察するとテープが誘導している。
 1
1
1/26 11:19
南を観察するとテープが誘導している。
 10mかそこらを南に下降して鞍部へトラバースする。ただしこちらもかなりの急傾斜で足場や掴まる木が少なく怖い思いをした。
10mかそこらを南に下降して鞍部へトラバースする。ただしこちらもかなりの急傾斜で足場や掴まる木が少なく怖い思いをした。
 1
1
1/26 11:20
10mかそこらを南に下降して鞍部へトラバースする。ただしこちらもかなりの急傾斜で足場や掴まる木が少なく怖い思いをした。
 深い谷が迫る痩せたコルに下り立つ。
深い谷が迫る痩せたコルに下り立つ。
 1
1
1/26 11:24
深い谷が迫る痩せたコルに下り立つ。
 岩峰を振り返って。正面が崖のように見えた東斜面。下降を失敗すると先ほどの谷に転落することになる。
岩峰を振り返って。正面が崖のように見えた東斜面。下降を失敗すると先ほどの谷に転落することになる。
 1
1
1/26 11:24
岩峰を振り返って。正面が崖のように見えた東斜面。下降を失敗すると先ほどの谷に転落することになる。
 岩峰へ取り付くも道が不明瞭で足場が崩れやすい。
岩峰へ取り付くも道が不明瞭で足場が崩れやすい。
 1
1
1/26 11:24
岩峰へ取り付くも道が不明瞭で足場が崩れやすい。
 例の谷の縁ぎりぎりを歩くシーンもあり嫌な汗をかいた。
例の谷の縁ぎりぎりを歩くシーンもあり嫌な汗をかいた。
 1
1
1/26 11:25
例の谷の縁ぎりぎりを歩くシーンもあり嫌な汗をかいた。
 意外にも緩やかな土の道を踏んで岩峰の頂上に立つ。こんな所に指導標が。
意外にも緩やかな土の道を踏んで岩峰の頂上に立つ。こんな所に指導標が。
 1
1
1/26 11:28
意外にも緩やかな土の道を踏んで岩峰の頂上に立つ。こんな所に指導標が。
 岩峰にも山名板等はなし。
岩峰にも山名板等はなし。
 1
1
1/26 11:29
岩峰にも山名板等はなし。
 一般ルートとの分岐に向けて急登を突き上げる。
一般ルートとの分岐に向けて急登を突き上げる。
 1
1
1/26 11:37
一般ルートとの分岐に向けて急登を突き上げる。
 灌木を避けながらにじり上がると最後はほとんど直登になり苦しめられた。
灌木を避けながらにじり上がると最後はほとんど直登になり苦しめられた。
 1
1
1/26 11:45
灌木を避けながらにじり上がると最後はほとんど直登になり苦しめられた。
 分岐に辿り着くと鹿留・杓子山と富士山が迎えてくれる。
分岐に辿り着くと鹿留・杓子山と富士山が迎えてくれる。
 1
1
1/26 11:47
分岐に辿り着くと鹿留・杓子山と富士山が迎えてくれる。
 白根三山をはじめ南アルプスの面々。
白根三山をはじめ南アルプスの面々。
 1
1
1/26 11:48
白根三山をはじめ南アルプスの面々。
 <分岐>
<分岐>
文台山側には「歩道不明瞭」の文字。以前は通行不能の表示もあったような。
 1
1
1/26 11:49
<分岐>
文台山側には「歩道不明瞭」の文字。以前は通行不能の表示もあったような。
 一般ルートに入るとブナが目立ち始める。
一般ルートに入るとブナが目立ち始める。
 1
1
1/26 11:55
一般ルートに入るとブナが目立ち始める。
 文台山~ハガケ山のルートとは段違いに歩きやすい。
文台山~ハガケ山のルートとは段違いに歩きやすい。
 1
1
1/26 11:56
文台山~ハガケ山のルートとは段違いに歩きやすい。
 1568m点の竜宮跡分岐点より、ここも富士山が大きい。
1568m点の竜宮跡分岐点より、ここも富士山が大きい。
 1
1
1/26 11:59
1568m点の竜宮跡分岐点より、ここも富士山が大きい。
 <峰神社>
<峰神社>
尾根の中央に配された石祠。片側の灯篭の胴が切り株で代用されている。
 1
1
1/26 12:00
<峰神社>
尾根の中央に配された石祠。片側の灯篭の胴が切り株で代用されている。
 御正体山が近くなってきた。
御正体山が近くなってきた。
 1
1
1/26 12:02
御正体山が近くなってきた。
 白銀の南アルプス。
白銀の南アルプス。
 1
1
1/26 12:06
白銀の南アルプス。
 心配していた雪もほとんど残っていなかった。ハガケ山の辺りで凍結していたら万事休すだったけど。
心配していた雪もほとんど残っていなかった。ハガケ山の辺りで凍結していたら万事休すだったけど。
 1
1
1/26 12:08
心配していた雪もほとんど残っていなかった。ハガケ山の辺りで凍結していたら万事休すだったけど。
 <御正体山山頂>
<御正体山山頂>
緩いアップダウンを経てブナ林の中にある山頂に到着。
 1
1
1/26 12:15
<御正体山山頂>
緩いアップダウンを経てブナ林の中にある山頂に到着。
 一等三角点「御正体山」
一等三角点「御正体山」
 1
1
1/26 12:16
一等三角点「御正体山」
 山頂の中心地には御正体権現と山頂標が並ぶ。祠にはイザナギの札が納められていた。
山頂の中心地には御正体権現と山頂標が並ぶ。祠にはイザナギの札が納められていた。
 1
1
1/26 12:16
山頂の中心地には御正体権現と山頂標が並ぶ。祠にはイザナギの札が納められていた。
 眺めのない頂上だけど空は開けて気持ちがいい。
眺めのない頂上だけど空は開けて気持ちがいい。
 1
1
1/26 12:17
眺めのない頂上だけど空は開けて気持ちがいい。
 下りは池の平ルートで鹿留川に出るので一旦来た道を引き返す。写真はP1568との鞍部にある小ギャップ。見た目ほど難しくはないけど初見だとぎょっとする。
下りは池の平ルートで鹿留川に出るので一旦来た道を引き返す。写真はP1568との鞍部にある小ギャップ。見た目ほど難しくはないけど初見だとぎょっとする。
 1
1
1/26 12:33
下りは池の平ルートで鹿留川に出るので一旦来た道を引き返す。写真はP1568との鞍部にある小ギャップ。見た目ほど難しくはないけど初見だとぎょっとする。
 <峰宮跡分岐>
<峰宮跡分岐>
軽く登り返して峰神社を通過。後は下るのみ。
 1
1
1/26 12:37
<峰宮跡分岐>
軽く登り返して峰神社を通過。後は下るのみ。
 <分岐>
<分岐>
ブナやミズラナの樹皮を見ながらハガケ山から合流してきた分岐に戻ってきた。ここから南へ折れて池の平に下りる。
 1
1
1/26 12:51
<分岐>
ブナやミズラナの樹皮を見ながらハガケ山から合流してきた分岐に戻ってきた。ここから南へ折れて池の平に下りる。
 南アルプスの素晴らしい眺めとここでお別れ。最後の最後で甲斐駒も顔を出した。
南アルプスの素晴らしい眺めとここでお別れ。最後の最後で甲斐駒も顔を出した。
 1
1
1/26 12:51
南アルプスの素晴らしい眺めとここでお別れ。最後の最後で甲斐駒も顔を出した。
 池の平ルートは急坂ながら明瞭で歩きやすい。さすがはプリンスルートといったところか。
池の平ルートは急坂ながら明瞭で歩きやすい。さすがはプリンスルートといったところか。
 1
1
1/26 12:55
池の平ルートは急坂ながら明瞭で歩きやすい。さすがはプリンスルートといったところか。
 <妙心上人堂跡>
<妙心上人堂跡>
すり鉢状の山道を下りていくと突然公園風に整地されたテラスに出る。振り返ると複数の石仏。付近には都留市教育委員会の設置した解説板や2004年の皇太子殿下御登頂のプレートがある。
 1
1
1/26 12:59
<妙心上人堂跡>
すり鉢状の山道を下りていくと突然公園風に整地されたテラスに出る。振り返ると複数の石仏。付近には都留市教育委員会の設置した解説板や2004年の皇太子殿下御登頂のプレートがある。
 大岩の下に並ぶ風変わりな石仏は妙心はじめ3代行者の像と思われる。この岩陰が上人入定の地だろうと辺りを観察すると「座禅岩」とある。現在、故郷の岐阜県揖斐川町にある横蔵寺に祀られている上人の即身仏は坐像である。
大岩の下に並ぶ風変わりな石仏は妙心はじめ3代行者の像と思われる。この岩陰が上人入定の地だろうと辺りを観察すると「座禅岩」とある。現在、故郷の岐阜県揖斐川町にある横蔵寺に祀られている上人の即身仏は坐像である。
 1
1
1/26 12:59
大岩の下に並ぶ風変わりな石仏は妙心はじめ3代行者の像と思われる。この岩陰が上人入定の地だろうと辺りを観察すると「座禅岩」とある。現在、故郷の岐阜県揖斐川町にある横蔵寺に祀られている上人の即身仏は坐像である。
 上人堂跡の向かいは見事な富士山の展望台。ベンチもあって広々としているので休憩するには最適。
上人堂跡の向かいは見事な富士山の展望台。ベンチもあって広々としているので休憩するには最適。
 1
1
1/26 13:01
上人堂跡の向かいは見事な富士山の展望台。ベンチもあって広々としているので休憩するには最適。
 龍ノ口と呼ばれる沢沿いまで植林の中を一気に下りていく。
龍ノ口と呼ばれる沢沿いまで植林の中を一気に下りていく。
 1
1
1/26 13:03
龍ノ口と呼ばれる沢沿いまで植林の中を一気に下りていく。
 そろそろ龍の口という所まで下ったところで唐突に32番の観音様と出会う。ここで33番は上人堂跡にいた背の高い観音像かなと想像したのだけどそれとは別に安置されているらしい。
そろそろ龍の口という所まで下ったところで唐突に32番の観音様と出会う。ここで33番は上人堂跡にいた背の高い観音像かなと想像したのだけどそれとは別に安置されているらしい。
 1
1
1/26 13:07
そろそろ龍の口という所まで下ったところで唐突に32番の観音様と出会う。ここで33番は上人堂跡にいた背の高い観音像かなと想像したのだけどそれとは別に安置されているらしい。
 荒れているという情報もあったけど至って快適な山道。途中からはゴム製の階段道も現れる。
荒れているという情報もあったけど至って快適な山道。途中からはゴム製の階段道も現れる。
 1
1
1/26 13:11
荒れているという情報もあったけど至って快適な山道。途中からはゴム製の階段道も現れる。
 <龍の口>
<龍の口>
久々に「登山道」のプレートを見て谷に下り立つ。龍の口の解説板の足元には31番の石仏。
 1
1
1/26 13:13
<龍の口>
久々に「登山道」のプレートを見て谷に下り立つ。龍の口の解説板の足元には31番の石仏。
 上人水垢離の場という事だけど上流の水量はあまりなかった。
上人水垢離の場という事だけど上流の水量はあまりなかった。
 1
1
1/26 13:13
上人水垢離の場という事だけど上流の水量はあまりなかった。
 登山口まで何度か沢を渡る箇所がある。いずれも橋が架けられているので通過は容易。
登山口まで何度か沢を渡る箇所がある。いずれも橋が架けられているので通過は容易。
 1
1
1/26 13:19
登山口まで何度か沢を渡る箇所がある。いずれも橋が架けられているので通過は容易。
 地形図の実線よりやや西側で作業道に出た。雪があったのは御正体山の頂上とここくらい。
地形図の実線よりやや西側で作業道に出た。雪があったのは御正体山の頂上とここくらい。
 1
1
1/26 13:20
地形図の実線よりやや西側で作業道に出た。雪があったのは御正体山の頂上とここくらい。
 石仏の番号を数えながら薄暗いダートの道を黙々と下りていく。時折見逃して引き返す、というような事が何度かあった。
石仏の番号を数えながら薄暗いダートの道を黙々と下りていく。時折見逃して引き返す、というような事が何度かあった。
 1
1
1/26 13:25
石仏の番号を数えながら薄暗いダートの道を黙々と下りていく。時折見逃して引き返す、というような事が何度かあった。
 P845の作業道分岐では道間違いを起こした。南側(写真右手)に下るのが正解。
P845の作業道分岐では道間違いを起こした。南側(写真右手)に下るのが正解。
 1
1
1/26 13:29
P845の作業道分岐では道間違いを起こした。南側(写真右手)に下るのが正解。
 この分岐に設置された登山道の案内板の位置が良くない。片方は北の作業道を指している、のだけど先が明らかに荒廃していたのですぐに間違いに気付けた。
この分岐に設置された登山道の案内板の位置が良くない。片方は北の作業道を指している、のだけど先が明らかに荒廃していたのですぐに間違いに気付けた。
 1
1
1/26 13:29
この分岐に設置された登山道の案内板の位置が良くない。片方は北の作業道を指している、のだけど先が明らかに荒廃していたのですぐに間違いに気付けた。
 正解の池の平側の作業道から。右手の22番の石仏が景色に溶け込んでいて下りてくる時には見落としていた。
正解の池の平側の作業道から。右手の22番の石仏が景色に溶け込んでいて下りてくる時には見落としていた。
 1
1
1/26 13:31
正解の池の平側の作業道から。右手の22番の石仏が景色に溶け込んでいて下りてくる時には見落としていた。
 <池の平>
<池の平>
川沿いにゆるゆると下り登山口に到着。
 1
1
1/26 13:37
<池の平>
川沿いにゆるゆると下り登山口に到着。
 今上天皇はここから登られたのかな。
今上天皇はここから登られたのかな。
 1
1
1/26 13:37
今上天皇はここから登られたのかな。
 所々に解説板などがあったので読み読み下りてきたけど龍の口から続くこの沢の名前は出てこなかった。
所々に解説板などがあったので読み読み下りてきたけど龍の口から続くこの沢の名前は出てこなかった。
 1
1
1/26 13:37
所々に解説板などがあったので読み読み下りてきたけど龍の口から続くこの沢の名前は出てこなかった。
 池の平から先は舗装路の林道細野鹿留線。南側には木製アーチの虹の木橋。綺麗な駐車場まである。
池の平から先は舗装路の林道細野鹿留線。南側には木製アーチの虹の木橋。綺麗な駐車場まである。
 1
1
1/26 13:39
池の平から先は舗装路の林道細野鹿留線。南側には木製アーチの虹の木橋。綺麗な駐車場まである。
 少し先には立派なあずまやも。ハイカーが結構利用するのかなと思ったら林道は年中閉鎖されている事をこの後知る。
少し先には立派なあずまやも。ハイカーが結構利用するのかなと思ったら林道は年中閉鎖されている事をこの後知る。
 1
1
1/26 13:42
少し先には立派なあずまやも。ハイカーが結構利用するのかなと思ったら林道は年中閉鎖されている事をこの後知る。
 鹿留川の美しい水色。
鹿留川の美しい水色。
 1
1
1/26 13:43
鹿留川の美しい水色。
 観察難易度の高い11番観音。崩落で林道が作り直されたのか道から離れた法面中段に同化するように立っている。
観察難易度の高い11番観音。崩落で林道が作り直されたのか道から離れた法面中段に同化するように立っている。
 1
1
1/26 13:45
観察難易度の高い11番観音。崩落で林道が作り直されたのか道から離れた法面中段に同化するように立っている。
 ズームにしないと彫られた十一番の字も読めない。
ズームにしないと彫られた十一番の字も読めない。
 1
1
1/26 13:45
ズームにしないと彫られた十一番の字も読めない。
 8番観音は岩陰に。
8番観音は岩陰に。
 1
1
1/26 13:51
8番観音は岩陰に。
 ここは珍しく他の石仏と一緒。恐らく旧三十三観音の一体と思われる。平成8年に地元有志の手によって安置された「新」三十三観音はみな聖観音菩薩像だが、こちらの旧観音さまは千手観音像。”妙心”講の再興にあたり予算や彫り手に制約が付いたのだろうと無粋な想像をした。
ここは珍しく他の石仏と一緒。恐らく旧三十三観音の一体と思われる。平成8年に地元有志の手によって安置された「新」三十三観音はみな聖観音菩薩像だが、こちらの旧観音さまは千手観音像。”妙心”講の再興にあたり予算や彫り手に制約が付いたのだろうと無粋な想像をした。
 1
1
1/26 13:52
ここは珍しく他の石仏と一緒。恐らく旧三十三観音の一体と思われる。平成8年に地元有志の手によって安置された「新」三十三観音はみな聖観音菩薩像だが、こちらの旧観音さまは千手観音像。”妙心”講の再興にあたり予算や彫り手に制約が付いたのだろうと無粋な想像をした。
 3番観音は小さな祠の境内に立つ。山の神様だろうか。他にも昭和に建てられた馬頭観音もあった。
3番観音は小さな祠の境内に立つ。山の神様だろうか。他にも昭和に建てられた馬頭観音もあった。
 1
1
1/26 13:57
3番観音は小さな祠の境内に立つ。山の神様だろうか。他にも昭和に建てられた馬頭観音もあった。
 岩の上で手を合わせる石仏。番号がないけどこちらが2番かと思ったらちゃんと2番観音はその先にいた。
岩の上で手を合わせる石仏。番号がないけどこちらが2番かと思ったらちゃんと2番観音はその先にいた。
 1
1
1/26 14:03
岩の上で手を合わせる石仏。番号がないけどこちらが2番かと思ったらちゃんと2番観音はその先にいた。
 そうこうしているうちに林道ゲートに出る。冬期規制かと思ったら年中通行止めだった。車道のどこにも落石はなかったしつい最近できたかのような整備具合だったので驚きだ。
そうこうしているうちに林道ゲートに出る。冬期規制かと思ったら年中通行止めだった。車道のどこにも落石はなかったしつい最近できたかのような整備具合だったので驚きだ。
 1
1
1/26 14:05
そうこうしているうちに林道ゲートに出る。冬期規制かと思ったら年中通行止めだった。車道のどこにも落石はなかったしつい最近できたかのような整備具合だったので驚きだ。
 <御正体神社>
<御正体神社>
ゲートのすぐ先に御正体神社の参道入口。
 1
1
1/26 14:06
<御正体神社>
ゲートのすぐ先に御正体神社の参道入口。
 「御正体山」の扁額が掛かる鳥居の足元には1番の石仏。
「御正体山」の扁額が掛かる鳥居の足元には1番の石仏。
 1
1
1/26 14:06
「御正体山」の扁額が掛かる鳥居の足元には1番の石仏。
 長い参道を登る。山の神社にありがちな急な階段ではなく段差が広く取ってあり歩きやすい。
長い参道を登る。山の神社にありがちな急な階段ではなく段差が広く取ってあり歩きやすい。
 1
1
1/26 14:07
長い参道を登る。山の神社にありがちな急な階段ではなく段差が広く取ってあり歩きやすい。
 拝殿内の様子。妙心ゆかりのお宮ということで神社というよりもお堂の雰囲気が濃い。東の三輪神社は御正体山をご神体としているそうだが、こちらはどうなのだろう。
拝殿内の様子。妙心ゆかりのお宮ということで神社というよりもお堂の雰囲気が濃い。東の三輪神社は御正体山をご神体としているそうだが、こちらはどうなのだろう。
 1
1
1/26 14:08
拝殿内の様子。妙心ゆかりのお宮ということで神社というよりもお堂の雰囲気が濃い。東の三輪神社は御正体山をご神体としているそうだが、こちらはどうなのだろう。
 拝殿の裏に回ると隠れるように念仏塔が立てられていた。修験宗廃止の折に山中の上人堂は取り壊されたという話だけど、三代巨戒が建てたというこの塔は破壊を免れたようだ。
拝殿の裏に回ると隠れるように念仏塔が立てられていた。修験宗廃止の折に山中の上人堂は取り壊されたという話だけど、三代巨戒が建てたというこの塔は破壊を免れたようだ。
 1
1
1/26 14:09
拝殿の裏に回ると隠れるように念仏塔が立てられていた。修験宗廃止の折に山中の上人堂は取り壊されたという話だけど、三代巨戒が建てたというこの塔は破壊を免れたようだ。
 神社を出て北上。管理釣り場の向かいは採石場になっていた。
神社を出て北上。管理釣り場の向かいは採石場になっていた。
 1
1
1/26 14:16
神社を出て北上。管理釣り場の向かいは採石場になっていた。
 <大山祇神社>
<大山祇神社>
砂原地区南のはずれに鎮座する山の神様。境内に石仏・石祠が多数。
 1
1
1/26 14:19
<大山祇神社>
砂原地区南のはずれに鎮座する山の神様。境内に石仏・石祠が多数。
 拝殿を覗くと中の木祠にはそれぞれ仏像が。
拝殿を覗くと中の木祠にはそれぞれ仏像が。
 1
1
1/26 14:20
拝殿を覗くと中の木祠にはそれぞれ仏像が。
 門原地区の農地?内にある四等三角点「大野」を探す。点の記にはこの電柱の近くにあるらしいのだけど見付からない。
門原地区の農地?内にある四等三角点「大野」を探す。点の記にはこの電柱の近くにあるらしいのだけど見付からない。
 1
1
1/26 14:34
門原地区の農地?内にある四等三角点「大野」を探す。点の記にはこの電柱の近くにあるらしいのだけど見付からない。
 10分近く探したのだけど枯草で荒れて標石は見付からず。やや離れた所に防護石にしては大きな石があったけど三角点との関連も判らずじまいだった。
10分近く探したのだけど枯草で荒れて標石は見付からず。やや離れた所に防護石にしては大きな石があったけど三角点との関連も判らずじまいだった。
 1
1
1/26 14:34
10分近く探したのだけど枯草で荒れて標石は見付からず。やや離れた所に防護石にしては大きな石があったけど三角点との関連も判らずじまいだった。
 しかし門原地区の入口には古い石造物が多数あり収穫はあった。
しかし門原地区の入口には古い石造物が多数あり収穫はあった。
 1
1
1/26 14:42
しかし門原地区の入口には古い石造物が多数あり収穫はあった。
 完全に苔に飲まれているものも含め10数基はあっただろうか。
完全に苔に飲まれているものも含め10数基はあっただろうか。
 1
1
1/26 14:42
完全に苔に飲まれているものも含め10数基はあっただろうか。
 <門原不動尊>
<門原不動尊>
石仏群の近くにあるお不動様。中には秋葉神社の掛け軸がある。この辺りはやはり神仏習合の名残が色濃く残っている。
 1
1
1/26 14:43
<門原不動尊>
石仏群の近くにあるお不動様。中には秋葉神社の掛け軸がある。この辺りはやはり神仏習合の名残が色濃く残っている。
 北側、滝子山方面の眺め。
北側、滝子山方面の眺め。
 1
1
1/26 14:48
北側、滝子山方面の眺め。
 <今宮神社>
<今宮神社>
奇異な幹回りのケヤキがある旧村社。スサノオをはじめ九柱を祀る。
 1
1
1/26 14:54
<今宮神社>
奇異な幹回りのケヤキがある旧村社。スサノオをはじめ九柱を祀る。
 覆屋の中には繊細な彫刻の施された本殿がある。こちらは富士講や御正体山信仰よりも古い。
覆屋の中には繊細な彫刻の施された本殿がある。こちらは富士講や御正体山信仰よりも古い。
 1
1
1/26 14:55
覆屋の中には繊細な彫刻の施された本殿がある。こちらは富士講や御正体山信仰よりも古い。
 鹿留発電所の鉄管。この斜面の途中にお宮があるらしいけど未踏査。
鹿留発電所の鉄管。この斜面の途中にお宮があるらしいけど未踏査。
 1
1
1/26 15:01
鹿留発電所の鉄管。この斜面の途中にお宮があるらしいけど未踏査。
 桂川沿いまで下りてきた。
桂川沿いまで下りてきた。
 1
1
1/26 15:03
桂川沿いまで下りてきた。
 四等三角点「小沼」
四等三角点「小沼」
標石は確認できず防護石と割れた標柱のみ。
 1
1
1/26 15:04
四等三角点「小沼」
標石は確認できず防護石と割れた標柱のみ。
 発電所西側にあるこちらの水路はオーバーフロー時のものかな。
発電所西側にあるこちらの水路はオーバーフロー時のものかな。
 1
1
1/26 15:05
発電所西側にあるこちらの水路はオーバーフロー時のものかな。
 桂川を渡る。付近にあったという小山田氏の屋敷跡に因むものだろうか、橋近くに石仏が並ぶ。
桂川を渡る。付近にあったという小山田氏の屋敷跡に因むものだろうか、橋近くに石仏が並ぶ。
 1
1
1/26 15:10
桂川を渡る。付近にあったという小山田氏の屋敷跡に因むものだろうか、橋近くに石仏が並ぶ。
 予期せず富士山が。
予期せず富士山が。
 1
1
1/26 15:10
予期せず富士山が。
 中央道を潜って北の天の滝へ。獣避けのフェンスの先からちょっとした山道を下る。案内が周辺にないのでここでよいのだろうかとちょっと躊躇する。
中央道を潜って北の天の滝へ。獣避けのフェンスの先からちょっとした山道を下る。案内が周辺にないのでここでよいのだろうかとちょっと躊躇する。
 1
1
1/26 15:16
中央道を潜って北の天の滝へ。獣避けのフェンスの先からちょっとした山道を下る。案内が周辺にないのでここでよいのだろうかとちょっと躊躇する。
 <天の滝>
<天の滝>
次第に大きくなる轟音を辿っていくと滝壺に到達する。一帯はホールのようになっていて主瀑が立てる轟きに包まれる。あちこちから漏れ出ずる潜流瀑も見事。
 1
1
1/26 15:19
<天の滝>
次第に大きくなる轟音を辿っていくと滝壺に到達する。一帯はホールのようになっていて主瀑が立てる轟きに包まれる。あちこちから漏れ出ずる潜流瀑も見事。
 周辺の摂理が見える岩盤にも圧倒される。個人的には田原の滝に並ぶ名瀑だと思う。
周辺の摂理が見える岩盤にも圧倒される。個人的には田原の滝に並ぶ名瀑だと思う。
 1
1
1/26 15:19
周辺の摂理が見える岩盤にも圧倒される。個人的には田原の滝に並ぶ名瀑だと思う。
 天の滝への道の様子。急傾斜で道もやや荒れている。スニーカーだとちょっと辛いかも。
天の滝への道の様子。急傾斜で道もやや荒れている。スニーカーだとちょっと辛いかも。
 1
1
1/26 15:20
天の滝への道の様子。急傾斜で道もやや荒れている。スニーカーだとちょっと辛いかも。
 次は太郎・次郎滝を見に夏狩へ。
次は太郎・次郎滝を見に夏狩へ。
 1
1
1/26 15:29
次は太郎・次郎滝を見に夏狩へ。
 道すがらに出会った社号不詳のお宮。道祖神・月待塔が立つ。
道すがらに出会った社号不詳のお宮。道祖神・月待塔が立つ。
 1
1
1/26 15:33
道すがらに出会った社号不詳のお宮。道祖神・月待塔が立つ。
 耕雲院入口の石仏群。
耕雲院入口の石仏群。
 1
1
1/26 15:34
耕雲院入口の石仏群。
 <身禄堂>
<身禄堂>
名もなき祠を見つつ東へ進んでいくと民家の一角に寄りかかるような塚状の高台に稲荷社と小さなお堂がある。実はこれは桂溶岩流の末端にあたるそう。お堂の名前は富士講の食行身禄から取られているのだろう。
 1
1
1/26 15:34
<身禄堂>
名もなき祠を見つつ東へ進んでいくと民家の一角に寄りかかるような塚状の高台に稲荷社と小さなお堂がある。実はこれは桂溶岩流の末端にあたるそう。お堂の名前は富士講の食行身禄から取られているのだろう。
 お堂の脇には様々な道祖神や石仏が保存されている。特に双体道祖神などは味わい深い。
お堂の脇には様々な道祖神や石仏が保存されている。特に双体道祖神などは味わい深い。
 1
1
1/26 15:35
お堂の脇には様々な道祖神や石仏が保存されている。特に双体道祖神などは味わい深い。
 案内を辿り太郎・次郎滝へ。こちらは天の滝とは違い柄杓流川まで舗装路で下りられる。
案内を辿り太郎・次郎滝へ。こちらは天の滝とは違い柄杓流川まで舗装路で下りられる。
 1
1
1/26 15:36
案内を辿り太郎・次郎滝へ。こちらは天の滝とは違い柄杓流川まで舗装路で下りられる。
 こんな所にも馬頭観音。
こんな所にも馬頭観音。
 1
1
1/26 15:36
こんな所にも馬頭観音。
 本流に辿り着くまでに既に断崖からの潜流瀑が楽しめる。
本流に辿り着くまでに既に断崖からの潜流瀑が楽しめる。
 1
1
1/26 15:37
本流に辿り着くまでに既に断崖からの潜流瀑が楽しめる。
 <太郎・次郎滝>
<太郎・次郎滝>
名前の由来はさておき、先ほど歩いた住宅地の真裏に見事な断崖と滝まで形成されている事に驚く。十分に見応えのする光景だけど水量がもっと多い時に来ると水飛沫が気持ちよさそう。
 1
1
1/26 15:38
<太郎・次郎滝>
名前の由来はさておき、先ほど歩いた住宅地の真裏に見事な断崖と滝まで形成されている事に驚く。十分に見応えのする光景だけど水量がもっと多い時に来ると水飛沫が気持ちよさそう。
 <東桂駅>
<東桂駅>
最寄りの東桂駅に引き返し行動終了。
 1
1
1/26 15:47
<東桂駅>
最寄りの東桂駅に引き返し行動終了。




















 へるにゃん
へるにゃん













 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手































































































































































































































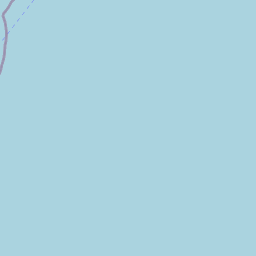






















いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する