ペテガリ岳西尾根~ルベツネ山~1600峰~ヤオロマップ岳~1839峰~コイカクシュサツナイ岳~札内川ヒュッテ

- GPS
- 128:00
- 距離
- 38.6km
- 登り
- 3,141m
- 下り
- 3,005m
コースタイム
(天気:晴れ 行動時間:3時間50分/8:50~12:40)
第2日目 8/2(日) ペテガリ山荘~1050m~1293m~1301m~ペテガリ岳~1647m~1535m鞍部~ペテガリCカール△
(天気:曇りのち雨 行動時間:9時間/4:40~13:40)
第3日目 8/3(月) ペテガリCカール~1535m鞍部~ルベツネ南峰~ルベツネ山△
(天気:雨のち止む 行動時間:2時間/15:00~17:00)
第4日目 8/4(火) ルベツネ山~1688m~1600m~1569m~ヤオロマップ岳△
(天気:晴れ一時ガス 行動時間:10時間45分/4:30~15:15)
第5日目 8/5(水) ヤオロマップ岳~1839峰~ヤオロマップ岳~ヤオロの窓~コイカクシュサツナイ岳~コイカク夏尾根の頭△
(天気:晴れのちガス 行動時間:9時間20分/4:50~11:10、 14:00~17:00)
第6日目 8/6(木) コイカク夏尾根の頭~上二股~コイカクシュサツナイ沢出合~札内川ヒュッテ [下山]
(天気:晴れ 行動時間:5時間10分/5:10~10:20)
| 過去天気図(気象庁) | 2009年08月の天気図 |
|---|---|
| アクセス | |
| コース状況/ 危険箇所等 |
<コースのポイント> ・ペテガリ山荘まで 浦河町の神威岳の登山口である神威山荘手前500mほどに林道分岐がある。分岐は連続して2箇所あるが、奥の方の分岐を左折する。ニシュオマナイ川へ下り渡渉するとまた林道が分岐する。正規には真っ直ぐ川沿いを行くが、左折して植林帯のブル道を山の方に登っても、沢の源頭手前で合流する(聞いた話なので未確認)。渡渉を繰り返すが踏み跡は明瞭でテープもしつこく付いている。沢の源頭手前で尾根へ急登する明瞭な踏み跡があるが、これを行くと先のブル道に合流してしまい、登山口に戻ってしまうので惑わされないこと。正規ルートは忠実に沢をたどる。峠に出たあとは、すぐに下るのでなく稜線上を少し右に歩いてから下るので注意。ここも赤テープが付いているので迷うことはないだろう。 旧静内町からアプローチする林道はゲート閉鎖でここ数年使えない。その理由は日高横断道路が建設中止となり、無駄になった大規模工事を人目に触れさせたくないからだと言われている。理由はどうあれ、ペテガリ岳はますます遙かなる山となっている。 ・ペテガリCカールと水場 日高三大カールというのがあるそうだ。幌尻七つ沼カール、カムエク八ノ沢カール、ペテガリCカールだそう。Cカールもその名にふさわしい美しく快適な泊まり場である。日高のカールはどこでもそうだろうが、稜線からカールへの下りが急峻で注意を要する。Cカールへも非常に厳しい道だ。分岐は1535mコルのぴったりその場所にあり、古い赤テープの目印もあるがあまり目立たない。根曲がりのヤブにつかまりながら下降するが、踏み跡がわかりにくいので注意。ガス時で迷ったときは若干右方向に下るとよい。多少迷っても空地に行き当たるので問題ない。テントサイトの標高は1440mくらいである。サイトは状態が良いのが2箇所、難ありも含めると4箇所くらいある。水場へは更に10分ほど下る。正面の岩場方向ではなく、右方向へ続くお花畑の中の踏み跡を下ってゆく。すぐにハイマツのヤブになるが、更に下ると急な沢地形になり、低いダケカンバのハードなヤブになる。岩がコケで滑りやすいので十分注意。これにめげずにしばらく下ると、水がたっぷり湧き出している場所に出る。エキノコックスの心配もないので、安心して飲める。汲みにくいのでコップも持ってゆくと良い。 ・1839峰 1839峰については、ここ数年で急激に登りやすくなったようである。国境稜線と比較にならないほどの濃いヤブで苦労したという2001年の記録もある。一般民が通れるようになったのはここ5、6年の話だと思われる。大ブレイク中のようで、今回も1839を目指す4パーティと会った。今後も登りやすい状態が続くと思われるが、ヤオロマップからはかなり長くそこそこヤブもあるので、十分な体力が必要である。稜線上にはいくつか滑落注意のポイントがあり、特に山頂直下の草付の直登は油断はならない。大人数の場合はロープ携行が望ましいと思う。 ・ヤオロマップ岳頂上の水場 山頂からコイカク方面にほんの少し下ると防風壁のある立派なテントサイトがある。サイトから右(十勝側)に踏み跡があり、これを下ると7~8分で沢地形に出る。滑りやすく急だがヤブはほとんど無い。更に少し下ると小さな窪地に出る。この窪地の中に足元の岩の間から細く水が流れ出しているところが2箇所ほどある。水は冷たくて非常にうまい。もちろんエキノコックスフリー。こんな急な斜面に水が湧いているのは驚きである。コップやビニール袋がないと汲めないので要注意。日照りが続くと涸れるかもしれない。窪地から更に下るともう少し水量が多いところがあるらしい(未確認)。 ・稜線上のビヴァーク場所 1301m~ペテガリの鞍部(2張)、ペテガリ山頂(1張)、ルベツネ山頂(なんとか1張)、1688m~1600m間鞍部のやや北(2張)、1600m山頂(1張)、1569m山頂(1張)、ヤオロマップ山頂(3張)、ヤオロの北の1752m山頂(1張)、ヤオロの窓(2張)、コイカク山頂(2張)、コイカク夏尾根の頭(2張)、夏尾根1305m地点(2張)。 <ヤブについて> ひどかった順番に下記に記す。 ①1600m峰→ヤオロマップ この区間が最もひどく、思い出したくもない。ハイマツ、ダケカンバ、ネマガリダケのジャングル。特に1569m峰前後は身動きすら取れなくなるほどで、はかどらない行程にストレスがたまる。時間は6時間かかると見ておいた方がよい。逆走ならば1時間くらいマイナスか。危険な箇所はあまりないので、体力と気力だけの問題である。 ②ルベツネ→1600m峰 悪名高き「りんご畑」だけあって低木ダケカンバのひどいヤブだが、時間は思ったよりかからない。良く探せばヤブに弱点があるのが①との大きな違い。この間4時間ほど。逆走の場合はプラス1~2時間だろう。特に1688mまでの登りがかなりつらそうである。 ③ペテガリ岳→ルベツネ山 1535mコル→ルベツネ南峰のハイマツは深いところで首まであり、尋常でなくきつい。所々、ハイマツの上を渡ることになるが、足を踏み外したときに頭から突っ込むので、リカバリーが大変である。逆ルートの場合は枝の方向が順目になるのでだいぶ楽だろう。ペテガリ~ルベツネはどちらに向かうにも4時間見ておけば良い。 ④ヤオロマップ⇔1839峰 全体的にハイマツとダケカンバのヤブが濃いが、①②③ほど極端にひどい場所は無いように思った。時間は両方向とも荷を十分軽くして3時間ほど。 ⑤ヤオロの窓→コイカク 濃いハイマツ帯で、短い区間だがかなり苦労する。ただこちらも逆ルートの場合は楽だろう。 快適な(?)ヤブ漕ぎに当たっては、丈夫なズボンと軍手は必携。上下長袖。また、ヘルメットがあると頭から強引に突っ込めるので重宝する。ザックカバーもあると良い(松ヤニでべとべとになる)。 <その他の注意点> ・ヒグマについて フンは至る所にあり、この山域には所構わず生息していると思われる。怖いことは怖いが、一般的な注意事項をしっかり守っていればまず大丈夫だろう。特にゴミや食料は、においが出ないように袋に入れ、ザックにしまってから寝るのを忘れてはならない。不意の遭遇を避けるためのホイッスルは必携。また、カール内はヒグマがいる確率が高いので、降りる前に十分確認する必要がある。 ・虫について 日高は虫が非常に多い。注意を要するのはダニ、アブ、ブヨである。ペテガリ山荘までの沢登りとペテガリ西尾根はダニが非常に多く、時々体に付いていないか点検した方がよい。首筋に付くことが多いので、襟のある服やタオルを首に巻くなどで防ぐ。標高の低い沢沿いはアブも多い。稜線上に出るとブヨが非常に多く、休憩もままならないほど。防虫ネットも欲しいところである。また、虫の活動が鈍い早朝に行動すると比較的快適である。 |
写真
感想
第1日目 8/1(土) 神威山荘手前林道分岐~ニシュオマナイ川渡渉点~ベッピリガイ沢出合~ペテガリ山荘△
(天気:晴れ 行動時間:3時間50分/8:50~12:40)
前日に静内のビジネスホテルに宿泊し、朝一のJRで荻伏駅に到着。途中東静内と春立の間で列車が鹿と衝突し立ち往生したため到着が少し遅れた。すでに駅には予約したタクシーが着いているかと思ったが、誰もいない。会社に連絡してみると、こちらに来る途中事故にあったそうで、遅れているそうだ。実は前日も飛行機が遅れ、その後のバスも遅れ、危うく静内までたどり着けないところだった。ただでさえ心配事の多い日高の縦走なのに、幸先悪いスタートでなんとなく気分が悪い。天気も夏の日高ではおなじみの霧雨でジメジメしている。
タクシーは15分ほど遅れて到着。神威橋奥のゲートまでお願いするが、ゲートが開いていたら神威山荘まで行ってくれと頼んだ。20分ほど走り上野深集落を過ぎるとダートになる。運転手さんに、「山の中は意外と晴れてるんじゃないですか?」と聞いたら、「いや~どこもかしこも毎日霧雨だよ」と言っていた。でも、ダートに入ってしばらくすると見る見るうちに晴れてきた。運転手さんは「兄ちゃんの言うとおりになったな~」と感心していた。ゲートは予想通り施錠はしていなかったので、神威山荘の手前まで入ってもらった(料金9040円)。
山荘の500mほど手前に林道分岐があり、ここが現在ペテガリ岳の登山口になっている。元々は旧静内町からペテガリ山荘まで車で入れたのだが、日高横断道路の建設が中止になってから何故か林道は通行止めになっている。建設中止の責任問題を過熱させないための苦肉の策だとの噂だ。林道分岐を川のほうに下っていくと間もなく渡渉点になる。ここはまず横着して登山靴で渡渉したが岩で足が滑ってコケてしまい、いきなり水浸しになった。カメラも濡れて不調になったため、この日はこの後写真が1枚も撮れなかった。川を渡ってすぐに沢シューに履き替えた。
渡渉後すぐにニシュオマナイ川の支流に入るが目印も踏み跡もかなりしっかりしている。渡渉を繰り返しながら登ってゆくが、水量は少なくヤブもあまり無く、快適に進む。途中、大きな滝がある。ここは右岸を巻き、非常に急なので注意が要るが、それ以外はほとんど問題になるところは無かった。沢の源頭手前で左の尾根にはっきりした踏み跡を見つけこれを登ることにした。非常に急だがすぐに稜線に出る。だが踏み跡はその後南へと続いているため、おかしいなと思って沢まで引き返した。そのまま沢沿いを進むことにしたが、こちらにも目印が付いており、正しい道のようだった。やがて沢に水は無くなり、峠に出た。峠の向こうへも相変わらずピンクテープが続いており、安心して歩ける。ベッピリガイ沢に向けて下るとすぐに沢に水が流れ出し、やがて踏み跡は沢から右手にはずれ、突如林道に出た。
ここからは1時間ちょっと炎天下の林道をひたすら歩きつづる。林道も所々渡渉があるため登山靴には履き変えなかった。やがて三角屋根の大きなペテガリ山荘に無事到着した。この日は道迷いがあって30分ほどロスしたが、それを含めても4時間かからない行程だった。初日としては体力の消耗も少なく、上々の出来であった。
実は私は約30年ほど前の小学校1~2年の時、旧静内町に住んでいたことがある。このときに父親他数名とペテガリ岳の登山に挑戦している。途中の1293mピークまでで撤退したが、そのときにもペテガリ山荘に泊まった(当時はここまで車で入れた)。記憶もおぼろげだが、山荘は近年建て替えられたらしく、明らかに立派になっていていて驚いた。沢から徒歩で峠越えをしないとたどり着けない山奥の小屋にしてはあまりにも立派過ぎると思ってしまう。しばらく一人だったが夕方にペテガリから4パーティが降りてきた。単独行3名と2名のパーティ。皆さん秋田、栃木、静岡、大阪と内地の方であり、ペテガリ西尾根のピストン狙いである。せっかく遠くから日高まで来たのに、日高らしくない西尾根なんかで満足せずに、縦走でもすればいいのにと思うのだが、皆200名山ピークハントが目的のようであった。
試しに今日迷った箇所のはっきりした踏み跡について皆に聞いてみた。すると、なんと3パーティの方がやはり間違いの踏み跡に引き込まれてしまったとのこと。おかしいと思いながらもずんずん進むと、なんとスタートの渡渉点に戻ってしまったらしい! おかげで初日は7時間行動になってしまったそうだ。どうやら分岐までは2本の登山路があるのだそう。まさか真夏の好天日にリングワンデリングするとは思わなかったとのこと(笑)。引き返した自分は幸いだった。
その後、神威山荘からは誰も登ってこず、明日は一人でペテガリに登ることになった。栃木のパーティが今日は西尾根で2回もヒグマを見たとのことで早速びびる。しかし、ヒグマの問題は日高では開き直って腹をくくるしかない。気休めかもしれないが、熊鈴と呼子も持っている。7時過ぎには就寝し明日のハードな行程に備えた。
第2日目 8/2(日) ペテガリ山荘~1050m~1293m~1301m~ペテガリ岳~1647m~1535m鞍部~ペテガリCカール△
(天気:曇りのち雨 行動時間:9時間/4:40~13:40)
今日は天気は下り坂だそうだが、行程はなだらかな西尾根で安全である。Cカールまでたどり着けば安全地帯で水も確実に取れる。可能な限り早立ちで早めに到着したい。とはいっても一人ではヒグマが怖いのでライトを使わなくて良いくらいに明るくなってから出発する。
小学校2年の時以来、30年ぶりの西尾根再訪であるが、景色の記憶はほとんど無い。ただ、最初にある1050mピークを越えたところの笹の急斜面は記憶にあった。先を歩いていた父親が、登山道にあった大きな浮石を笹の急斜面にゴロゴロと転がしたことを思い出した。静内町の小中学校では大抵校歌にペテガリ岳が謳われている。しかし、当然のことながらこの難しい山を実際登った小学生などほとんどいない。当時、自分もペテガリに挑戦というだけで相当話題になった記憶がある。1293mピークから先は初めての道である。北には1839峰が見え、正面には綺麗な三角形のペテガリ岳とおにぎり型のルベツネ山が見えてきたが、徐々にガスがかかるようになる。国境稜線のヤオロマップ岳はすでにどす黒い雲の中に入ってしまっている。天気はゆっくりと下り坂だ。
登山道はアップダウンを繰り返すので1301mピークがなかなか近づかず疲れる。ようやく1301mを超えると最後の標高差500m以上の直登だ。2日目とあってまだ荷物も20キロある。半端でなくつらい。ゆっくり登るが、森林限界上では風が強くなり、横殴りに雨も降りだした。一気に全身濡れてしまったが、気温が高いのがまだ幸いしている。フラフラになって誰もいないペテガリ山頂(1736m)についた。何とか雨は止んだが、いつまた降り出すか分からない。あこがれの遥かなるペテガリ岳ではあったのだが、休憩も早々に国境稜線を進むことにした。
ところが、国境稜線に入るや否や、濃いハイマツ漕ぎに悩まされることになり、一気にスピードが落ちた。1647m鞍部からはハイマツは薄くなったが、日高・十勝の両側が切れ落ち、非常な緊張感を強いられる。藪が無ければ北アルプスの大キレットに等しい困難度だ。日高山脈は基本的に国境稜線に登山道は無い。弾力のあるハイマツに何度も押し戻されるハードなヤブ漕ぎが続く。更にルベツネ山周辺は日高ヒダと呼ばれるほどのナイフリッジが続き、滑落すれば大変なことになる。もちろんこれらは重々承知で入山しているのだが、そのことが意味する重大さをようやくこのとき体感し始めた。この先ただ事では済まない。緊張感で押しつぶされそうになりながら、苦しい登降を続ける。
1535m鞍部にCカールへの分岐がある。赤テープがあるが、少々分かりにくいため、途中で拾った残置スリングを岩に巻き付けた。分岐というより、足元を覆っているクマザサに穴があいているような感じで、まるでマンホールの中へと降りてゆくような急峻さだ。父親からもカールバントには十分注意するようアドバイスされていたが、雨が降っているのもありスリップしまくる。あまりに急でこれは明日登り返しが出来ないのではと不安になるが今は下るしかない。おまけに途中で踏み跡を完全に見失った。一面濃いガスの藪の中を注意深く下ってゆくと、突如岩の点在するポッカリとした空地に飛び出した。鞍部から標高にしてちょうど100m下った場所、難行軍ではあったが稜線からの所要時間はわずか10分ほどであった。ここが噂に聞くペテガリCカールである。
Cカールには3張ほどテントサイトがあり、外界の天気の荒れようが信じられないほど無風地帯で静かだ。稜線上の厳しさを考えるとまさに天国のように快適な場所。チングルマが満開、ナキウサギの声もカール壁にこだましており、標高がわずか1440mの場所だとは到底信じられない。すぐにテントを設営し、右方向に続く踏み跡を下って沢に水を汲みに行った。わずか10分ほど下ると湧き水がたっぷり出ているが、この10分がまたとてつもなくハードだ。途中ではヤブ漕ぎをたっぷりさせられ、びしょぬれになった。その上源頭の沢地形に入ると非常に急で、スリップ要注意。日高の稜線での水取りはどこでも非常な苦労を要する。懸垂下降の必要が無いだけ、まだマシと思うべきだろう。
天候はいったん落ち着いて、夜には風は全く無くなった。携帯サイトも繋がるので天気を確認すると明日8/3は曇りで8/4は曇り時々晴れだった。だが、その後は当初の予報より悪くなっており、8/5は雨になっていた。これを見て完全に意気消沈した。今日の難路には精神的にもかなり参っていた。この先は相当天気の条件が良くないと進めないであろう。滑りやすいナイフリッジが続くルベツネ山周辺では当然雨の中の行動はNG、視界があり、風が弱いことがMust条件だ。エスケープはペテガリ東尾根を考えていたが、この天気ではかえって遭難する恐れもある。確実なのは来た道を忠実を下って、ペテガリ山荘まで戻ることだ。進むか戻るかは五分五分だろうと覚悟し、この日は眠りについた。
濃いガスに包まれ、無風で恐ろしいほど静かな夜だった。ヒグマの不安から何度か目を覚まし、そのたびに我に返ったように呼子を吹くのだった。
第3日目 8/3(月) ペテガリCカール~1535m鞍部~ルベツネ南峰~ルベツネ山△
(天気:雨のち止む 行動時間:2時間/15:00~17:00)
夜10時を過ぎた頃から雨が降り始めた。翌3時に起床して一応朝食を取ったが、雨は止む気配が無い。天気予報は曇りのままなので、天気悪化は一時的なものだろうと見ていたが、待てど暮らせど雨は止まない。完全に予報は外れた。気温もかなり下がっており、寒くて外に出る気がしない。仕方ない、停滞じゃ~。この日はありったけの服を着込み、寝ることに専念した。相変わらずCカールは静寂でとてもよく眠れる。さわさわと降る雨の中、ナキウサギの声がときどき甲高く響く。
午前中に一度雨は止んだが、午後になるとまた降りだした。ジメジメのテントの中で悶々としながら予定を考えてみる。今後の天気を考えると、どう見てもこの先進むのは負け戦だった。しかし、だからといってやれるところまでやらずに撤退するのも悲しい。撤退できないところまで突っ込んで遭難するのは愚かだが、まだ余裕があるのに撤退するのもまた愚かだ。そう、どんなに悪条件が重なったとしても、ルベツネ山までは行けるはずなのだ。「明日は最低でもルベツネまで行ってから引き返そう」 そういう結論になった。
ところが、2時を過ぎると雨が止み急に気温が上がってきた。見ると上空には太陽も少し見え始めている。こうなると、上の天気が気になってくる。「そうだ、ルベツネにテントを張ろう」と急に思い立った。事前の調査でルベツネ山頂はかろうじてテントが張れるとの情報を得ていた。風も弱い。まさかこの天気では先着者もいるまい。ひょっとすると山頂は雲海の上かもしれない。善は急げと大急ぎでテントをたたんだ。出発前に再び非常な苦労をして水を汲みに行き、全ての水筒を満タンにした(4リットル)。こうして24時間以上滞在したCカールを後にした。
カールバントの登りは壮絶を極めた。どう考えても45度以上ある滑りやすい岩の斜面を直登である。普通に考えると登れるわけが無い。しかし、ここには笹のブッシュという強力な助っ人がある。これをありったけの腕力で掴みながら止まらずに登るのである。きついが休むことは不可能だ。手で笹に掴まっていないと落ちてしまう。20分間必死に格闘を続け、マンホールから這い上がるようにしてようやく稜線に飛び出した。あまりの安堵感にザックを下ろして横になった。天気はどんどん良くなっており、青空も見え出している。これはしてやったりだった。
1535mコルからはしばらく転落注意の細い稜線が続く。少し登ると、北大スキー部の遭難碑があった。2名の名前と「ペテガリよ永遠なれ 昭和35年8月2日この地に逝く」とある。8/2とは昨日ではないか。手を合わせて再び碑に目を向けると、横の岩場に見慣れない花が咲いている。よくよく見てみるとカムイビランジではないか! 写真でしか見たことはなかったが、特徴的なのですぐに分かった。日高の固有種なのだが、その日高の中でもカムエクやエサオマンなど限られた場所でしか見られない貴重な花だ。ルベツネにもあるとの情報をWEBでは見ていたが、まさか本当にあるとは思わなかった。この碑を設けた人達は、逝った両君の手向けにカムイビランジをと思ったのかもしれない。
ルベツネ南峰が近づくと稜線は広くなり安全になるが、ハイマツが一気に押し寄せてくる。ここのハイマツは全行程で一番すごかった。翌日のダケカンバ・ネマガリ混合のヤブも酷かったがハイマツ単体では1535mコル→ルベツネ南峰が最も壮絶であった。所々、どうやっても通れないので、ハイマツの上を渡るが、足を踏み外すと顔から突っ込む。ザックが覆い被さり、なかなか起き上がれずえらいことになる。途中でザックにつけた熊鈴が無くなっていることに気づいた。ヤブに引っ張られたのだろう。尾瀬で買った高価なものだったが、とても戻って探す気にはなれない。仕方なく前進する。非常な苦難の末、ようやくルベツネ南峰(1720m)に着いた。ここからルベツネ山(1727m)までは少しハイマツの丈が低くなり、あまり時間はかからず到着した。Cカールからわずか2時間だったが、体力的には1つの山に登ったほどのハードワークだった。
ルベツネの山頂は非常に狭く、北と東は絶壁である。テントも本当に「かろうじて」張れる状態だった。チングルマの株の上に張ることになるが、スペースが無いので仕方が無い(内地でこんなことをやったら大問題だろう)。狭くて張るのには苦労したが、出来上がってみると床はフカフカで凸凹もいい具合で快適に寝られそうだった。
登頂後しばらく1839峰が雲海の上に顔を出していた。すごい山だと改めて思った。高峰が並ぶ国境稜線からずいぶんと外れているにもかかわらず、このあたりで1800mの標高を越える山は皆無であり、異常に目立つのだ。最近は東京からのツアーも入るほどポピュラーになり、WEBでも何かと大注目なのだが、その理由も十分納得である。それにしても、こんなすごい山を見落としている日本300名山の選定眼には疑問を抱かざるを得ない。
寝る前に、明日はこのまま進むべきだと思い直した。間違いなく明日8/4の天気は良い。あさって8/5は雨だが、その次の8/6は晴れである。8/5はヤオロ山頂で停滞を余儀なくされるかもしれないが、その場合でも予備日の8/6に下山することは十分可能だし、無理のない計画である。これはどう考えても進むべきだろう。今日の朝にはほぼ撤退と考えていたのに山での心理状態は本当に微妙で不思議なものだ。天気と同じである。ただ、ルベツネでテントを張ろうと思ったその決断がものをいったのは確かだ。山頂でテントを張れるという情報を事前に得ていたことも大きい(これを知らなければこの日は行動しなかっただろう)。情報戦の勝利である。いずれにしても、やはり簡単にあきらめるものではない。あきらめなければ道は開けることも本当にあるのだ。
ただ唯一不安だったのは、ヤオロマップ頂上の水場で水が取れるかどうかだった。手持ちの水で行動できるのは頑張ってあと2日間だ。ヤオロから南に日高側の斜面をかなり下ると水が取れるとの情報もあったが、懸垂下降用のロープが無いので無理も出来ない。山頂の水が出ていることをとにかく祈るだけだった。
第4日目 8/4(火) ルベツネ山~1688m~1600m~1569m~ヤオロマップ岳△
(天気:晴れ一時ガス 行動時間:10時間45分/4:30~15:15)
3時に起き、テントの外を眺めると信じられない光景が広がっていた。4日目にして初めて見た快晴の国境稜線の大展望である。あまりの美しい光景に全く言葉を失った。北はヤオロマップと1839峰、カムエク、遠くはエサオマンや札内岳、勝幌も見えている。南はやはりすぐそばのペテガリ岳の三角形が素晴らしい。神威や遠くには楽古と思われる鋭鋒も確認できる。日本アルプスでさえもこんなに延々と続く緑の大山脈は見たことがない。日高の国境稜線付近で今まで登ったのは幌尻岳とピパイロ岳、そして南日高の楽古岳だが、残念ながら天気がイマイチでここまでの展望は無かった。生涯で初めて間近に見た、日高核心部の眺めである。
ご来光と共に出発する。太陽が出るとまた山肌が素晴らしい色合いに変わる。刻々と変わる大絵巻に感動しきりであるが、あまり気を取られてはおれない。今日は全行程でおそらく最も危険なところを歩く。スタート直後のルベツネの頂上直下が特に危ない。ルートは急な下りの上、日高側も十勝側もすっぱりと切れ落ちたナイフリッジが1688峰まで続いている。ここは細心の注意を払ったが、幸いにもヤブのおかげで恐怖感はそれほどでもなかった。1688までは比較的ヤブが薄くスピードは速い。しかし、その後1469へ高度を下げてゆくとヤブがどんどん濃くなり、ぐんとスピードが落ちた。特にダケカンバの低木が厄介で、この区間はりんご畑と揶揄されている。大きなザックを背負っていると、引っかかりまくるので、めんどくささが倍増する。
ところが苦労した割には比較的行程ははかどり、距離的に中間の1600峰には8時20分に到着した。ここまで4時間半と見ていたのだが、4時間を切るスピードで、順調な滑り出しであった。あまり苦もなく到達できた感じだったが、ずいぶんと暑くなってきたのが気になる。1600峰は国境稜線が直角に折れ曲がる重要なポイントにあり、非常に目立つ鋭鋒である。個人的には名前が付いていても良いくらいの名山と思うのだが、標高の低さが災いしてか、全く注目されていない。山頂は狭いが、ルベツネよりは快適にテントを張れるスペースもあり、焚き火の跡もあった。泊まるにも気持ちの良いピークであるが、風が吹くと相当しんどい場所ではあるだろう。
1600峰で大休止後、西に90°進路を変えて次のピーク1569峰に向かう。通常の登山道なら30分ちょっとの距離であるが、WEBではこの区間が最も激ヤブで、3時間かかるとの情報を得ていた。恐れおののきながらの前進である。中間点の最低コルまでは下りなのもあって比較的順調に進んだが、その後突然ペースが急激に落ちた。ハイマツ、ダケカンバ、ネマガリダケが複雑に絡み合ったブッシュ帯である。その酷さは筆舌に尽くしがたい。通常、ヤブの中でも探しているうちに比較的弱点を見つけられることが多いのだが、この区間はそういったケースは全く無い。一様に濃いブッシュだ。チエノワを解くようにブッシュを分解しながら進む。それもままならないときは強引に突っ込むが大抵押し戻される。こうなると泣きそうである。おそらくは獣さえも全く通らない稜線なのではなかろうか。
更に悪いことに、気温が高くなって熱中症の気も出始めた。熱中症は一度山形の朝日連峰でとんでもない目にあっている。こんなところで倒れたら大変なことになるので、意識的に日陰での休憩を多くする。そうすると更にペースが落ちるという悪循環になってしまう。これがもし登山口のそばなら引き返したかもしれない。しかし、既に半分の行程を越えた今となっては、何が何でもヤオロに到達せねばならない。とにかく頭を空っぽにしてヤブをかき分け続ける。
1569峰直下では、尾根上のダケカンバ帯を避けて南斜面を巻いたところ、びっしりと絡み合った背丈以上のネマガリダケに全く身動きが取れなくなり、本当に焦った。もがいても何をしてもその場から動けないあの恐怖は忘れがたい。苦難の末何とか見つけた獣道に這い上がり、安堵のため息をついた。
それでも正午過ぎになんとか1569m峰に到達した。昼飯を食って大休止するがあまりの暑さに意識が朦朧としている。ブッシュの日陰で体温を下げたあと、再び意を決しヤブに体を入れてゆく。1569からヤオロマップの最低鞍部は距離的にはすぐであるが、ここの区間もヤブはMax状態の酷さである。ヤオロの登りになると岩場が多くなり、ヤブ漕ぎは減る。しかし今度は登りがきついので体感的には楽になった感じが全くしない。ますます休憩は多くなる。幸いにも山頂が近くなると一時的にいい具合にガスが湧き出し風も吹いて、一気に涼しくなった。これをチャンスとばかりに頑張って登り、ついにヤオロマップ岳(1794m)の山頂に到達した。目標は10時間以内だったが、大幅にオーバー。カッパは松やにまみれでベトベトで穴もあいた。昨日にはカッパのズボンのゴムも切れてしまったので、即席で細引きでサスペンダーを作って応急処置した。ヨレヨレのヘロヘロで実にみっともない姿だが、今はただただ安堵感と充実感でいっぱいである。この縦走で一番困難な核心部をついに越えたのだ。
テント設営後、何はともあれ水を汲みに行く。事前調査どおり山頂から20mほど北側の立派なテントサイトから、十勝側の斜面にはっきりした踏み跡が付いていた。かなりの急傾斜なので慎重に下ってゆくが、Cカールとは違いヤブがあまり無いので比較的楽だ。7~8分ほどで明瞭な沢に入ると、すぐに小さなくぼ地のような場所に出る。ここの足元の岩の間から少量であるが水が染み出している。水量は思ったより多く、コップを当てると15秒ほどでいっぱいになる。何度も繰り返してすくい、水筒4リットルを満タンにした。驚くほど冷たい水で、まろやかで実にうまかった。
山頂に戻ったところで、3日ぶりに人に会った。1839峰に登ってきたところだそうだ。ヤオロ山頂の少し北の1752ピークにテントを張っているそうで、今日はそこまで戻るそうである。ヤブの状態を聞くと普通程度だそうで、思ったより楽そうだ。特に今日の激ヤブをクリアしている自分にとっては多分あまり問題はないだろう。ただ明日は雨なのだ。1839は今回は残念ながらお預けとしようと涙を飲む。ところが、最新の天気予報を確認してみると、なんと曇り時々晴れに変わっているではないか! 今までツキにも見放されていたが、ここへきてようやく運気も上がってきたようだ。こうなったらもう1839峰にも行ってしまうしかない!!
ヤオロマップ岳の山頂は東は絶壁だが、それ以外は緩斜面なので広広としているように感じる。山頂そばのテントサイトも岩で囲われており、天候が荒れてもおそらく安全だろう。実に気持ちの良いところである。そして大注目の眺めはやはり1839峰である。ヤオロ山頂から見る姿は南アルプスの北岳とそっくりであり、非常に登行欲をそそる。明日がとにかく楽しみである。風もなく暖かく穏やかな夜になった。緊張感からも開放され、久しぶりに泥のように眠った。ヒグマ対策のホイッスルもだんだん面倒になって吹かなくなった。腹が据わってきたといえばいいのか… もう俺を食うなら食えという感じだ。
第5日目 8/5(水) ヤオロマップ岳~1839峰~ヤオロマップ岳~ヤオロの窓~コイカクシュサツナイ岳~コイカク夏尾根の頭△
(天気:晴れのちガス 行動時間:9時間20分/4:50~11:10、 14:00~17:00)
朝、天気予報よりも天気はずいぶん良く、雲は出ているが晴れている。暑くなりそうだ。昨日よりは余裕のある行程ではあるが、早立ちすることにした。
1839峰への尾根に入ると2~3分ほどで広いテントサイトがあった。山頂よりも安全な所で、悪天時はこちらのほうがよいかもしれない。途中の1781mピークまではアップダウンも少なく、ヤブも低く、非常に快適である。眺めはルベツネ山の姿が特にいい。麓の沢の険悪さもよく分かる。日高側はカンゾウの花が満開で、一面お花畑であった。その後も花が多く、白いシオガマ、白いフウロなど珍しいものもある。1839峰は花の名山であることも認識した。そして更に言うと、この山はヒグマの痕跡が非常に濃い。新鮮なフンも至るところにあり、びびりながら歩いてゆく。1781ピークを越えるとルートはかなり下り、その後細かなアップダウンを繰り返す。昨日のヤブを思わせるほどの難路も少々出てくるが、何より今日はピストンなので荷が軽い。体力の消耗度合いが昨日とは全然違う。ただ思ったより距離が長く、全てのピークは巻かずに完全に稜線上を行くのできつい。1770mの偽ピークを越えてもまだ残りが長くてガックリ。その後ようやく本峰に取り付くが、急な岩場の直登であり、手がかりも怪しい草付きでかなり危険である。ロープが欲しいほどの箇所なので、厳格な3点確保で慎重に進む。今回の縦走中、最も危険な箇所はここであった。調べたら過去に滑落死亡事故も起きていて、この山はロープ非携行で登るにはちょっと酷ではないかとも感じた。登山者も増えており、フィクスロープ設置が望まれるが、公式には登山道はないことになっているためそれも無理であろう。いずれにしろ、何があっても自分で責任を持つ覚悟が必要だ。
ヤオロマップから2時間20分で1839峰(1842m)に到着した。眺めは素晴らしく、この縦走中最高の景色だったといってよい。その理由はこの山が国境稜線からおおきく外れているからである。重なり合って全貌が分からない山々が分解されて構造が非常に良く分かる。特にここから見るカムイエクウチカウシ山は超一級品である。このように南西稜が翼を広げるように大きく張り出している姿は1839からか、もしくは幌尻岳から見るのが最適である(父親談)。そして、その東のピラミッド峰、更に東に並ぶ1823峰がとても立派なことに驚く。1839、1823といった無名峰でここまで立派な山は、北海道以外ではありえないだろう。コイカクシュサツナイ岳の曲線的で重厚な姿も良い。南方向には今まで歩いてきたペテガリ西尾根からヤオロマップまでの稜線が全て見渡せた。長い行程を振り返ると感慨深く、Cカールで停滞していたのが遠い昔のことのように思えた。とにかく見飽きることのない景色に、1時間以上の長い休憩となってしまった。
下りは慎重に行く。例の危険箇所は慎重すぎるくらい気を使った。暑いのもあり、休憩を取りながら行くと往路よりも長く、3時間かかってヤオロマップ岳まで戻った。昨日以上に暑く、空身にも関わらずヘロヘロである。雲が湧いてきたがなかなか太陽がさえぎられるほどには成長しない。このままコイカクシュサツナイ岳に向かうと熱中症になりそうなので、夕方に行動することにして休んだ。コイカクまでは危険な箇所は全くないので、到着が多少遅くなっても大丈夫なはずである。しばらく靴下や濡れたものを乾かしながらウダウダする。そして、もう一度水場まで下り、水筒を満タンにすると共に、その場で1リットルほども飲み干してしまった。細いながらも水量は一定で、相当日照りが続かないと枯れないのではないかと思う。
14時近くになるとコイカク方面がガスに覆われてきたので、テントをたたみ出発することにした。ヤオロマップ岳~ヤオロの窓は完全なる登山道でヤブ漕ぎはほとんどない。景色も非常によく、花も多く、久しぶりの快適な道にルンルン気分である。この間はいたるところにナキウサギがおり、チーチーという鳴き声があちこちから聞こえる。ヤオロの窓は歴舟川の支流のヤオロマップ右沢が函状となって国境稜線まで突き上げている、壮絶な箇所である。日高の沢の険悪さを思い知らされる。ここにも快適なテントサイトがあるが、水場がある分ヤオロマップ山頂のほうが勝っているだろう。
ヤオロの窓を過ぎるとコイカクシュサツナイ岳山頂までハイマツのハードなヤブ漕ぎが続く。ここもペテガリ~ルベツネに準ずるほど酷いのだが、この縦走最後のヤブ漕ぎでもあるので、もう終わりだと思うと心理的には楽だ。傾斜は緩いが、無風で暑く意外ときつい。休みながらゆっくり登るが、なんとか十分明るいうちにコイカクシュサツナイ岳(1721m)の山頂に着いた。快適なテントサイトもあるが、濃いガスに包まれ、今ひとつパッとしないので、夏尾根の頭まで行くことにする。途中には有名な北大山岳部のケルンがある。「コイカクに逝ける友を偲んで」と標識があり、酒瓶が供えてある。夏尾根の頭(1719m)にはサイトが2箇所あり、コイカク山頂よりも顕著なピークなので眺めは良かった。これ以上下ると明日は国境稜線からの風景を拝めなくなるので、ここにテントを張ることにする。周りは一面のお花畑である。ラストを飾るにふさわしいピークだ。暑かったのもあり、ヤオロからは3時間かかった。
念のため、明日の下山路を確認してからテントに入った。夏尾根のルートが転がり落ちるように沢に吸い込まれているのを見ると少し不安になった。その先に続くコイカクシュサツナイ沢も自分にとっては未知の世界である。でもここから先は登山道なのだ。そう思うといくらか安心だった。予備日までフルに使うことになったので、親に電話連絡することにした。電波は問題なく、すぐに繋がった。コイカク山頂に無事でいること、1日延びて下山するが体調その他全く問題ないことを伝えた。
最後のレトルト食品である牛丼をペロリとたいらげた。米もほぼなくなった。あとは行動食で食いつなぐしかないが、量は十分はあるし、遅くとも明日の午前中には下山できるはずだった。今日は1839狙いの人に何人か会うだろうと予想していたが、結局誰にも会わなかった。最終的に国境稜線上で会った人は昨日の一人だけである。こんなに人に会わない山旅は南ア白峰南嶺と深南部を2002年に6日間かけて縦走したとき以来だ。連日緊張にさらされ正直苦しかったが、一方で楽しくて仕方がなかったことも事実。やはり静かな山が自分には向いている。
第6日目 8/6(木) コイカク夏尾根の頭~上二股~コイカクシュサツナイ沢出合~札内川ヒュッテ [下山]
(天気:晴れ 行動時間:5時間10分/5:10~10:20)
最後の朝である。昨夜の濃いガスは見事に取れており、快晴の中のご来光となった。名残惜しいが、国境稜線の眺めを見納め、夏尾根を下ることにする。コイカクからの眺めもやはり1839峰が最も印象的で、昨日は北岳に見えたが、ここからは塩見岳そっくりだった。6日間、常に1839峰に見守られながら歩んでいた感が強い。愛着も大きく思い出の山となった。
コイカクの夏尾根は北アルプス3大急登など目でないほどの急峻さである。標高差は1000mあり、1箇所を除いてほとんど傾斜は緩まない。上部は滑落事故も起きているほど危険なので慎重に行く。北の対岸の1643峰と1823峰が大迫力で望まれるが、足元が危ないので気が気ではない。2~3箇所ほど北西側がすっぱり切れ落ちたところを通過せねばならないが、その後ルートは落ち着いてくる。それにしてもヤブが無いって何て楽なんだろう。急傾斜一辺倒なので、信じられないほどの早さで標高が下がる。体調はすこぶる良いので一時平坦になる1305m地点でも休まずに一気に上二股まで下ることにする。上二股直前で笹原に出て道が少し分かりにくくなるが、適当に目印のテープを探しながら歩くと、ちょうど沢の分岐に出た。登りの時は少々分かりにくいので注意がいるだろう。やや左股方面に入ってから右折する格好になる。ここまでわずか1時間45分というハイペースだった。
ここでたてつづけに4パーティーに遭遇。皆1839狙いだそうだ。内地からのツアーの5人客もおり、改めて1839峰の人気爆発ぶりを認識した。皆一様にヤブ漕ぎのハードさを気にしていたが、それよりもこの暑さでは心配事は水である。ヤオロ頂上の水場の場所を教え、コップを持ってゆくように伝えた。ペテガリから縦走してきたというと皆目を丸くしていた。道はあるのかと聞かれたので、無いですと答えた。
上二股では久しぶりに豊富な水が得られたので、ココアや味噌汁を作ったりして大休止した。沢シューに履き替えて出発。コイカクシュサツナイ沢は河原が広く、滝がひとつも無いという、日高では希少価値の簡単な沢だ。もはやこれは沢登りではなく、ただの川歩きである。渡渉も今日のような晴天下では全て膝下で全く問題ない。2箇所だけ函になっている箇所があり、このうち下流のほうは腰までの深さなので、右岸の巻き道を通ったほうが良い。問題になるところはそれくらいである。広い河原では太陽がじりじり照り付けるのでわざと水の中に入って歩く。大きな砂防ダムは右岸を巻き、更にずんずん行くとやがて札内川本流沿い(コイカク沢出合)の立派な鉄橋が見えてくる。左岸のコンクリート堰堤のハシゴを登ると林道に抜けられ、林道から鉄橋の上に行けるようになっている。立派な鉄橋の正体はあの悪名高き日高横断道路だ。あとは10分ほどこの道路を歩く。トンネルを抜けたところにこじんまりとした札内川ヒュッテがあり、ここがゴールである。何事も無く無事に下山でき、とにかくホッとした。
早く下山できたので、ヒュッテで休みがてらテントや寝袋を乾かしたりして、荷物を整理した。すると札内川ダムの利用調査を行っている人がやってきた。これは推測であるが、ダムの周辺を整備して観光客を呼ぶしか頓挫した日高横断道路の活用方法が無いのであろう。全く壮大なる無駄遣いもいいところである。簡単なアンケートに答えたあと、色々と無駄話をした。テントも乾きさて出発しようとしたら、なんと山岳センターまで車で送ってくれるという。携帯が通じないのでタクシーを呼ぶために山岳センターまであと8キロ炎天下の車道を歩かねばならなかった。大感謝でお礼を言いまくりだった。一応念のため仕事中なのではないかと確認したら、「ヒマだから別にいいですよ」とのこと(笑)。
山岳センターで下山報告をし、そのあとシャワーを浴びられるかと思ったら、朝と夕方しかやっていないとのこと。仕方ないので体を拭いて着替えるだけにした。センター内には「ぴよろ」というかわいい名前のレストランもある。ここで中札内産豚肉のハンバーグ定食をたいらげたが、とてもうまかった。人気の食堂らしくたくさんの家族連れで賑わっていた。タクシーを呼び、車が来るまでの間、山岳展示室を見学した。ここには有名な昭和45年カムエク八ノ沢カールのヒグマ遭難事故の遺品など、貴重なものが展示されている。これらを見ると、北アルプスと共に日高も遭難に次ぐ遭難の歴史だったことがわかる。特に札内川十ノ沢の雪崩遭難は壮絶であった。リーダーはデブリの中で4日間生きつづけて遺書を書き綴ったのだが、これはまさに松濤明の「風雪のビバーク」の再現である。直筆の遺書のあまりの生々しさに、頭痛がして気がめいってきた。
タクシーで中札内の市街地まで出た(5400円)。祖父の記念館のある「六花の森」を見学したあと、バスで帯広に出て、JR特急「おおぞら」で札幌まで帰ってきた。実家に着いたのは夜9時で疲労困憊だったが、考えてみればこの日の朝はコイカクの頂上で寝ていたわけだから、すごいものである。眠いにもかかわらず、この日は父親と日高談義で盛り上がり、寝たのは日が変わる直前であった。こうしてペテガリ岳~1839峰~コイカクシュサツナイ岳という壮大な縦走を終えた。

 triglav
triglav













 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手









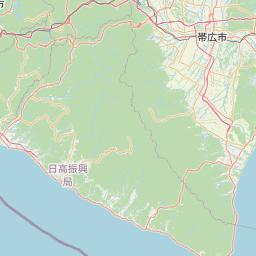
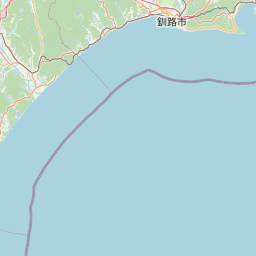

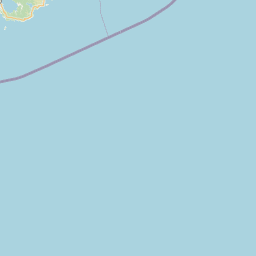















いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する