 【安全登山の広場①】
【安全登山の広場①】
6時54分、JR土樽駅に近い「安全登山の広場」に到着します。駐車スペースは20台ほどです。トイレはありませんが、すぐそばに水場があります。この日駐車していたのは私だけでした。
 2
2
5/24 6:54
【安全登山の広場①】
6時54分、JR土樽駅に近い「安全登山の広場」に到着します。駐車スペースは20台ほどです。トイレはありませんが、すぐそばに水場があります。この日駐車していたのは私だけでした。
 【安全登山の広場②】
【安全登山の広場②】
谷川連峰登山道整備に尽力された「ヒゲさん」こと高波吾策氏の立派な胸像があります。ここは越後側からの谷川連峰登山の起点となる場所です。
 2
2
5/24 6:54
【安全登山の広場②】
谷川連峰登山道整備に尽力された「ヒゲさん」こと高波吾策氏の立派な胸像があります。ここは越後側からの谷川連峰登山の起点となる場所です。
 【万太郎山登山口へ向かう】
【万太郎山登山口へ向かう】
7時03分、支度を整えてから歩き始めます。まずは車道をしばらく歩いて「吾策新道」登山口へ向かいます。
 0
0
5/24 7:03
【万太郎山登山口へ向かう】
7時03分、支度を整えてから歩き始めます。まずは車道をしばらく歩いて「吾策新道」登山口へ向かいます。
 タニウツギを眺めながら、舗装道路を歩きます(^^)
タニウツギを眺めながら、舗装道路を歩きます(^^)
関越自動車道をくぐった先に、少しだけ砂利道区間があります。
 9
9
5/24 7:12
タニウツギを眺めながら、舗装道路を歩きます(^^)
関越自動車道をくぐった先に、少しだけ砂利道区間があります。
 【吾策新道駐車場に到着】
【吾策新道駐車場に到着】
7時35分、吾策新道の駐車場に到着です。駐車スペースは10台程度です。この奥には舗装道路が続いていますが、大きな石が置かれて車が入れないようにしてありました。
 2
2
5/24 7:35
【吾策新道駐車場に到着】
7時35分、吾策新道の駐車場に到着です。駐車スペースは10台程度です。この奥には舗装道路が続いていますが、大きな石が置かれて車が入れないようにしてありました。
 「安全登山の広場」からこの吾策新道駐車場まで、徒歩で30分ほどでした。駐車場の奥へと歩き続けます。
「安全登山の広場」からこの吾策新道駐車場まで、徒歩で30分ほどでした。駐車場の奥へと歩き続けます。
 0
0
5/24 7:36
「安全登山の広場」からこの吾策新道駐車場まで、徒歩で30分ほどでした。駐車場の奥へと歩き続けます。
 【万太郎山・登山口】
【万太郎山・登山口】
7時40分、舗装道路を歩いていると、右側に登山口を示す道標が出てきました。ここから登山開始です。標高差1350mを一気にかせぐダイナミックなコースです!
 0
0
5/24 7:40
【万太郎山・登山口】
7時40分、舗装道路を歩いていると、右側に登山口を示す道標が出てきました。ここから登山開始です。標高差1350mを一気にかせぐダイナミックなコースです!
 最初はブナと杉の混合林です。わりと急登です。
最初はブナと杉の混合林です。わりと急登です。
 0
0
5/24 7:45
最初はブナと杉の混合林です。わりと急登です。
 登山道の様子はこんな感じ。日陰で湿り気がありますが、まあ普通です(^^;)
登山道の様子はこんな感じ。日陰で湿り気がありますが、まあ普通です(^^;)
 4
4
5/24 7:45
登山道の様子はこんな感じ。日陰で湿り気がありますが、まあ普通です(^^;)
 ほぼ視界が利かない登山道を黙々と歩き続けます。誰にも会いません。
ほぼ視界が利かない登山道を黙々と歩き続けます。誰にも会いません。
 0
0
5/24 8:01
ほぼ視界が利かない登山道を黙々と歩き続けます。誰にも会いません。
 【序盤・ガマンの時間】
【序盤・ガマンの時間】
「何ぁ~んにも見えない…」
万太郎山の序盤はガマンの時間です(*_*)
 2
2
5/24 7:49
【序盤・ガマンの時間】
「何ぁ~んにも見えない…」
万太郎山の序盤はガマンの時間です(*_*)
 「おぉ、タムシバが咲いてますね♪」我慢の登山が続いていますが、花が咲いていることが唯一の救いです。
「おぉ、タムシバが咲いてますね♪」我慢の登山が続いていますが、花が咲いていることが唯一の救いです。
 23
23
5/24 8:10
「おぉ、タムシバが咲いてますね♪」我慢の登山が続いていますが、花が咲いていることが唯一の救いです。
 8時24分、「舟窪(ふなくぼ)」の手前まで来ると、雪道が始まります。
8時24分、「舟窪(ふなくぼ)」の手前まで来ると、雪道が始まります。
 0
0
5/24 8:24
8時24分、「舟窪(ふなくぼ)」の手前まで来ると、雪道が始まります。
 雪面はコチコチに堅くなっています。トレースはありません。ツボ足のままキックステップで登り続けます。
雪面はコチコチに堅くなっています。トレースはありません。ツボ足のままキックステップで登り続けます。
 3
3
5/24 8:27
雪面はコチコチに堅くなっています。トレースはありません。ツボ足のままキックステップで登り続けます。
 【舟窪・ルートミス①】
【舟窪・ルートミス①】
残雪のせいでしょうか。いつの間にかルートを見失い、ヤブの急斜面を登る羽目になります。「あちゃー、どこでどう間違えたんだろう…」
 2
2
5/24 8:34
【舟窪・ルートミス①】
残雪のせいでしょうか。いつの間にかルートを見失い、ヤブの急斜面を登る羽目になります。「あちゃー、どこでどう間違えたんだろう…」
 【舟窪・ルートミス②】
【舟窪・ルートミス②】
GPSで確認すると、夏道とはやや外れたルートを歩いていることが分かりました。何とか夏道の方へ修正しようとすると、嫌らしい雪のトラバースにぶつかり、ここで軽アイゼンを履きました。
 5
5
5/24 8:40
【舟窪・ルートミス②】
GPSで確認すると、夏道とはやや外れたルートを歩いていることが分かりました。何とか夏道の方へ修正しようとすると、嫌らしい雪のトラバースにぶつかり、ここで軽アイゼンを履きました。
 【舟窪・ルートミス③】
【舟窪・ルートミス③】
固くなった雪面のトラバース、そして木の枝をつかんでの急斜面の登りで、時間と体力を奪われます。
 1
1
5/24 8:46
【舟窪・ルートミス③】
固くなった雪面のトラバース、そして木の枝をつかんでの急斜面の登りで、時間と体力を奪われます。
 【舟窪手前・要注意①】
【舟窪手前・要注意①】
8時50分、ようやく夏道に戻りました。とは言いましても、なかなかの急登が続き…
 1
1
5/24 8:50
【舟窪手前・要注意①】
8時50分、ようやく夏道に戻りました。とは言いましても、なかなかの急登が続き…
 【舟窪手前・要注意②】
【舟窪手前・要注意②】
そしてヒザ上までの踏み抜きです。まったく踏んだり蹴ったりです(*_*)
 5
5
5/24 8:53
【舟窪手前・要注意②】
そしてヒザ上までの踏み抜きです。まったく踏んだり蹴ったりです(*_*)
 【舟窪手前・要注意③】
【舟窪手前・要注意③】
後方を振り返ります。ご覧下さい、GPSによるとこんなトラバースが夏道なのです。「う~ん、もしGPSとアイゼンが無かったら敗退するとこだった…」
 10
10
5/24 8:57
【舟窪手前・要注意③】
後方を振り返ります。ご覧下さい、GPSによるとこんなトラバースが夏道なのです。「う~ん、もしGPSとアイゼンが無かったら敗退するとこだった…」
 やれやれ、どうにか困難な場所をパスできたようです。イワウチワを見ながら、少し落ち着きます(^^)
やれやれ、どうにか困難な場所をパスできたようです。イワウチワを見ながら、少し落ち着きます(^^)
 34
34
5/24 8:59
やれやれ、どうにか困難な場所をパスできたようです。イワウチワを見ながら、少し落ち着きます(^^)
 【舟窪を通過】
【舟窪を通過】
9時00分、無事に「舟窪(1300m)」を通過します。登山口からはここまで1時間20分で、想定したよりも時間がかかりました。先ほどのルートミスのせいです。
 1
1
5/24 9:00
【舟窪を通過】
9時00分、無事に「舟窪(1300m)」を通過します。登山口からはここまで1時間20分で、想定したよりも時間がかかりました。先ほどのルートミスのせいです。
 「舟窪」からは新緑の爽やかなブナ林を歩きます。この先で雪道も終わりました。アイゼンをはずします。
「舟窪」からは新緑の爽やかなブナ林を歩きます。この先で雪道も終わりました。アイゼンをはずします。
 3
3
5/24 9:01
「舟窪」からは新緑の爽やかなブナ林を歩きます。この先で雪道も終わりました。アイゼンをはずします。
 雲が晴れてきましたね…
雲が晴れてきましたね…
 2
2
5/24 9:02
雲が晴れてきましたね…
 「舟窪」からは稜線上、ゆるやかな斜面を登ると徐々に視界が開けてきます。ガマンの時間もようやく終わりです(^^)
「舟窪」からは稜線上、ゆるやかな斜面を登ると徐々に視界が開けてきます。ガマンの時間もようやく終わりです(^^)
 2
2
5/24 9:11
「舟窪」からは稜線上、ゆるやかな斜面を登ると徐々に視界が開けてきます。ガマンの時間もようやく終わりです(^^)
 右手側、奥に『仙ノ倉山(2026.2m)』が見えてきました。
右手側、奥に『仙ノ倉山(2026.2m)』が見えてきました。
 7
7
5/24 9:13
右手側、奥に『仙ノ倉山(2026.2m)』が見えてきました。
 樹林帯を抜けて稜線に出ました。岩混じりのやせ尾根が始まります。すぐ先で小ピーク「P1450」、その先「大ベタテノ頭」を通過します。
樹林帯を抜けて稜線に出ました。岩混じりのやせ尾根が始まります。すぐ先で小ピーク「P1450」、その先「大ベタテノ頭」を通過します。
 1
1
5/24 9:18
樹林帯を抜けて稜線に出ました。岩混じりのやせ尾根が始まります。すぐ先で小ピーク「P1450」、その先「大ベタテノ頭」を通過します。
 【ようやく展望が開ける】
【ようやく展望が開ける】
ここでようやく展望が開けました。まだ遠目の風景になるのですが、岩の上に上がって周りを見回してみます。
 2
2
5/24 9:19
【ようやく展望が開ける】
ここでようやく展望が開けました。まだ遠目の風景になるのですが、岩の上に上がって周りを見回してみます。
 ●
●
*9時19分・高度1450m付近
こちらは南の方角。中央のピークが『万太郎山(1954.1m)』です。
 18
18
5/24 9:19
●
*9時19分・高度1450m付近
こちらは南の方角。中央のピークが『万太郎山(1954.1m)』です。
 ●●
●●
*右のピーク、主脈となる稜線上に『エビス大黒ノ頭(1888m)』が見えます。
 2
2
5/24 9:19
●●
*右のピーク、主脈となる稜線上に『エビス大黒ノ頭(1888m)』が見えます。
 ●●●
●●●
*左のピークが谷川連峰最高峰『仙ノ倉山(2026.2m)』、中央の奥にちょこんと『平標山(1983.7m)』が顔を覗かせています。
 26
26
5/24 9:19
●●●
*左のピークが谷川連峰最高峰『仙ノ倉山(2026.2m)』、中央の奥にちょこんと『平標山(1983.7m)』が顔を覗かせています。
 ●●●●
●●●●
*こちらは西の方角。左奥に白く平たいピーク『苗場山(2145.3m)』、手前は『日白山(1631m)』『タカマタギ(1529.2m)』などが連なる稜線だと思います。
 8
8
5/24 9:19
●●●●
*こちらは西の方角。左奥に白く平たいピーク『苗場山(2145.3m)』、手前は『日白山(1631m)』『タカマタギ(1529.2m)』などが連なる稜線だと思います。
 ●
●
*9時21分・高度1450m付近
中央の奥に『巻機山(1967m)』、が見えます。
 3
3
5/24 9:21
●
*9時21分・高度1450m付近
中央の奥に『巻機山(1967m)』、が見えます。
 ●●
●●
*中央の一番高いピーク『茂倉岳(1977.9m)』、そのすぐ右隣に一段低く見えるのが『一ノ倉岳(1974.2m)』…
 10
10
5/24 9:21
●●
*中央の一番高いピーク『茂倉岳(1977.9m)』、そのすぐ右隣に一段低く見えるのが『一ノ倉岳(1974.2m)』…
 ●●●
●●●
*写真左端のピーク『谷川岳・トマノ耳(1963m)』、中央の少し左『オジカ沢ノ頭』…
 2
2
5/24 9:21
●●●
*写真左端のピーク『谷川岳・トマノ耳(1963m)』、中央の少し左『オジカ沢ノ頭』…
 ●●●●
●●●●
*そして中央のピーク『万太郎山(1954.1m)』です。
 5
5
5/24 9:21
●●●●
*そして中央のピーク『万太郎山(1954.1m)』です。
 さて、痩せ岩場を進みます。左側は切れ落ちているため注意です…
さて、痩せ岩場を進みます。左側は切れ落ちているため注意です…
 1
1
さて、痩せ岩場を進みます。左側は切れ落ちているため注意です…
 このショウジョウバカマは「鮮やかなピンク色」をしていました♪
このショウジョウバカマは「鮮やかなピンク色」をしていました♪
 18
18
5/24 9:26
このショウジョウバカマは「鮮やかなピンク色」をしていました♪
 【大ベタテノ頭を通過】
【大ベタテノ頭を通過】
9時27分、「大ベタテノ頭(1470m)」を通過します。標柱がありませんので、どこがピークかは分かりません(^^;)
 0
0
5/24 9:27
【大ベタテノ頭を通過】
9時27分、「大ベタテノ頭(1470m)」を通過します。標柱がありませんので、どこがピークかは分かりません(^^;)
 「大ベタテノ頭」からは鞍部へと下り、傾斜のきつい岩混じりの道を登ることになります。
「大ベタテノ頭」からは鞍部へと下り、傾斜のきつい岩混じりの道を登ることになります。
 1
1
5/24 9:31
「大ベタテノ頭」からは鞍部へと下り、傾斜のきつい岩混じりの道を登ることになります。
 ●
●
*大ベタテノ頭から鞍部へと下る途中、『万太郎山(1954.1m』の全体がよく見えました。
 0
0
5/24 9:32
●
*大ベタテノ頭から鞍部へと下る途中、『万太郎山(1954.1m』の全体がよく見えました。
 ●●
●●
*左のピーク『オジカ沢ノ頭』、右のピーク『大障子ノ頭』になります。
 0
0
5/24 9:32
●●
*左のピーク『オジカ沢ノ頭』、右のピーク『大障子ノ頭』になります。
 ●●●
●●●
*こちらが『万太郎山(1954.1m)』です。手前から尾根が左へと続き、中腹で右に折り返して山頂へ向かっています。その折り返した辺りが『井戸小屋沢ノ頭』です。
 11
11
5/24 9:32
●●●
*こちらが『万太郎山(1954.1m)』です。手前から尾根が左へと続き、中腹で右に折り返して山頂へ向かっています。その折り返した辺りが『井戸小屋沢ノ頭』です。
 ●●●●
●●●●
 0
0
5/24 9:32
●●●●
 それにしても『万太郎山』、想像以上にハードだなぁ…
それにしても『万太郎山』、想像以上にハードだなぁ…
 6
6
5/24 9:34
それにしても『万太郎山』、想像以上にハードだなぁ…
 大ベタテノ頭から鞍部へと下る斜面では、タムシバが咲き誇っていました♪
大ベタテノ頭から鞍部へと下る斜面では、タムシバが咲き誇っていました♪
 25
25
5/24 9:37
大ベタテノ頭から鞍部へと下る斜面では、タムシバが咲き誇っていました♪
 タムシバ、そしてその奥に万太郎山。キレイでした~(^^)
タムシバ、そしてその奥に万太郎山。キレイでした~(^^)
 5
5
5/24 9:36
タムシバ、そしてその奥に万太郎山。キレイでした~(^^)
 さて、鞍部を越えるとそこから先はやや急峻な登りが始まります(*_*)
さて、鞍部を越えるとそこから先はやや急峻な登りが始まります(*_*)
 0
0
5/24 9:45
さて、鞍部を越えるとそこから先はやや急峻な登りが始まります(*_*)
 登山道の左「井戸小屋沢」側は切れ落ちています。注意しながら歩き続けます…
登山道の左「井戸小屋沢」側は切れ落ちています。注意しながら歩き続けます…
 2
2
5/24 9:46
登山道の左「井戸小屋沢」側は切れ落ちています。注意しながら歩き続けます…
 前方の様子です。ここから左に見えるガレ気味の急斜面を登りきったピークが『井戸小屋沢ノ頭』になります。そこからさらに右へ進み、『万太郎山』山頂を目指します。
前方の様子です。ここから左に見えるガレ気味の急斜面を登りきったピークが『井戸小屋沢ノ頭』になります。そこからさらに右へ進み、『万太郎山』山頂を目指します。
 4
4
5/24 9:46
前方の様子です。ここから左に見えるガレ気味の急斜面を登りきったピークが『井戸小屋沢ノ頭』になります。そこからさらに右へ進み、『万太郎山』山頂を目指します。
 【注意・ガレた斜面】
【注意・ガレた斜面】
『井戸小屋沢ノ頭』手前のガレた斜面です。ロープを手がかりにゆっくりと高度を上げていきます。
 0
0
5/24 9:53
【注意・ガレた斜面】
『井戸小屋沢ノ頭』手前のガレた斜面です。ロープを手がかりにゆっくりと高度を上げていきます。
 途中からはガレが無くなり、岩場の登りになります。
途中からはガレが無くなり、岩場の登りになります。
 0
0
5/24 9:57
途中からはガレが無くなり、岩場の登りになります。
 おや、これはムラサキヤシオでしょうか?あと少しで満開を迎えそうですね(^^)
おや、これはムラサキヤシオでしょうか?あと少しで満開を迎えそうですね(^^)
 7
7
おや、これはムラサキヤシオでしょうか?あと少しで満開を迎えそうですね(^^)
 イワカガミに励まされながら、慎重に登り続けます。
イワカガミに励まされながら、慎重に登り続けます。
 15
15
5/24 9:56
イワカガミに励まされながら、慎重に登り続けます。
 ようやく岩場を登り切り、そして後方を振り返ります。たどってきた尾根がよく見えました。「たいぶ歩きましたね…」
ようやく岩場を登り切り、そして後方を振り返ります。たどってきた尾根がよく見えました。「たいぶ歩きましたね…」
 3
3
5/24 9:59
ようやく岩場を登り切り、そして後方を振り返ります。たどってきた尾根がよく見えました。「たいぶ歩きましたね…」
 【井戸小屋沢ノ頭に到着】
【井戸小屋沢ノ頭に到着】
10時03分、「井戸小屋沢ノ頭」に到着です。目指す『万太郎山』がまた一段と大きくなりました。
 3
3
5/24 10:03
【井戸小屋沢ノ頭に到着】
10時03分、「井戸小屋沢ノ頭」に到着です。目指す『万太郎山』がまた一段と大きくなりました。
 ●
●
*「井戸小屋沢ノ頭」にて『万太郎山』方面を見回します。奥に『茂倉岳』『谷川岳』が続く稜線が見えます。今日はあそこまで行くつもりですが、かなり遠いですね…(^^;)
 7
7
5/24 10:04
●
*「井戸小屋沢ノ頭」にて『万太郎山』方面を見回します。奥に『茂倉岳』『谷川岳』が続く稜線が見えます。今日はあそこまで行くつもりですが、かなり遠いですね…(^^;)
 ●●
●●
*左のピーク『オジカ沢ノ頭』、中央のピーク『大障子ノ頭』です。
 1
1
5/24 10:04
●●
*左のピーク『オジカ沢ノ頭』、中央のピーク『大障子ノ頭』です。
 ●●●
●●●
*『万太郎山(1954.1m)』です。実際のピークはギザギザの一番左端のさらに奥になります。ここからまだまだ岩稜歩きが続きそうです。
 5
5
5/24 10:04
●●●
*『万太郎山(1954.1m)』です。実際のピークはギザギザの一番左端のさらに奥になります。ここからまだまだ岩稜歩きが続きそうです。
 ●●●●
●●●●
*ずっと奥に『苗場山(2145.3m)』が見えます。見える位置がずいぶん変わりましたね。
 1
1
5/24 10:04
●●●●
*ずっと奥に『苗場山(2145.3m)』が見えます。見える位置がずいぶん変わりましたね。
 「井戸小屋沢ノ頭」を示す標柱はだいぶ痛んでいました。
「井戸小屋沢ノ頭」を示す標柱はだいぶ痛んでいました。
 1
1
5/24 10:05
「井戸小屋沢ノ頭」を示す標柱はだいぶ痛んでいました。
 万太郎山登山口からこの「井戸小屋沢ノ頭」まで、およそ2時間25分でした。さて、進みます…
万太郎山登山口からこの「井戸小屋沢ノ頭」まで、およそ2時間25分でした。さて、進みます…
 1
1
5/24 10:05
万太郎山登山口からこの「井戸小屋沢ノ頭」まで、およそ2時間25分でした。さて、進みます…
 【注意・第2のガレ場】
【注意・第2のガレ場】
10時08分、「井戸小屋沢ノ頭」からすぐ先に、またもやガレ場が現れます。急斜面な上に小石がゴロゴロしていて、登るのに手こずりました(*_*)
 0
0
5/24 10:08
【注意・第2のガレ場】
10時08分、「井戸小屋沢ノ頭」からすぐ先に、またもやガレ場が現れます。急斜面な上に小石がゴロゴロしていて、登るのに手こずりました(*_*)
 ガレ場をパスして進むと、かわいらしいシラネアオイに出会えました~(^^)
ガレ場をパスして進むと、かわいらしいシラネアオイに出会えました~(^^)
 28
28
5/24 10:14
ガレ場をパスして進むと、かわいらしいシラネアオイに出会えました~(^^)
 【鋸歯のごとき岩峰群①】
【鋸歯のごとき岩峰群①】
10時24分、山頂直下の岩峰群への登りが始まりました。
 1
1
5/24 10:24
【鋸歯のごとき岩峰群①】
10時24分、山頂直下の岩峰群への登りが始まりました。
 【鋸歯のごとき岩峰群②】
【鋸歯のごとき岩峰群②】
この岩斜面は高度感があります。ですが、それほど長くは続きません。
 1
1
5/24 10:25
【鋸歯のごとき岩峰群②】
この岩斜面は高度感があります。ですが、それほど長くは続きません。
 【鋸歯のごとき岩峰群③】
【鋸歯のごとき岩峰群③】
両足の奥には『仙ノ倉山』が見えます。一歩一歩、慎重に足を運びます…
 2
2
5/24 10:27
【鋸歯のごとき岩峰群③】
両足の奥には『仙ノ倉山』が見えます。一歩一歩、慎重に足を運びます…
 そしてこの岩場に来てようやくシャクナゲに出会えました♪
そしてこの岩場に来てようやくシャクナゲに出会えました♪
 31
31
5/24 10:33
そしてこの岩場に来てようやくシャクナゲに出会えました♪
 ●
●
*10時35分、岩峰に登り切ったところの様子です。こちらは後方、たったいま写真左下に見える登山道を登ってきました。
 0
0
5/24 10:35
●
*10時35分、岩峰に登り切ったところの様子です。こちらは後方、たったいま写真左下に見える登山道を登ってきました。
 ●●
●●
*左手側には、この後で歩くことになる主脈の稜線が続いています。
 2
2
5/24 10:35
●●
*左手側には、この後で歩くことになる主脈の稜線が続いています。
 ●●●
●●●
*こちらが進行方向です。ここから先は、いくつかの小ピークを右から巻いて進みます。
 0
0
5/24 10:35
●●●
*こちらが進行方向です。ここから先は、いくつかの小ピークを右から巻いて進みます。
 ●●●●
●●●●
 1
1
5/24 10:35
●●●●
 ポツポツと咲いているシャクナゲを横目に見ながら、歩き続けます(^^)
ポツポツと咲いているシャクナゲを横目に見ながら、歩き続けます(^^)
 3
3
5/24 10:37
ポツポツと咲いているシャクナゲを横目に見ながら、歩き続けます(^^)
 前方、小ピークが並んでいる様子が分かります。3つのピークを越えたその先に、主脈縦走路の分岐点があります。
前方、小ピークが並んでいる様子が分かります。3つのピークを越えたその先に、主脈縦走路の分岐点があります。
 1
1
5/24 10:38
前方、小ピークが並んでいる様子が分かります。3つのピークを越えたその先に、主脈縦走路の分岐点があります。
 【マジでツライ…】
【マジでツライ…】
「ちょ、ちょっとタンマ…」小さなアップダウンを歩いていると、息が上がってきました。あの「舟窪」通過時のダメージが響いています(*_*)
 2
2
5/24 10:44
【マジでツライ…】
「ちょ、ちょっとタンマ…」小さなアップダウンを歩いていると、息が上がってきました。あの「舟窪」通過時のダメージが響いています(*_*)
 そして最後の登りがやって来ました。ここを登り切ると主脈縦走路の分岐点になります。「あそこに行ったら休もう…」
そして最後の登りがやって来ました。ここを登り切ると主脈縦走路の分岐点になります。「あそこに行ったら休もう…」
 3
3
5/24 10:47
そして最後の登りがやって来ました。ここを登り切ると主脈縦走路の分岐点になります。「あそこに行ったら休もう…」
 【主脈縦走路・分岐点①】
【主脈縦走路・分岐点①】
10時52分、ようやく「主脈縦走路・分岐点」に到着です!ちなみに万太郎山山頂は、ここから2~3分歩いたところにあります。おや、男女の2人組がいます。「こんにちは~!」
 7
7
5/24 10:52
【主脈縦走路・分岐点①】
10時52分、ようやく「主脈縦走路・分岐点」に到着です!ちなみに万太郎山山頂は、ここから2~3分歩いたところにあります。おや、男女の2人組がいます。「こんにちは~!」
 【主脈縦走路・分岐点②】
【主脈縦走路・分岐点②】
「こんにちは!」このトレランのお二人は『茂倉岳』『谷川岳』を経由し、これから『平標山』へ向かうとのことでした。「朝7時頃に茂倉岳登山口を出発して来たんですよ…」「え、何ですって!?」
 16
16
5/24 10:53
【主脈縦走路・分岐点②】
「こんにちは!」このトレランのお二人は『茂倉岳』『谷川岳』を経由し、これから『平標山』へ向かうとのことでした。「朝7時頃に茂倉岳登山口を出発して来たんですよ…」「え、何ですって!?」
 【主脈縦走路・分岐点③】
【主脈縦走路・分岐点③】
朝7時出発ということは、たった4時間弱でここまで来ているということになります。いや~、世の中には恐ろしい人がいるものです(*_*)「どうか、お気をつけて…!」
 13
13
5/24 10:53
【主脈縦走路・分岐点③】
朝7時出発ということは、たった4時間弱でここまで来ているということになります。いや~、世の中には恐ろしい人がいるものです(*_*)「どうか、お気をつけて…!」
 オレはこの『万太郎山』1つを登るだけで4時間もかかっている…。まったく、自信なくしちゃいますよ(;_;)
オレはこの『万太郎山』1つを登るだけで4時間もかかっている…。まったく、自信なくしちゃいますよ(;_;)
さて、周りを見回してみましょう。
 1
1
5/24 10:56
オレはこの『万太郎山』1つを登るだけで4時間もかかっている…。まったく、自信なくしちゃいますよ(;_;)
さて、周りを見回してみましょう。
 【分岐点からの展望①】
【分岐点からの展望①】
まずは北東の方角。左の手前に『足拍子岳(1408m)』の険しい岩尾根、中央の奥には白く『巻機山(1967m)』、左の奥に『平ヶ岳(2141m)』…
 3
3
5/24 10:57
【分岐点からの展望①】
まずは北東の方角。左の手前に『足拍子岳(1408m)』の険しい岩尾根、中央の奥には白く『巻機山(1967m)』、左の奥に『平ヶ岳(2141m)』…
 【分岐点からの展望②】
【分岐点からの展望②】
そこから右回転、東の方角。手前から谷川連峰の主脈となる縦走路が伸びています。左から『茂倉岳(1977.9m)』『一ノ倉岳(1974.2m)』、そして中央『谷川岳(1963m)』、右奥にうっすらと『武尊山(2158m)』…
 12
12
5/24 10:57
【分岐点からの展望②】
そこから右回転、東の方角。手前から谷川連峰の主脈となる縦走路が伸びています。左から『茂倉岳(1977.9m)』『一ノ倉岳(1974.2m)』、そして中央『谷川岳(1963m)』、右奥にうっすらと『武尊山(2158m)』…
 【分岐点からの展望③】
【分岐点からの展望③】
さらに右回転、南東の方角。左には俎嵓山稜からの稜線が『小出俣山(1749.1m)』へと続いています。
 2
2
5/24 10:57
【分岐点からの展望③】
さらに右回転、南東の方角。左には俎嵓山稜からの稜線が『小出俣山(1749.1m)』へと続いています。
 【分岐点からの展望④】
【分岐点からの展望④】
さらに右回転、南の方角。あのピークが『万太郎山(1954.1m)』となります。ピークはもう目の前です。
 1
1
5/24 10:57
【分岐点からの展望④】
さらに右回転、南の方角。あのピークが『万太郎山(1954.1m)』となります。ピークはもう目の前です。
 ●
●
*さらに西から北の方角を見回しました。こちらは南西の方角。右の手前に見えるのが『エビス大黒ノ頭(1888m)』になります。
 0
0
5/24 10:57
●
*さらに西から北の方角を見回しました。こちらは南西の方角。右の手前に見えるのが『エビス大黒ノ頭(1888m)』になります。
 ●●
●●
*こちらは西の方角。左端に『仙ノ倉山(2026.2m)』、ほぼ中央に『苗場山(2145.3m)』
 2
2
5/24 10:57
●●
*こちらは西の方角。左端に『仙ノ倉山(2026.2m)』、ほぼ中央に『苗場山(2145.3m)』
 ●●●
●●●
*こちらは北の方角。手前にはたったいま歩いてきた「吾策新道」の尾根、その奥には『足拍子岳』などの峰々、さらに『飯士山(1111.5m)』なども見えます。
 0
0
5/24 10:58
●●●
*こちらは北の方角。手前にはたったいま歩いてきた「吾策新道」の尾根、その奥には『足拍子岳』などの峰々、さらに『飯士山(1111.5m)』なども見えます。
 ●●●●
●●●●
*こちらは北東の方角。中央に『茂倉岳(1977.9m)』、すぐ右隣『一ノ倉岳(1974.2m)』、右端に『谷川岳(1963m)』です。
 1
1
5/24 10:58
●●●●
*こちらは北東の方角。中央に『茂倉岳(1977.9m)』、すぐ右隣『一ノ倉岳(1974.2m)』、右端に『谷川岳(1963m)』です。
 さてさて、休憩しましょうか♪
さてさて、休憩しましょうか♪
 2
2
5/24 10:59
さてさて、休憩しましょうか♪
 【分岐点・ランチタイム】
【分岐点・ランチタイム】
谷川岳が見える位置で、ドッコイショと…
 3
3
5/24 10:59
【分岐点・ランチタイム】
谷川岳が見える位置で、ドッコイショと…
 ビール(^^)
ビール(^^)
 16
16
5/24 11:01
ビール(^^)
 おつまみ
おつまみ
 9
9
5/24 11:01
おつまみ
 おにぎり
おにぎり
 10
10
5/24 11:01
おにぎり
 そして大好物のチョコ!
そして大好物のチョコ!
 7
7
5/24 11:02
そして大好物のチョコ!
 【まだまだ遠い…】
【まだまだ遠い…】
しかし、あの谷川岳までけっこう遠いよ。谷川岳のあと茂倉岳まで歩くわけだから、まだまだ時間がかかりそうスね…
 12
12
5/24 11:03
【まだまだ遠い…】
しかし、あの谷川岳までけっこう遠いよ。谷川岳のあと茂倉岳まで歩くわけだから、まだまだ時間がかかりそうスね…
 雲がポッカリ浮かんでる。
雲がポッカリ浮かんでる。
あぁ、なんかいいなぁ…
 2
2
5/24 11:05
雲がポッカリ浮かんでる。
あぁ、なんかいいなぁ…
 ●
●
*おにぎりを食べながら、空を眺めました。
 0
0
5/24 11:06
●
*おにぎりを食べながら、空を眺めました。
 ●●
●●
 2
2
5/24 11:06
●●
 ●●●
●●●
*この時間、「空のブルー」と「雲&残雪のホワイト」が実にキレイでした♪
 2
2
5/24 11:07
●●●
*この時間、「空のブルー」と「雲&残雪のホワイト」が実にキレイでした♪
 ●●●●
●●●●
 0
0
5/24 11:07
●●●●
 セルフで記念撮影。「疲れたけど、これから頑張って谷川岳まで行ってみるよ~!」
セルフで記念撮影。「疲れたけど、これから頑張って谷川岳まで行ってみるよ~!」
 34
34
5/24 11:12
セルフで記念撮影。「疲れたけど、これから頑張って谷川岳まで行ってみるよ~!」
 11時16分、休憩を終えて万太郎山ピークへ向かいます。
11時16分、休憩を終えて万太郎山ピークへ向かいます。
 0
0
5/24 11:16
11時16分、休憩を終えて万太郎山ピークへ向かいます。
 分岐点から万太郎山山頂へは、ほんの2~3分で着きます。左巻きに進みます。
分岐点から万太郎山山頂へは、ほんの2~3分で着きます。左巻きに進みます。
 0
0
5/24 11:17
分岐点から万太郎山山頂へは、ほんの2~3分で着きます。左巻きに進みます。
 この日、「分岐点→万太郎山山頂」区間にシャクナゲが一番多く咲いていました(^^)/
この日、「分岐点→万太郎山山頂」区間にシャクナゲが一番多く咲いていました(^^)/
 9
9
5/24 11:17
この日、「分岐点→万太郎山山頂」区間にシャクナゲが一番多く咲いていました(^^)/
 【万太郎山・山頂到着】
【万太郎山・山頂到着】
11時19分、あっという間に『万太郎山(1954.1m)』山頂に到着です!
 3
3
5/24 11:19
【万太郎山・山頂到着】
11時19分、あっという間に『万太郎山(1954.1m)』山頂に到着です!
 三角点にタッチ
三角点にタッチ
 9
9
5/24 11:23
三角点にタッチ
 万太郎山山頂には、トレランの若い男性が休憩していました。『平標山』から走ってきたそうです。その男性としばらく会話を楽しみました。
万太郎山山頂には、トレランの若い男性が休憩していました。『平標山』から走ってきたそうです。その男性としばらく会話を楽しみました。
 2
2
5/24 11:32
万太郎山山頂には、トレランの若い男性が休憩していました。『平標山』から走ってきたそうです。その男性としばらく会話を楽しみました。
 さて、山頂の奥へ行き仙ノ倉山方面を見てみましょう。
さて、山頂の奥へ行き仙ノ倉山方面を見てみましょう。
 0
0
5/24 11:27
さて、山頂の奥へ行き仙ノ倉山方面を見てみましょう。
 【万太郎山からの展望①】
【万太郎山からの展望①】
まずは南の方角。写真の中心付近に見えるのが『小出俣山(1749.1m)』だと思います。
 1
1
5/24 11:33
【万太郎山からの展望①】
まずは南の方角。写真の中心付近に見えるのが『小出俣山(1749.1m)』だと思います。
 【万太郎山からの展望②】
【万太郎山からの展望②】
そこから右回転、南西の方角。左端から出た尾根が中心付近で左にカーブし、一番高くなった場所がおそらく『東俣ノ頭』…・
 1
1
5/24 11:33
【万太郎山からの展望②】
そこから右回転、南西の方角。左端から出た尾根が中心付近で左にカーブし、一番高くなった場所がおそらく『東俣ノ頭』…・
 【万太郎山からの展望③】
【万太郎山からの展望③】
さらに右回転、西の方角。左に見える鋭いピーク『エビス大黒ノ頭(1888m)』、右の一番高いピークが『仙ノ倉山(2026.2m)』…
 5
5
5/24 11:33
【万太郎山からの展望③】
さらに右回転、西の方角。左に見える鋭いピーク『エビス大黒ノ頭(1888m)』、右の一番高いピークが『仙ノ倉山(2026.2m)』…
 【万太郎山からの展望④】
【万太郎山からの展望④】
さらに右回転、北西の方角。左奥が『苗場山(2145.3m)』になります。
 1
1
5/24 11:34
【万太郎山からの展望④】
さらに右回転、北西の方角。左奥が『苗場山(2145.3m)』になります。
 仙ノ倉山
仙ノ倉山
ズーム写真1
 0
0
5/24 11:34
仙ノ倉山
ズーム写真1
 仙ノ倉山
仙ノ倉山
ズーム写真2
 0
0
5/24 11:34
仙ノ倉山
ズーム写真2
 仙ノ倉山
仙ノ倉山
ズーム写真3
 4
4
5/24 11:34
仙ノ倉山
ズーム写真3
 仙ノ倉山
仙ノ倉山
ズーム写真4
 1
1
5/24 11:34
仙ノ倉山
ズーム写真4
 【万太郎山とお別れ】
【万太郎山とお別れ】
11時34分、万太郎山を後にして『谷川岳』へと歩き始めます。
 1
1
5/24 11:34
【万太郎山とお別れ】
11時34分、万太郎山を後にして『谷川岳』へと歩き始めます。
 シャクナゲを見ながら先ほど休憩した「分岐点」まで戻り…
シャクナゲを見ながら先ほど休憩した「分岐点」まで戻り…
 8
8
5/24 11:37
シャクナゲを見ながら先ほど休憩した「分岐点」まで戻り…
 分岐点からは次のポイント『大障子ノ頭』へと向かいます。まずは標高差230mの鞍部へと下ります。
分岐点からは次のポイント『大障子ノ頭』へと向かいます。まずは標高差230mの鞍部へと下ります。
 3
3
5/24 11:38
分岐点からは次のポイント『大障子ノ頭』へと向かいます。まずは標高差230mの鞍部へと下ります。
 ハイマツですね。この下り斜面で多く見かけました。
ハイマツですね。この下り斜面で多く見かけました。
 0
0
5/24 11:40
ハイマツですね。この下り斜面で多く見かけました。
 男性2人とスライドです。この人たちも谷川岳から主脈を縦走して平標山に行くそうです。みんなすごいなぁ~
男性2人とスライドです。この人たちも谷川岳から主脈を縦走して平標山に行くそうです。みんなすごいなぁ~
 9
9
5/24 11:39
男性2人とスライドです。この人たちも谷川岳から主脈を縦走して平標山に行くそうです。みんなすごいなぁ~
 「万太郎山→大障子ノ頭」区間では、シャクナゲや…
「万太郎山→大障子ノ頭」区間では、シャクナゲや…
 3
3
5/24 11:42
「万太郎山→大障子ノ頭」区間では、シャクナゲや…
 ミヤマダイコンソウ
ミヤマダイコンソウ
 7
7
5/24 11:45
ミヤマダイコンソウ
 ミネザクラなどが咲いていました(^^)
ミネザクラなどが咲いていました(^^)
 4
4
5/24 11:49
ミネザクラなどが咲いていました(^^)
 【池の中の白い物体】
【池の中の白い物体】
「万太郎山→大障子ノ頭」区間の途中、右手側に池が見えました。笹原をかき分けて近くに行ってみると、池の中に何か白いものが見えました。「何だろう…」
 1
1
5/24 11:57
【池の中の白い物体】
「万太郎山→大障子ノ頭」区間の途中、右手側に池が見えました。笹原をかき分けて近くに行ってみると、池の中に何か白いものが見えました。「何だろう…」
 この白い物体はゼリー状でプルンとした感じです。きっと何かの生き物の卵ですね…。私はこういうの苦手です(^^;)
この白い物体はゼリー状でプルンとした感じです。きっと何かの生き物の卵ですね…。私はこういうの苦手です(^^;)
 6
6
5/24 11:59
この白い物体はゼリー状でプルンとした感じです。きっと何かの生き物の卵ですね…。私はこういうの苦手です(^^;)
 登山道に戻って歩き続けると、ハクサンイチゲの群落に出会いました♪
登山道に戻って歩き続けると、ハクサンイチゲの群落に出会いました♪
 22
22
5/24 12:02
登山道に戻って歩き続けると、ハクサンイチゲの群落に出会いました♪
 かわいいですね~(^^)
かわいいですね~(^^)
 23
23
5/24 12:03
かわいいですね~(^^)
 ●
●
*12時09分、「万太郎山→大障子ノ頭」区間の鞍部周辺を歩いています。
 0
0
5/24 12:09
●
*12時09分、「万太郎山→大障子ノ頭」区間の鞍部周辺を歩いています。
 ●●
●●
*前方に『大障子ノ頭(1800m)』が大きく見えてきました。荒々しい感じがします。
 2
2
5/24 12:09
●●
*前方に『大障子ノ頭(1800m)』が大きく見えてきました。荒々しい感じがします。
 ●●●
●●●
*こちらが進行方向です。写真の左が「俎嵓」になります。
 0
0
5/24 12:09
●●●
*こちらが進行方向です。写真の左が「俎嵓」になります。
 ●●●●
●●●●
 0
0
5/24 12:09
●●●●
 ●
●
*同じく「万太郎山→大障子ノ頭」区間の鞍部周辺、右手側の様子を中心に見回します。こちらは後方の風景。左上のピークが『万太郎山(1954.1m)』です。
 0
0
5/24 12:12
●
*同じく「万太郎山→大障子ノ頭」区間の鞍部周辺、右手側の様子を中心に見回します。こちらは後方の風景。左上のピークが『万太郎山(1954.1m)』です。
 ●●
●●
*右手側には笹原が広がっていますが、そこから一気に「大障子沢」へと切れ落ちています。
 1
1
5/24 12:12
●●
*右手側には笹原が広がっていますが、そこから一気に「大障子沢」へと切れ落ちています。
 ●●●
●●●
*こちらがいま向かっている『大障子ノ頭』です。
 0
0
5/24 12:12
●●●
*こちらがいま向かっている『大障子ノ頭』です。
 ●●●●
●●●●
*左のピークが「俎嵓」です。
 0
0
5/24 12:12
●●●●
*左のピークが「俎嵓」です。
 12時18分、『大障子ノ頭(1800m)』への登りが始まります。ゴツゴツした岩の斜面で、灌木や岩をつかみながらゆっくりと登りました。
12時18分、『大障子ノ頭(1800m)』への登りが始まります。ゴツゴツした岩の斜面で、灌木や岩をつかみながらゆっくりと登りました。
 0
0
5/24 12:18
12時18分、『大障子ノ頭(1800m)』への登りが始まります。ゴツゴツした岩の斜面で、灌木や岩をつかみながらゆっくりと登りました。
 そして岩峰を右巻きにして進み、ピークへと向かいます。
そして岩峰を右巻きにして進み、ピークへと向かいます。
 0
0
5/24 12:23
そして岩峰を右巻きにして進み、ピークへと向かいます。
 『大障子ノ頭』ピークの手前で、ハクサンコザクラに出会いました(*^_^*)
『大障子ノ頭』ピークの手前で、ハクサンコザクラに出会いました(*^_^*)
 16
16
5/24 12:25
『大障子ノ頭』ピークの手前で、ハクサンコザクラに出会いました(*^_^*)
 【大障子ノ頭に到着】
【大障子ノ頭に到着】
12時30分、『大障子ノ頭(1800m)』ピークに到着です。狭いピークにポツンと標柱だけが立っています。
 1
1
5/24 12:30
【大障子ノ頭に到着】
12時30分、『大障子ノ頭(1800m)』ピークに到着です。狭いピークにポツンと標柱だけが立っています。
 【大障子ノ頭・後方の風景①】
【大障子ノ頭・後方の風景①】
『大障子ノ頭』から後方「万太郎山方面」を見回しました。
 2
2
5/24 12:32
【大障子ノ頭・後方の風景①】
『大障子ノ頭』から後方「万太郎山方面」を見回しました。
 【大障子ノ頭・後方の風景②】
【大障子ノ頭・後方の風景②】
右端のピークが『東俣ノ頭』で、ほぼ中央のひょっこり出ているのが「P1807」ではないかと思います。
 1
1
5/24 12:32
【大障子ノ頭・後方の風景②】
右端のピークが『東俣ノ頭』で、ほぼ中央のひょっこり出ているのが「P1807」ではないかと思います。
 【大障子ノ頭・後方の風景③】
【大障子ノ頭・後方の風景③】
こちらが『万太郎山(1954.1m)』になります。「吾策新道」から見た様子よりも、こちらから見た山容のほうが私は好きです。
 3
3
5/24 12:32
【大障子ノ頭・後方の風景③】
こちらが『万太郎山(1954.1m)』になります。「吾策新道」から見た様子よりも、こちらから見た山容のほうが私は好きです。
 【大障子ノ頭・後方の風景④】
【大障子ノ頭・後方の風景④】
写真の左端を見ますと、万太郎山の山頂直下にあった「岩峰群」の様子が分かります。
 1
1
5/24 12:32
【大障子ノ頭・後方の風景④】
写真の左端を見ますと、万太郎山の山頂直下にあった「岩峰群」の様子が分かります。
 【大障子ノ頭から進行方向①】
【大障子ノ頭から進行方向①】
さらにこれから向かう谷川岳方面を眺めます。まずは北東の方角。中央に『茂倉岳(1977.9m)』、その右に『一ノ倉岳(1974.2m)』…
 4
4
5/24 12:43
【大障子ノ頭から進行方向①】
さらにこれから向かう谷川岳方面を眺めます。まずは北東の方角。中央に『茂倉岳(1977.9m)』、その右に『一ノ倉岳(1974.2m)』…
 【大障子ノ頭から進行方向②】
【大障子ノ頭から進行方向②】
そこから右回転、東の方角。これからさらに稜線を歩き続けます。中央のピークが『オジカ沢ノ頭』、その左奥に『谷川岳(1963m)』…
 3
3
5/24 12:43
【大障子ノ頭から進行方向②】
そこから右回転、東の方角。これからさらに稜線を歩き続けます。中央のピークが『オジカ沢ノ頭』、その左奥に『谷川岳(1963m)』…
 【大障子ノ頭から進行方向③】
【大障子ノ頭から進行方向③】
さらに右回転、南東の方角。左のピーク『俎嵓(1761m)』、そこから右へ『川棚ノ頭(1845.7m)』『本谷ノ頭(1696m)』が続いています。
 5
5
5/24 12:43
【大障子ノ頭から進行方向③】
さらに右回転、南東の方角。左のピーク『俎嵓(1761m)』、そこから右へ『川棚ノ頭(1845.7m)』『本谷ノ頭(1696m)』が続いています。
 【大障子ノ頭から進行方向④】
【大障子ノ頭から進行方向④】
さらに右回転、南の方角。こちらは『小出俣山(1749.1m)』や『三尾根岳』などです。
 2
2
5/24 12:43
【大障子ノ頭から進行方向④】
さらに右回転、南の方角。こちらは『小出俣山(1749.1m)』や『三尾根岳』などです。
 さて、この『大障子ノ頭(1800m)』からは下って「大障子避難小屋(1675m)」『小障子ノ頭』を経由し、『オジカ沢ノ頭(1890m)』を目指します。
さて、この『大障子ノ頭(1800m)』からは下って「大障子避難小屋(1675m)」『小障子ノ頭』を経由し、『オジカ沢ノ頭(1890m)』を目指します。
 1
1
5/24 12:44
さて、この『大障子ノ頭(1800m)』からは下って「大障子避難小屋(1675m)」『小障子ノ頭』を経由し、『オジカ沢ノ頭(1890m)』を目指します。
 空を仰ぎます。「この先、まだまだアップダウンがあるな…」
空を仰ぎます。「この先、まだまだアップダウンがあるな…」
 1
1
5/24 12:46
空を仰ぎます。「この先、まだまだアップダウンがあるな…」
 この花は何でしょう?サラサドウダン?
この花は何でしょう?サラサドウダン?
 0
0
5/24 12:50
この花は何でしょう?サラサドウダン?
 ミツバノバイカオウレンは、この辺りにだけ見かけました♪
ミツバノバイカオウレンは、この辺りにだけ見かけました♪
 7
7
5/24 12:37
ミツバノバイカオウレンは、この辺りにだけ見かけました♪
 眼下に「大障子避難小屋」が見えてきました。鞍部の少し手前にあります。登山道は歩きやすいです。
眼下に「大障子避難小屋」が見えてきました。鞍部の少し手前にあります。登山道は歩きやすいです。
 3
3
5/24 12:55
眼下に「大障子避難小屋」が見えてきました。鞍部の少し手前にあります。登山道は歩きやすいです。
 【大障子避難小屋を通過】
【大障子避難小屋を通過】
12時56分、「大障子避難小屋(1700m)を通過します。築年は1992年、収容人数10人です。水場は小屋前方20mから左へ下った沢水(往復20分)。トイレ無し。
 1
1
5/24 12:56
【大障子避難小屋を通過】
12時56分、「大障子避難小屋(1700m)を通過します。築年は1992年、収容人数10人です。水場は小屋前方20mから左へ下った沢水(往復20分)。トイレ無し。
 「大障子避難小屋」からは少し下った後、手前の小ピークの向こうが『小障子ノ頭』となります。
「大障子避難小屋」からは少し下った後、手前の小ピークの向こうが『小障子ノ頭』となります。
 0
0
5/24 12:57
「大障子避難小屋」からは少し下った後、手前の小ピークの向こうが『小障子ノ頭』となります。
 ミヤマダイコンソウを眺めながら、斜面を登ります…
ミヤマダイコンソウを眺めながら、斜面を登ります…
 2
2
5/24 12:59
ミヤマダイコンソウを眺めながら、斜面を登ります…
 ●
●
*13時01分、「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間の小ピークから、後方を振り返りました。
 1
1
5/24 13:02
●
*13時01分、「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間の小ピークから、後方を振り返りました。
 ●●
●●
 1
1
5/24 13:02
●●
 ●●●
●●●
*中央に『大障子ノ頭(1800m)』のピーク、そこから登山道が続いて中腹に「大障子避難小屋(1700m)」が見えます。
 5
5
5/24 13:02
●●●
*中央に『大障子ノ頭(1800m)』のピーク、そこから登山道が続いて中腹に「大障子避難小屋(1700m)」が見えます。
 ●●●●
●●●●
 1
1
5/24 13:02
●●●●
 ゆるいアップダウンの中、気持ちのいい笹原を歩きます。『小障子ノ頭』ピークまであと少しです。
ゆるいアップダウンの中、気持ちのいい笹原を歩きます。『小障子ノ頭』ピークまであと少しです。
 0
0
5/24 13:08
ゆるいアップダウンの中、気持ちのいい笹原を歩きます。『小障子ノ頭』ピークまであと少しです。
 「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間でも、またハクサンイチゲの群落に出会いました(^^)
「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間でも、またハクサンイチゲの群落に出会いました(^^)
 11
11
5/24 13:11
「大障子避難小屋→小障子ノ頭」区間でも、またハクサンイチゲの群落に出会いました(^^)
 【小障子ノ頭に到着】
【小障子ノ頭に到着】
13時14分、『小障子ノ頭』に到着しました。特に何もありません。そのまま通過します。
 0
0
5/24 13:14
【小障子ノ頭に到着】
13時14分、『小障子ノ頭』に到着しました。特に何もありません。そのまま通過します。
 『小障子ノ頭』からは少し下ってから『オジカ沢ノ頭』へのややツライ登りとなります。ずっとアップダウンが続いているため、足取りもしだいに重くなってきています(>_<)
『小障子ノ頭』からは少し下ってから『オジカ沢ノ頭』へのややツライ登りとなります。ずっとアップダウンが続いているため、足取りもしだいに重くなってきています(>_<)
 0
0
5/24 13:15
『小障子ノ頭』からは少し下ってから『オジカ沢ノ頭』へのややツライ登りとなります。ずっとアップダウンが続いているため、足取りもしだいに重くなってきています(>_<)
 ●
●
*13時16分、「小障子ノ頭→オジカ沢ノ頭」区間を歩いています。
 1
1
5/24 13:16
●
*13時16分、「小障子ノ頭→オジカ沢ノ頭」区間を歩いています。
 ●●
●●
*左に『茂倉岳(1977.9m)』、ほぼ中央に『一ノ倉岳(1974.2m)』…
 3
3
5/24 13:17
●●
*左に『茂倉岳(1977.9m)』、ほぼ中央に『一ノ倉岳(1974.2m)』…
 ●●●
●●●
*『オジカ沢ノ頭(1890m)』です。この先でなかなかの登りが待ち構えています。ここからですと、奥の『谷川岳(1963m)』が見えません。
 2
2
5/24 13:17
●●●
*『オジカ沢ノ頭(1890m)』です。この先でなかなかの登りが待ち構えています。ここからですと、奥の『谷川岳(1963m)』が見えません。
 ●●●●
●●●●
 1
1
5/24 13:17
●●●●
 13時23分、鞍部を経て、いよいよ『オジカ沢ノ頭』への長い登りが始まりました。疲れがたまっており、しょっちゅう立ち止まっては水ばかり飲んでいました(*_*)
13時23分、鞍部を経て、いよいよ『オジカ沢ノ頭』への長い登りが始まりました。疲れがたまっており、しょっちゅう立ち止まっては水ばかり飲んでいました(*_*)
 0
0
5/24 13:23
13時23分、鞍部を経て、いよいよ『オジカ沢ノ頭』への長い登りが始まりました。疲れがたまっており、しょっちゅう立ち止まっては水ばかり飲んでいました(*_*)
 「あぁ、ツライ…。ピークに着いたら絶対に休憩するぞ…」
「あぁ、ツライ…。ピークに着いたら絶対に休憩するぞ…」
 1
1
5/24 13:27
「あぁ、ツライ…。ピークに着いたら絶対に休憩するぞ…」
 【オジカ沢ノ頭避難小屋】
【オジカ沢ノ頭避難小屋】
13時44分、「オジカ沢ノ頭避難小屋」を通過します。山頂までは距離にしてあと100mほどです。築年は1995年、収容人数5人。トイレ・水場無し。
 1
1
5/24 13:44
【オジカ沢ノ頭避難小屋】
13時44分、「オジカ沢ノ頭避難小屋」を通過します。山頂までは距離にしてあと100mほどです。築年は1995年、収容人数5人。トイレ・水場無し。
 【オジカ沢ノ頭に到着】
【オジカ沢ノ頭に到着】
13時47分、つらい登りの末に『オジカ沢ノ頭(1890m)』に到着です。「あぁ、もうダメだ。休憩しよう…」
 2
2
5/24 13:47
【オジカ沢ノ頭に到着】
13時47分、つらい登りの末に『オジカ沢ノ頭(1890m)』に到着です。「あぁ、もうダメだ。休憩しよう…」
 【波打つ稜線・霞の向こう①】
【波打つ稜線・霞の向こう①】
『オジカ沢ノ頭』ピークで休憩をしながら、後方の風景を見回しました。霞のずっと向こうには、この日歩いてきた稜線がうねっていました。こちらは南の方角。
 1
1
5/24 13:47
【波打つ稜線・霞の向こう①】
『オジカ沢ノ頭』ピークで休憩をしながら、後方の風景を見回しました。霞のずっと向こうには、この日歩いてきた稜線がうねっていました。こちらは南の方角。
 【波打つ稜線・霞の向こう②】
【波打つ稜線・霞の向こう②】
そこから右回転、南西の方角。手前がたったいま上がってきた登山道、正面には『俎嵓』がそびえています。
 3
3
5/24 13:47
【波打つ稜線・霞の向こう②】
そこから右回転、南西の方角。手前がたったいま上がってきた登山道、正面には『俎嵓』がそびえています。
 【波打つ稜線・霞の向こう③】
【波打つ稜線・霞の向こう③】
さらに右回転、西の方角。左下から稜線が伸びていき、右上の『万太郎山(1954.1m)』まで達しています。
 7
7
5/24 13:47
【波打つ稜線・霞の向こう③】
さらに右回転、西の方角。左下から稜線が伸びていき、右上の『万太郎山(1954.1m)』まで達しています。
 【波打つ稜線・霞の向こう④】
【波打つ稜線・霞の向こう④】
さらに右回転、北西の方角。その万太郎山から派生して右へと落ちていく尾根が「吾策新道」になります。いや~、歩きましたね…
 1
1
5/24 13:48
【波打つ稜線・霞の向こう④】
さらに右回転、北西の方角。その万太郎山から派生して右へと落ちていく尾根が「吾策新道」になります。いや~、歩きましたね…
 13時57分、休憩を終えて『オジカ沢ノ頭』を後にします。次のポイントはいよいよ『谷川岳(1963m)』です。
13時57分、休憩を終えて『オジカ沢ノ頭』を後にします。次のポイントはいよいよ『谷川岳(1963m)』です。
 1
1
5/24 13:57
13時57分、休憩を終えて『オジカ沢ノ頭』を後にします。次のポイントはいよいよ『谷川岳(1963m)』です。
 【痩せ岩場に注意】
【痩せ岩場に注意】
オジカ沢ノ頭周辺では「痩せ岩場」を歩きます。小さな岩峰を右に巻いたり左に巻いたりしながら進みます。時には急斜面の下りもあります。
 0
0
5/24 14:01
【痩せ岩場に注意】
オジカ沢ノ頭周辺では「痩せ岩場」を歩きます。小さな岩峰を右に巻いたり左に巻いたりしながら進みます。時には急斜面の下りもあります。
 もちろん足元は谷底まで切れ落ちています。この区間は十分な注意が必要です(*_*)
もちろん足元は谷底まで切れ落ちています。この区間は十分な注意が必要です(*_*)
 4
4
5/24 14:01
もちろん足元は谷底まで切れ落ちています。この区間は十分な注意が必要です(*_*)
 シャクナゲを横目にしながら、痩せ岩場を歩き続けます。
シャクナゲを横目にしながら、痩せ岩場を歩き続けます。
 2
2
5/24 14:03
シャクナゲを横目にしながら、痩せ岩場を歩き続けます。
 ●
●
*14時11分、「オジカ沢ノ頭→谷川岳」区間を歩いています。中央のピーク『茂倉岳(1977.9m)』がよく見えました。
 1
1
5/24 14:11
●
*14時11分、「オジカ沢ノ頭→谷川岳」区間を歩いています。中央のピーク『茂倉岳(1977.9m)』がよく見えました。
 ●●
●●
*写真の右に見える尾根を登り切ると、谷川岳「肩の小屋(1940m)」に着きます。
 2
2
5/24 14:11
●●
*写真の右に見える尾根を登り切ると、谷川岳「肩の小屋(1940m)」に着きます。
 ●●●
●●●
*中央には『天神山(1502m)』が見えます。
 0
0
5/24 14:11
●●●
*中央には『天神山(1502m)』が見えます。
 ●●●●
●●●●
*群馬県側、上空に暗雲が漂ってきました。
 1
1
5/24 14:11
●●●●
*群馬県側、上空に暗雲が漂ってきました。
 茂倉岳
茂倉岳
ズーム写真1
 1
1
5/24 14:04
茂倉岳
ズーム写真1
 茂倉岳
茂倉岳
ズーム写真2
 0
0
5/24 14:04
茂倉岳
ズーム写真2
 茂倉岳
茂倉岳
ズーム写真3
 0
0
5/24 14:04
茂倉岳
ズーム写真3
 茂倉岳
茂倉岳
ズーム写真4
 0
0
5/24 14:04
茂倉岳
ズーム写真4
 シャクナゲが咲く登山道を歩き続けます。疲れてはいますが、登山道自体に危険はなく、歩きやすいです。
シャクナゲが咲く登山道を歩き続けます。疲れてはいますが、登山道自体に危険はなく、歩きやすいです。
 4
4
5/24 14:18
シャクナゲが咲く登山道を歩き続けます。疲れてはいますが、登山道自体に危険はなく、歩きやすいです。
 右手には『俎嵓』が迫力ある姿を見せています。
右手には『俎嵓』が迫力ある姿を見せています。
 0
0
5/24 14:23
右手には『俎嵓』が迫力ある姿を見せています。
 【中ゴー尾根分岐点】
【中ゴー尾根分岐点】
14時27分、「中ゴー尾根」との分岐点に到着です。
 0
0
5/24 14:27
【中ゴー尾根分岐点】
14時27分、「中ゴー尾根」との分岐点に到着です。
 ここに注意をうながす看板がありました。「中ゴー尾根」は危険なんですね…
ここに注意をうながす看板がありました。「中ゴー尾根」は危険なんですね…
 1
1
5/24 14:28
ここに注意をうながす看板がありました。「中ゴー尾根」は危険なんですね…
 ●
●
*「中ゴー尾根分岐点」から少し斜面を登り、後方を振り返りました。左のピークが『俎嵓』になります。
 0
0
5/24 14:31
●
*「中ゴー尾根分岐点」から少し斜面を登り、後方を振り返りました。左のピークが『俎嵓』になります。
 ●●
●●
*中央のピーク『オジカ沢ノ頭(1890m)』です。右肩の奥には『万太郎山』山頂直下の岩峰群が見えます。
 2
2
5/24 14:31
●●
*中央のピーク『オジカ沢ノ頭(1890m)』です。右肩の奥には『万太郎山』山頂直下の岩峰群が見えます。
 ●●●
●●●
*こちらは「万太郎谷」になります。
 0
0
5/24 14:31
●●●
*こちらは「万太郎谷」になります。
 ●●●●
●●●●
*中央のピークが『茂倉岳(1977.9m)』です。
 2
2
5/24 14:31
●●●●
*中央のピークが『茂倉岳(1977.9m)』です。
 ●
●
*同じく「中ゴー尾根分岐点」から少し先で、今度は進行方向を見回しました。
 0
0
5/24 14:35
●
*同じく「中ゴー尾根分岐点」から少し先で、今度は進行方向を見回しました。
 ●●
●●
*中央の少し左に『一ノ倉岳(1974.2m)』のなだらかなピークが見えます。
 0
0
5/24 14:35
●●
*中央の少し左に『一ノ倉岳(1974.2m)』のなだらかなピークが見えます。
 ●●●
●●●
*こちらが進行方向です。谷川岳「肩の小屋」まであと一息といった感じです。
 2
2
5/24 14:35
●●●
*こちらが進行方向です。谷川岳「肩の小屋」まであと一息といった感じです。
 ●●●●
●●●●
 0
0
5/24 14:35
●●●●
 ここさえ登れば「肩の小屋」ですね…
ここさえ登れば「肩の小屋」ですね…
 0
0
5/24 14:42
ここさえ登れば「肩の小屋」ですね…
 小石混じりの登山道、歩きやすいです。
小石混じりの登山道、歩きやすいです。
 2
2
5/24 14:43
小石混じりの登山道、歩きやすいです。
 【肩の小屋に到着】
【肩の小屋に到着】
14時47分、谷川岳「肩の小屋(1940m)」に到着しました。万太郎山からここまで3時間ちょっとでした。
 2
2
5/24 14:47
【肩の小屋に到着】
14時47分、谷川岳「肩の小屋(1940m)」に到着しました。万太郎山からここまで3時間ちょっとでした。
 「肩の小屋」のすぐそばに展望台のような場所があります。そこからの風景を眺めました。「だいぶ歩きましたね…」
「肩の小屋」のすぐそばに展望台のような場所があります。そこからの風景を眺めました。「だいぶ歩きましたね…」
 0
0
5/24 14:46
「肩の小屋」のすぐそばに展望台のような場所があります。そこからの風景を眺めました。「だいぶ歩きましたね…」
 ●
●
 0
0
5/24 14:46
●
 ●●
●●
 2
2
5/24 14:46
●●
 ●●●
●●●
 0
0
5/24 14:46
●●●
 ●●●●
●●●●
 0
0
5/24 14:46
●●●●
 「肩の小屋」の周りに登山者は誰もいません。ひっそりしていました。
「肩の小屋」の周りに登山者は誰もいません。ひっそりしていました。
 0
0
5/24 14:48
「肩の小屋」の周りに登山者は誰もいません。ひっそりしていました。
 休憩をせずに「肩の小屋」を後にし、そのまま「トマノ耳」に向かいます。
休憩をせずに「肩の小屋」を後にし、そのまま「トマノ耳」に向かいます。
 2
2
5/24 14:49
休憩をせずに「肩の小屋」を後にし、そのまま「トマノ耳」に向かいます。
 階段を登り…
階段を登り…
 0
0
5/24 14:50
階段を登り…
 【谷川岳・トマノ耳に到着】
【谷川岳・トマノ耳に到着】
14時53分、あっという間に「トマノ耳(1963m)」に到着です。ここにも誰もいません。「こんなに静かな谷川岳は初めてだ…」
 8
8
5/24 14:53
【谷川岳・トマノ耳に到着】
14時53分、あっという間に「トマノ耳(1963m)」に到着です。ここにも誰もいません。「こんなに静かな谷川岳は初めてだ…」
 【トマノ耳からの展望①】
【トマノ耳からの展望①】
まずは北西の方角。写真の右に『茂倉岳(1977.9m)』、万太郎谷の上に見える一番手前の山は『高津倉山(1181m)』ですね…
 1
1
5/24 14:54
【トマノ耳からの展望①】
まずは北西の方角。写真の右に『茂倉岳(1977.9m)』、万太郎谷の上に見える一番手前の山は『高津倉山(1181m)』ですね…
 【トマノ耳からの展望②】
【トマノ耳からの展望②】
そこから右回転、北の方角。左に『一ノ倉岳(1974.2m)』、中央に谷川岳「オキノ耳(1977m)」、その右奥に『巻機山(1967m)』…
 5
5
5/24 14:54
【トマノ耳からの展望②】
そこから右回転、北の方角。左に『一ノ倉岳(1974.2m)』、中央に谷川岳「オキノ耳(1977m)」、その右奥に『巻機山(1967m)』…
 【トマノ耳からの展望③】
【トマノ耳からの展望③】
さらに右回転、北東の方角。左の一番高いピーク『朝日岳(1945.3m)』、写真のほぼ中央に『白毛門(1720m)』、右端の奥にうっすらと『至仏山(2228.1m)』…
 2
2
5/24 14:54
【トマノ耳からの展望③】
さらに右回転、北東の方角。左の一番高いピーク『朝日岳(1945.3m)』、写真のほぼ中央に『白毛門(1720m)』、右端の奥にうっすらと『至仏山(2228.1m)』…
 【トマノ耳からの展望④】
【トマノ耳からの展望④】
さらに右回転、東の方角。中央にうっすらと見えるのは『武尊山(2158m)』ではないかと思います。
 1
1
5/24 14:54
【トマノ耳からの展望④】
さらに右回転、東の方角。中央にうっすらと見えるのは『武尊山(2158m)』ではないかと思います。
 【群馬県側・見えない】
【群馬県側・見えない】
残念ながら、群馬県側は霞んでいて景色が見えませんでした。「そろそろ行きますか…」
 2
2
5/24 14:55
【群馬県側・見えない】
残念ながら、群馬県側は霞んでいて景色が見えませんでした。「そろそろ行きますか…」
 さて、すぐ隣の「オキノ耳」に向かいます。この途中、男女2人のペアとスライドしました。
さて、すぐ隣の「オキノ耳」に向かいます。この途中、男女2人のペアとスライドしました。
 0
0
5/24 14:58
さて、すぐ隣の「オキノ耳」に向かいます。この途中、男女2人のペアとスライドしました。
 岩場を越えて…
岩場を越えて…
 0
0
5/24 15:01
岩場を越えて…
 【谷川岳・オキノ耳に到着】
【谷川岳・オキノ耳に到着】
15時06分、谷川岳「オキノ耳(1977m)」に到着です。ここにも誰一人としていませんでした。静かです…
 6
6
5/24 15:06
【谷川岳・オキノ耳に到着】
15時06分、谷川岳「オキノ耳(1977m)」に到着です。ここにも誰一人としていませんでした。静かです…
 【オキノ耳から主稜線①】
【オキノ耳から主稜線①】
「オキノ耳」から主脈となる縦走路を眺めました。
 1
1
5/24 15:06
【オキノ耳から主稜線①】
「オキノ耳」から主脈となる縦走路を眺めました。
 【オキノ耳から主稜線②】
【オキノ耳から主稜線②】
左のピークがつい先ほど立っていた「トマノ耳(1963m)」、その右に見えるのはきっと『阿能川岳(1611.3m)』ですね…
 5
5
5/24 15:06
【オキノ耳から主稜線②】
左のピークがつい先ほど立っていた「トマノ耳(1963m)」、その右に見えるのはきっと『阿能川岳(1611.3m)』ですね…
 【オキノ耳から主稜線③】
【オキノ耳から主稜線③】
左から右へと主稜線がつながって右のピーク『オジカ沢ノ頭(1890m)』に達し…
 5
5
5/24 15:06
【オキノ耳から主稜線③】
左から右へと主稜線がつながって右のピーク『オジカ沢ノ頭(1890m)』に達し…
 【オキノ耳から主稜線④】
【オキノ耳から主稜線④】
さらにこの縦走路が左端の『万太郎山(1954.1m)』、そして一番奥の『仙ノ倉山(2026.2m)』のさらに向こうまで続くのです。
 1
1
5/24 15:06
【オキノ耳から主稜線④】
さらにこの縦走路が左端の『万太郎山(1954.1m)』、そして一番奥の『仙ノ倉山(2026.2m)』のさらに向こうまで続くのです。
 さて、「オキノ耳」を後にして歩き続けます。
さて、「オキノ耳」を後にして歩き続けます。
 0
0
5/24 15:08
さて、「オキノ耳」を後にして歩き続けます。
 「オキノ耳」周辺もシャクナゲがキレイでした(^^)
「オキノ耳」周辺もシャクナゲがキレイでした(^^)
 3
3
5/24 15:09
「オキノ耳」周辺もシャクナゲがキレイでした(^^)
 「富士浅間神社奥宮」の鳥居をくぐります。
「富士浅間神社奥宮」の鳥居をくぐります。
 4
4
5/24 15:12
「富士浅間神社奥宮」の鳥居をくぐります。
 鳥居周辺には「万太郎谷」方面に切れ落ちた箇所があります。慎重に歩きます…
鳥居周辺には「万太郎谷」方面に切れ落ちた箇所があります。慎重に歩きます…
 0
0
5/24 15:14
鳥居周辺には「万太郎谷」方面に切れ落ちた箇所があります。慎重に歩きます…
 ●
●
*15時18分、「オキノ耳→一ノ倉岳」区間を歩いています。
 1
1
5/24 15:18
●
*15時18分、「オキノ耳→一ノ倉岳」区間を歩いています。
 ●●
●●
 2
2
5/24 15:18
●●
 ●●●
●●●
*こちらが『一ノ倉岳(1974.2m)』です。この先で一度鞍部へ下り、そこからの登り返しがキツイのです(*_*)
 1
1
5/24 15:18
●●●
*こちらが『一ノ倉岳(1974.2m)』です。この先で一度鞍部へ下り、そこからの登り返しがキツイのです(*_*)
 ●●●●
●●●●
 1
1
5/24 15:18
●●●●
 高度感あるレリーフ脇を通過し…
高度感あるレリーフ脇を通過し…
 3
3
5/24 15:20
高度感あるレリーフ脇を通過し…
 【ノゾキに到着】
【ノゾキに到着】
15時30分、「ノゾキ」にやって来ました。
 0
0
5/24 15:30
【ノゾキに到着】
15時30分、「ノゾキ」にやって来ました。
 お約束通りに「ノゾキ」から「一ノ倉沢」を覗きます。雪崩れに磨かれた迫力ある岩肌を観賞しました。
お約束通りに「ノゾキ」から「一ノ倉沢」を覗きます。雪崩れに磨かれた迫力ある岩肌を観賞しました。
 7
7
5/24 15:30
お約束通りに「ノゾキ」から「一ノ倉沢」を覗きます。雪崩れに磨かれた迫力ある岩肌を観賞しました。
 『一ノ倉岳』への登り返しが始まりました。灌木の中、急登を進みます(*_*)
『一ノ倉岳』への登り返しが始まりました。灌木の中、急登を進みます(*_*)
 0
0
5/24 15:35
『一ノ倉岳』への登り返しが始まりました。灌木の中、急登を進みます(*_*)
 ●
●
*『一ノ倉岳』に向かって斜面を登っている途中、後方の「オキノ耳」を振り返ります。
 0
0
5/24 15:42
●
*『一ノ倉岳』に向かって斜面を登っている途中、後方の「オキノ耳」を振り返ります。
 ●●
●●
*東面は「荒々しい岩場」、西面は「なだらかな斜面」となっている「非対称山稜」を目にしました。
 14
14
5/24 15:42
●●
*東面は「荒々しい岩場」、西面は「なだらかな斜面」となっている「非対称山稜」を目にしました。
 ●●●
●●●
 0
0
5/24 15:42
●●●
 ●●●●
●●●●
 0
0
5/24 15:42
●●●●
 【水が無くなりピンチ】
【水が無くなりピンチ】
ここにきて、2L持ってきた水が底をついてきました。「茂倉岳避難小屋の水場は活きているだろうか。あそこで水がなかったら、残雪を食べながら歩き続けるしかない…」
 8
8
5/24 15:45
【水が無くなりピンチ】
ここにきて、2L持ってきた水が底をついてきました。「茂倉岳避難小屋の水場は活きているだろうか。あそこで水がなかったら、残雪を食べながら歩き続けるしかない…」
 ゴツゴツした岩混じりの斜面を登り続け…
ゴツゴツした岩混じりの斜面を登り続け…
 0
0
5/24 15:49
ゴツゴツした岩混じりの斜面を登り続け…
 【一ノ倉岳山頂を通過】
【一ノ倉岳山頂を通過】
15時51分、『一ノ倉岳(1974.2m)』に到着しました。山頂の一角に「一ノ倉岳避難小屋」があります。築年は1963年、収容人数は3人。無人。トイレ無し、水場無し。
 6
6
5/24 15:51
【一ノ倉岳山頂を通過】
15時51分、『一ノ倉岳(1974.2m)』に到着しました。山頂の一角に「一ノ倉岳避難小屋」があります。築年は1963年、収容人数は3人。無人。トイレ無し、水場無し。
 一ノ倉岳山頂を通過して、そのまま茂倉岳へと歩き続けます。進むごとに右手側、笹原の向こうの展望が開けてきました。
一ノ倉岳山頂を通過して、そのまま茂倉岳へと歩き続けます。進むごとに右手側、笹原の向こうの展望が開けてきました。
 0
0
5/24 15:52
一ノ倉岳山頂を通過して、そのまま茂倉岳へと歩き続けます。進むごとに右手側、笹原の向こうの展望が開けてきました。
 ●
●
*15時53分、「一ノ倉岳→茂倉岳」区間を歩いています。右手側、笹原の向こう側の風景です。正面に大きく『武能岳(1759.6m)』、右端に鋭峰『大源太山(1598m)』…
 0
0
5/24 15:53
●
*15時53分、「一ノ倉岳→茂倉岳」区間を歩いています。右手側、笹原の向こう側の風景です。正面に大きく『武能岳(1759.6m)』、右端に鋭峰『大源太山(1598m)』…
 ●●
●●
*左の奥に『巻機山(1967m)』、その真下に『七つ小屋山(1674.7m)』でそこから右へ「清水峠」を経て「ジャンクションピーク」へと馬蹄形縦走路が続きます。
 3
3
5/24 15:53
●●
*左の奥に『巻機山(1967m)』、その真下に『七つ小屋山(1674.7m)』でそこから右へ「清水峠」を経て「ジャンクションピーク」へと馬蹄形縦走路が続きます。
 ●●●
●●●
*左から『朝日岳(1945.3m)』『笠ヶ岳(1852.1)』と並び、右に低く『白毛門(1720m)』が見えます。
 1
1
5/24 15:53
●●●
*左から『朝日岳(1945.3m)』『笠ヶ岳(1852.1)』と並び、右に低く『白毛門(1720m)』が見えます。
 ●●●●
●●●●
 1
1
5/24 15:53
●●●●
 ●
●
*15時56分、茂倉岳手前にやってきました。
 1
1
5/24 15:56
●
*15時56分、茂倉岳手前にやってきました。
 ●●
●●
*こちらが『茂倉岳(1977.9m)』になります。なだらかな山容です。
 6
6
5/24 15:56
●●
*こちらが『茂倉岳(1977.9m)』になります。なだらかな山容です。
 ●●●
●●●
 2
2
5/24 15:56
●●●
 ●●●●
●●●●
 0
0
5/24 15:56
●●●●
 この辺りで少しだけ雪道を歩きましたが、何も問題はありませんでした。
この辺りで少しだけ雪道を歩きましたが、何も問題はありませんでした。
 0
0
5/24 15:57
この辺りで少しだけ雪道を歩きましたが、何も問題はありませんでした。
 茂倉岳への登りの途中でも、ハクサンイチゲの群落に出会いました~(^^)/
茂倉岳への登りの途中でも、ハクサンイチゲの群落に出会いました~(^^)/
 8
8
5/24 16:03
茂倉岳への登りの途中でも、ハクサンイチゲの群落に出会いました~(^^)/
 【茂倉岳山頂に到着】
【茂倉岳山頂に到着】
16時18分、『茂倉岳(1977.9m)』に到着です。谷川岳「トマノ耳」からここまで、およそ1時間20分でした。誰もいませんね…
 4
4
5/24 16:08
【茂倉岳山頂に到着】
16時18分、『茂倉岳(1977.9m)』に到着です。谷川岳「トマノ耳」からここまで、およそ1時間20分でした。誰もいませんね…
 そのまま山頂を通過して、「茂倉新道」から下山を始めます。
そのまま山頂を通過して、「茂倉新道」から下山を始めます。
 2
2
5/24 16:09
そのまま山頂を通過して、「茂倉新道」から下山を始めます。
 ●
●
*「茂倉岳→登山口・土樽」区間を歩いています。左手側、茂倉岳山頂付近から見た「万太郎谷」は美しい風景でした。
 3
3
5/24 16:10
●
*「茂倉岳→登山口・土樽」区間を歩いています。左手側、茂倉岳山頂付近から見た「万太郎谷」は美しい風景でした。
 ●●
●●
*こちらがその「万太郎谷」です。正面には『オジカ沢ノ頭(1890m)』があります。
 1
1
5/24 16:10
●●
*こちらがその「万太郎谷」です。正面には『オジカ沢ノ頭(1890m)』があります。
 ●●●
●●●
*こちらは進行方向です。右端の白い雪の中に「茂倉岳避難小屋」が見えます。中央の少し左、鋭く『万太郎山(1954.1m)』の姿も見えます。
 0
0
5/24 16:10
●●●
*こちらは進行方向です。右端の白い雪の中に「茂倉岳避難小屋」が見えます。中央の少し左、鋭く『万太郎山(1954.1m)』の姿も見えます。
 ●●●●
●●●●
 0
0
5/24 16:10
●●●●
 【水場へと急ぐ…】
【水場へと急ぐ…】
茂倉岳避難小屋を横目に、雪の斜面を下ります。まずは「水場」へ急ぎます。
 1
1
5/24 16:17
【水場へと急ぐ…】
茂倉岳避難小屋を横目に、雪の斜面を下ります。まずは「水場」へ急ぎます。
 果たして水場はどうなっているでしょうか?
果たして水場はどうなっているでしょうか?
おや!水が流れる音が聞こえてきますよ…
 0
0
5/24 16:17
果たして水場はどうなっているでしょうか?
おや!水が流れる音が聞こえてきますよ…
 【活きていた水場】
【活きていた水場】
水場に着くと、雪融けしたばかりの冷たい水がジャバジャバと流れていました。ここでゴクゴクと1Lほど飲み、そして顔を洗いました。
 8
8
5/24 16:17
【活きていた水場】
水場に着くと、雪融けしたばかりの冷たい水がジャバジャバと流れていました。ここでゴクゴクと1Lほど飲み、そして顔を洗いました。
 「いや~、生き返った!」大量の水を飲み、さらに水筒も満タンにしましたので、安心して下山を続けます。
「いや~、生き返った!」大量の水を飲み、さらに水筒も満タンにしましたので、安心して下山を続けます。
 2
2
5/24 16:19
「いや~、生き返った!」大量の水を飲み、さらに水筒も満タンにしましたので、安心して下山を続けます。
 【茂倉岳避難小屋を通過】
【茂倉岳避難小屋を通過】
16時21分、「茂倉岳避難小屋(1880m)」を通過します。この小屋は築年が1994年、収容人数20人。無人。トイレあり。水場あり。
 7
7
5/24 16:21
【茂倉岳避難小屋を通過】
16時21分、「茂倉岳避難小屋(1880m)」を通過します。この小屋は築年が1994年、収容人数20人。無人。トイレあり。水場あり。
 ここから登山口の土樽まで、標高差はおよそ1380m。うんざりするほど斜面を下り続けます。下りはじめにはザレた場所もあり、注意が必要です(*_*)
ここから登山口の土樽まで、標高差はおよそ1380m。うんざりするほど斜面を下り続けます。下りはじめにはザレた場所もあり、注意が必要です(*_*)
 3
3
5/24 16:24
ここから登山口の土樽まで、標高差はおよそ1380m。うんざりするほど斜面を下り続けます。下りはじめにはザレた場所もあり、注意が必要です(*_*)
 16時55分、「矢場ノ頭(1490m)」を通過。
16時55分、「矢場ノ頭(1490m)」を通過。
 1
1
5/24 16:55
16時55分、「矢場ノ頭(1490m)」を通過。
 「矢場ノ頭」から先は、こうして石がゴロゴロしていたり…
「矢場ノ頭」から先は、こうして石がゴロゴロしていたり…
 0
0
「矢場ノ頭」から先は、こうして石がゴロゴロしていたり…
 また、こんな木の根が張り出した登山道が嫌というほど続きます。
また、こんな木の根が張り出した登山道が嫌というほど続きます。
 1
1
5/24 17:04
また、こんな木の根が張り出した登山道が嫌というほど続きます。
 「あぁ、長い下り…。まだ終わらない…」展望は全く利かず、うんざりです(*_*)
「あぁ、長い下り…。まだ終わらない…」展望は全く利かず、うんざりです(*_*)
 1
1
5/24 17:05
「あぁ、長い下り…。まだ終わらない…」展望は全く利かず、うんざりです(*_*)
 これでもかと言うほど斜面を下り続け、ようやく下の方から「関越自動車道」の騒音が聞こえ始め、そしてブナの美林が見え始めます。「あぁ、あと少しだ…」
これでもかと言うほど斜面を下り続け、ようやく下の方から「関越自動車道」の騒音が聞こえ始め、そしてブナの美林が見え始めます。「あぁ、あと少しだ…」
 4
4
5/24 17:35
これでもかと言うほど斜面を下り続け、ようやく下の方から「関越自動車道」の騒音が聞こえ始め、そしてブナの美林が見え始めます。「あぁ、あと少しだ…」
 【茂倉岳登山口に到着】
【茂倉岳登山口に到着】
17時53分、やっとのことで土樽の「茂倉新道・登山口」にたどり着きました。「茂倉岳避難小屋」からは、およそ1時間30分でした。
 2
2
5/24 17:53
【茂倉岳登山口に到着】
17時53分、やっとのことで土樽の「茂倉新道・登山口」にたどり着きました。「茂倉岳避難小屋」からは、およそ1時間30分でした。
 【安全登山の広場に到着】
【安全登山の広場に到着】
18時05分、車道を歩いて「安全登山の広場」に無事戻りました。もう辺りも暗くなってきています。
 2
2
5/24 18:05
【安全登山の広場に到着】
18時05分、車道を歩いて「安全登山の広場」に無事戻りました。もう辺りも暗くなってきています。
 朝7時すぎから歩き始め、トータル11時間の長い山旅でしたね。安心したせいか、どっと疲れが出てきました…(*_*)
朝7時すぎから歩き始め、トータル11時間の長い山旅でしたね。安心したせいか、どっと疲れが出てきました…(*_*)
 2
2
5/24 18:06
朝7時すぎから歩き始め、トータル11時間の長い山旅でしたね。安心したせいか、どっと疲れが出てきました…(*_*)
 【バックショット】
【バックショット】
万太郎山への登りは想像以上にハードでした。ですが、咲き始めた花たちや残雪の山々、そして谷川連峰らしい波打つ稜線が楽しめました。それでは、また~(^^)/
 16
16
5/24 12:01
【バックショット】
万太郎山への登りは想像以上にハードでした。ですが、咲き始めた花たちや残雪の山々、そして谷川連峰らしい波打つ稜線が楽しめました。それでは、また~(^^)/


 Forest21
Forest21




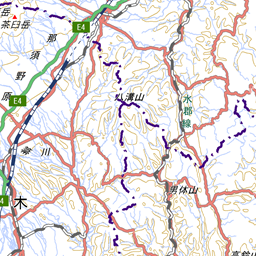




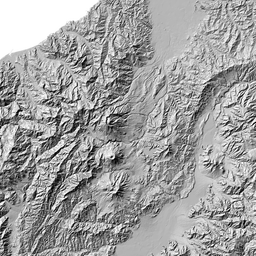



 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手

























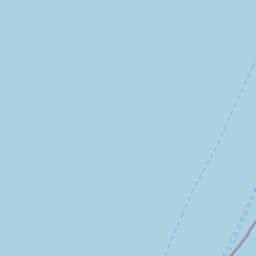
















いいねした人